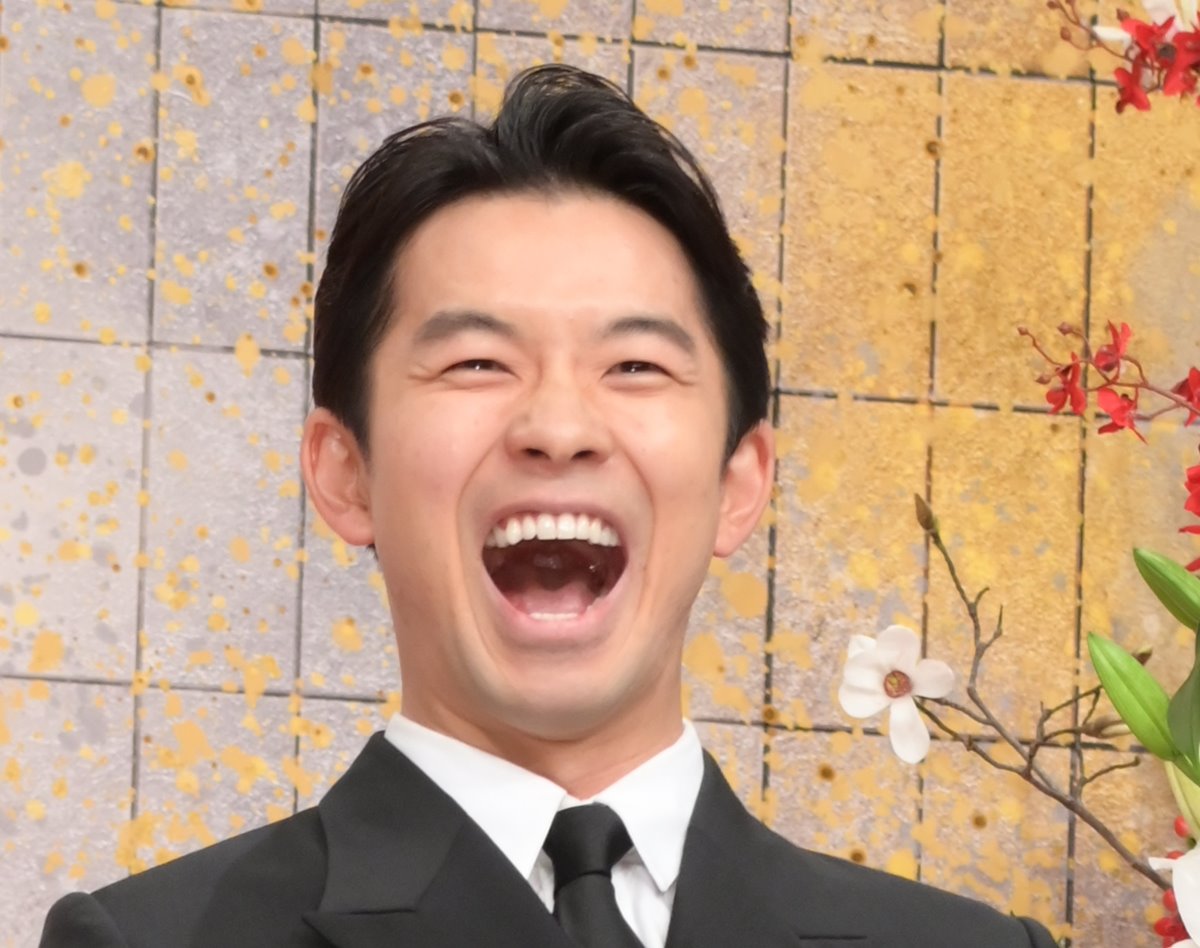画家・博さん(55)、作曲家・明さん(52)、ヴァイオリニスト・真理子さん(51)と、芸術家“千住3兄妹”を育て上げた教育評論家・千住文子さんが、6月27日に永眠(享年87)された。
それから、真理子さんは「母との時間」のすべてを思い出していた。母と二人三脚で厳しい練習を重ねた日々、天才と呼ばれるプレッシャーから楽器を手放した時期、2度の離婚も、母の存在抜きには語れない。
真理子さんは、2歳3カ月でヴァイオリンを習い始めた。最初の母娘の転機は小3のとき。小4から出られるコンクールへの出場が決まると、文子さんの態度が一変した。「出るのなら頑張りなさい。練習しないならやめなさい」と、母の眼の色が変わったのを真理子さんは覚えている。練習法も実にユニーク。
「ヘンデルのソナタの最初に1音ずつ上がっていくところを、私は表現できない。すると、母が即興でミュージカルを始めたんですよ。階段を上がったり下がったりして、『3分の間に物語がある』と。それが終わると、『次はあなたの番ね。どう表現するか、ヴァイオリンでやってみて』」(真理子さん・以下同)
母の世界に引き込まれて、自然に頑張ることができた。母は「わあ、すごい。真理ちゃん、よくなった!」と必ず褒めてくれた。気づけば、母と2人で頂点を目指し走りだしていた。小4の最初のチャレンジは2位、翌年にはコンクールで優勝する。そして12歳でプロデビューを果たし、世間は真理子さんを「天才少女」と賞賛した。しかし、10代の終わりを迎えたころ、ほころびが現われてくる。
「『天才少女』と拍手されるけど、当の本人は、『いかに天才を演じようか』と、もがいていたんです。1日14時間も練習すると肩がボロボロで体中の骨が痛くなる。毎晩、体中に湿布を貼って寝るんですが、その上から母が、私が寝つくまでマッサージしてくれました」
心身ともに限界を感じ20歳で楽器を置いた。一生弾かない決意だった。慶應の塾生としてキャンパスライフを楽しもうとしたが、「どこかでモーツァルトを耳にすると、ヴァイオリンを弾きたいと思う。でも、弾けなくて心臓がバクバクする。電車にも乗れなかった」という。そんな彼女を見かねて、母が結婚話を持ってきた。相手は4つ年上の医師。しかし、挙式の前日、相手のもう一つの顔を知る。
「式はしたけど、現実的生活も付き合いも一切なし。立ち上がれないほどの現場を私が見てしまってーー」。離婚を決意したものの、直後にNHKからキャスターの話が舞い込む。そこで「1年間は離婚は我慢を」と説得された。そして1年後に離婚。自宅に戻ると、そこには昔どおりに真理子さんと一緒に歩もうとする文子さんがいた。
ステージに復帰したのは23歳のとき。だが、苦しんだのはここからだった。長いブランクからかステージ中に思いどおりに弾けず、中止してしまうことさえあった。『天才も20歳過ぎればただの人』などとメディアは書き立てた。そして弾けなくなって7年目のことーー。
「それも突然でした。ゲストに呼ばれてチャイコフスキーのヴァイオリンコンチェルトを演奏しだして10分くらいたった瞬間に、すべての感覚がバーンと戻ってきました。悪夢から覚めたように」
会場にいた文子さんが、楽屋に飛び込んでくると、言葉なく互いに見つめ合った。何回もうなずく母の目から涙がこぼれた。その涙を見て、真理子さんは誓った。「もう二度と、音楽を裏切るまい」
30歳での再婚もまた、母が持ってきた話だった。今度は誠実な相手だったが、「この人の望むような穏やかな結婚生活を私は望んでいない。この先の人生は、ヴァイオリンだけに懸けていきたい」と悟った。
‘00年3月の兄妹3人での初共演となったコンサート『音楽会の絵』を見届けて、慶應の教授だった父が他界。翌年、文子さんは『千住家の教育白書』を出版して教育評論家、エッセイストとしての活動も始めた。そして’11年2月、腎臓がんが見つかる。すでにステージ4の末期がんだった。兄妹で話し合い、85歳という年齢も考慮した末に、告知に踏み切った。
「このころになると、けんかをしていた20代のころとは違い、母は私にとって愛おしい存在になっていましたね」と真理子さんは語る。何よりうれしかったのは、自分にしかできないことがあったこと。
「下の世話とお風呂です。これは娘の私の役目と思いました。夜中もゴソゴソ音がしたら、『お手洗いにいきたいんだな』と。それ以外も、立ち上がりたそうなときは、先に気づいて手を差し伸べたり。それは幼いころ、私が母にしてもらってきたことと同じだなって」
6月27日、最後に文子さんが口にしたのは、人生の大半を共に歩んだ娘の名だった。次兄の明さんは、母と娘との関係についてこう言った。
「真理子が母から受け継いだものは、母性愛です。自分の全存在をかけてヴァイオリンをさせてきた母に、してもらってきたことを返しているかのようでした。彼女たち2人には私たち男兄弟が立ち入れない結びつきがありました。母が生きている間は、真理子の人生の準備期間だったのではないかと思います。今からやっと人生の本番が始まると思うんです」
真理子さん自身、そのことを強く感じていた。
「生前、母が常に言っていました。『苦しんだり、悲しんだり、嘆いたり、そういう思いの人のために芸術はある』と。最後まで苦しみ続けた母を、自分のことのように感じたことで“芸術らしきもの”に踏み込めた気がします。私の演奏に対する母の評価は、いつも『もう少し言い方があるでしょう?』って思うくらい誰より辛辣でした(笑)。でも後から考えると常に正しい」
今また、母の存在を余計に身近に感じている。頭の右側辺りの空間を指しながら、真理子さんは言う。
「この辺にいる感じ。『じゃあ、一人でやってみなさい』と言われているのかな」