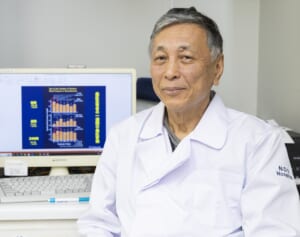“バツイチ”ならぬ“没イチ”という言葉をご存じだろうか。その意味は、配偶者に先立たれ、単身になった人のこと。そして、2年前、同じ境遇の没イチ同士が集まり、明るく笑顔で交流を深める「没イチの会」が結成された。現在はテレビでも特集が組まれるなど、話題を呼んでいる。
「65歳以上の没イチの数を見ると、女性は約720万人もいるんです。そんなに多いなら、“没イチ”同士をつなげたい。そう思って、定期的に飲み会を開催し、亡くなった配偶者のぶんも楽しむことができる会を作りました」
そう語るのは、発起人の第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部の小谷みどりさん(48)。彼女は、50歳以上のシニアを対象に再チャレンジをサポートする、立教セカンドステージ大学で“死生学”を教える講師だ。’15年6月、同大学で小谷さんの講座を受講する生徒やOB、OGの中で、配偶者を亡くした7人で発足したのが「没イチの会」。現在、小谷さんのほか、50〜70代のメンバーが11人(男性6人、女性5人)いる。
「私自身も、6年前に夫と死別しています。伴侶がいれば、どちらかが先に亡くなります。つまり、残された方は必ず“没イチ”になるわけです。ところが、死別した人に対してかわいそうという世間の目がずっと付きまとう。この偏見を変えていきたいとずっと思っていました」(小谷さん・以下同)
朝起きたら、心臓が止まって亡くなっていたという小谷さんの夫(享年42)。前日までまったくどこも悪くなかったのに、何が原因で心臓が止まったのかいまだにわからないという。
「6年がたちましたが、いまも夫が死んだとは思っていません。だから悲しくもないんです。周りの方々からは、“悲しいですね”“かわいそうですね”と言われますが、まったく悲しくないので違和感がある。ずっと出張に行っているという感じですね」
夫の死後、小谷さんが最初に違和感を覚えたのが、「離死別」という言葉だった。書類などで婚姻関係をチェックする欄に「既婚」「未婚」「離死別」の3つがある。離婚と死別はまったく違うのに、同じ扱いになっていることに疑問を感じたのだという。
「離婚と死別が同じようにされている割には、“バツイチ”は明るく言えるのに、“没イチ”はかわいそうな人のイメージ。たとえば、夫と死別した配偶者が、奇麗にお化粧をして明るい表情で出かけたとします。それを近所の人が見たら、“あの人、旦那さんが死んだばかりなのにね〜”となるんです。つまり死別の場合は、周りから悲しい姿を強要されるんですね。それも夫婦仲がよいという評判が高ければ高いほど強要される。世間にはまだそういう風潮が根強く残っているんです」
“没イチ”という言葉がこれからどんどん世間に浸透していくことで、多くの人が“バツイチ”のように明るく普通に使える社会になるーー。小谷さんは、そうなれば偏見がなくなると考えている。
「だから『没イチの会』は、悲しい人は入会できません。死別を思い出して泣いたりする人もダメ(笑)。年齢やどのような死別のされ方をしたかはそれぞれ違いますが、みんな死別を経験しているという共通意識がある。だから普通は聞けないようなことでも、明るくざっくばらんに話せる。自分1人だけではないという安心感がある。これが大事なのです」
世間の教訓としてよく使われる言葉に“その人の死を無駄にしない”というものがある。葬式に参加するたび、友人などを亡くすたび、そう思う人も多いだろう。しかし、小谷さんの解釈は、“その人が生きてきたことを無駄にしないために、その人と共に2倍楽しく生きる”ということーー。
「『没イチの会』は、亡くなった伴侶の愚痴なんかも明るく話せる環境なので、みんなで慰め合ったりもします。ただし、みんなが悲しんだりするための会ではありません。入会条件は、ポジティブであること。たしかに“没イチ”になると寂しいかもしれません。でも“悲しい”と“寂しい”は違います。できれば、地域ごとに『没イチの会』のようなコミュニティを作れるのが理想なのですが……。でも、そういうムーブメントを起こす火付け役になることはできると思っています。それが私の役割。亡くなった人のことを忘れずに明るく楽しく。そう思える世の中に近づいていければいいな、と」
配偶者との死別は大きな悲しみだ。ただ、考え方ひとつで、その後の人生の充実感は大きく変わってくるのかもしれない。