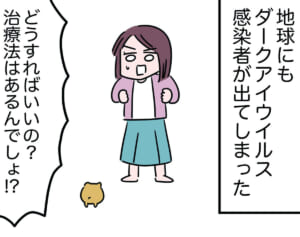第5回 30数年ぶりの母との生活開始
関口家には、とてつもない先例が、あった。父の弟、つまり私の叔父は、船乗りで船長にまでなった人だった。叔父は、南極観測船<宗谷>について行ったタンカー船に乗船していたのだ。晩婚だった叔父は、下船すると必ず、両親と母親(私にとっては祖母)、そして幼少の私が住む家に帰って来た。
チーズやら葡萄酒、黒パンを手土産に叔父は、私にまだ見ぬ外国の話しをたくさんしてくれた。私は、叔父の英語の発音を聞くのが、大好きだった。叔父は、若死にしたが、幼少期の私に多大な影響を与えた最初の人だった。そう、物心がついた頃から、私には、地平線の向こうに行くことは、しごく当然のことだったのだ。
長じてからは、叔父のように英語を話したかった私は、せっせと英会話教室に通い、外国人を受け入れる神奈川県の国際交流課でのアルバイトに精を出した。私のまなざしの範疇には、日本という国は、存在していなかったんだと思う。それは、ある意味で両親から、家族から遠ざかるということでもあった。
埼玉県にある大学に入学した際、母を説得して下宿生活を開始した。19歳になろうとする春のことだ。大学は、通学しようと思えば可能な距離だったが、私は、いずれ海外で生活をすることを考え、早く親元から飛び立ちたかったのだ。
それ以来、短期滞在はあっても、長期的に母と一緒に暮らすことは、一切なかった。
今から思うと、何て自分勝手な人間だったんだろうとつくづく思う。常に自分の前方のみに気を取られ、自分のやりたいことを見つけるまであがき続け、実に好きなように、生きたいように、自分の人生を生きてきたのだ。
成人式は、拒否し(晴れ着を作るお金があるなら、そのお金を留学資金に当てたいと言った!)大学の卒業式も待たずに1981年3月、日本を待ち切れないとばかりに飛び出したのだ。
後年、母は私が本当に大学を卒業したのかどうか、半信半疑だったと打ち明けた。また、母の姉達は、母が、私を成田まで見送った翌朝、一人で早朝の公園に行き、号泣したということを教えてくれた。
それでも私は、ひるまなかった。
何かに憑かれたように、天職と呼べるものを新天地のオーストラリアで探し続けたのである。母は、そんな私をいつも後ろから見守ってきてくれた存在だったんだなあ、と今さらながら思う。母の揺るぎない信頼と愛情がなかったら、今の私はない。これだけは、はっきりと言える。
遂に映画監督という天職に出合った時、私は歓喜に包まれたが、母には戸惑いと失望が隠せなかった。母にとっては、先行き全く保証がない職業のために、私は、長い人生の時間とお金を費やしてきたのか、という思いだったんだと思う。一体私は、どこまで親不孝なのか。
それなのに私は、諦めなかった。そんな母心を知りつつ、でもねじ伏せながら、自分の信じた道を突き進んで来たのである。
しかし、遂に私が、母のことを振り返る時が、来た。
ドキュメンタリー映像作家 関口祐加 最新作 『此岸 彼岸』一覧