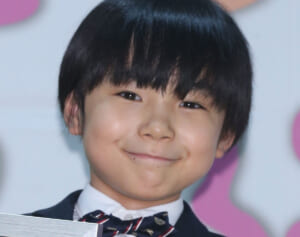STAP細胞をめぐる一連の騒動で窮地に立たされている理研だが、じつは日本最高峰の研究機関といわれてきた。前身の財団法人理化学研究所が誕生したのが1917年、創設したのは渋沢栄一だ。第一次世界大戦後の不況で苦境に立たされた理研を立て直したのが、第3代所長の大河内正敏である。
「大河内は所長就任当時42歳で、日本で最初の造兵学者でした。造兵学というのは武器・弾薬の研究をする学問で、理研の任務も兵器製造だったわけです。しかし、兵器を作るには重化学工業を発展させなければならず、そのために自由に研究できる研究機関を育てる決意をするのです」(大河内の評伝を書いた専修大学の齋藤憲教授)
大河内は若手の人材登用を積極的に進め、組織の拡大を図った。当然、人件費もかかるし研究資金も必要になる。そこで、大河内が考えたのが研究成果の商品化だった。
「理研は弁当箱に使われたアルマイト、コピーの元祖ともいえる陽画感光紙、ビタミンAなどさまざまなものを発明・発見しています。これらの発明をもとに、会社を山のように作った」(同)
理研の関連企業は最盛期には63社を数えた。陽画感光紙の製造販売会社は現在のリコーに、人造酒の会社は協和発酵になった。「ふえるわかめちゃん」の理研ビタミンも同じグループだ。さらに、世界に冠たるコンドームメーカー「オカモト」も、理研ゴムと岡本ゴムが合併してできた企業。
こうして、潤沢な資金を誇った理研は、湯川秀樹や朝永振一郎ら超一流の研究者を育て、多くのノーベル賞を生んだ。じつは、そうした研究のなかには、陸軍から要請されておこなった「原爆の開発」なども含まれている。
巨大になった理研は、戦後財閥解体で解散。(株)科学研究所となった。その資金難を救ったのが田中角栄だった。
「戦前、角栄が小さな建築会社を創業したとき、大河内が見かねて理研の工場を建てさせてあげたんです。角栄はそのときの恩を忘れず、理研が危機に瀕すると特殊法人化して、政府の予算を注ぎ込んだ。それで、理研は世界有数の研究機関に育っていくことができたんです」(同)
小保方晴子さんが所属した発生・再生科学総合研究センター(CDB)は、政府のミレニアムプロジェクトの一環として’00年に発足し、日本最高水準の研究環境が整えられている。幹細胞に詳しいジャーナリストの緑慎也氏が、理研の恵まれた環境についてこう語る。
「理研は3千人の科学者を抱えていますが、年間予算は850億円もある。小保方さんにも5
年間で1億円が割り当てられています。予算をどう使うかの権限も与えられていますが、1年で研究費1千万円、人件費1千万円というところでしょう」
かつて朝永振一郎は、理研を「科学者の自由な楽園」と呼んだ。今回の信用破壊は尋常ではないが、豊富な予算で好きな研究に没頭し、新たなノーベル賞学者が生まれることを期待したい。
(週刊『FLASH』4月8日号)