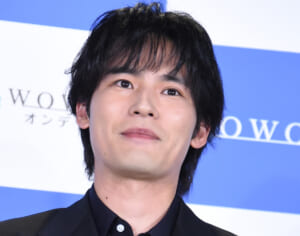「6月は、インポータントな月というイメージが子どものころからありまして。親父の命日が6月23日、敬愛するマイケル・ジャクソンは25日、そして僕のデビュー日が21日。もう20年以上、毎年6月にはシングルを出していて、気合の入る月なんです。新曲の『フェミニスト』は、女性の持つ母性と美しさを歌っています。僕ら男は、女性によってこの世に生を受けて、人生が始まる。愛する人がいて、支え、支えられてという愛の根源がテーマです」
そう語るのは、6月21日、11年ぶりにメジャーレーベルから新曲『フェミニスト』をリリースした田原俊彦(56)。デビュー直後から、近藤真彦、野村義男の3人で「たのきんトリオ」と呼ばれ、超人気アイドルのオーラで輝いたトシちゃん。還暦を4年後に迎えるいまも、毎年、夏の全国ライブツアーと冬のディナーショーを欠かさず開催。迫力たっぷりのダンサブルなステージで、多くのファンを魅了し続けている。
「独立」から23年、田原がジャニーズ事務所に入るまでのことを振り返る。
「生まれたのは、横須賀市馬堀町。横須賀って、海岸沿いの町で、しゃれた雰囲気があって。ところが、親父(冨士雄さん・享年37)が亡くなって、いきなり山梨県甲府のね、ほんと、やばいくらい田舎へ引っ越したから。カルチャーショックでしたよ。カエルはいるわ、毛虫はいるわ、カブトムシは捕れるわ(笑)。僕は早生まれ(’61年2月28日)なんで、6歳4カ月で親父が亡くなったんです。急に白い布かぶって、寝ていて。死んだって、わからなかったんじゃないかな。泣いたのか、泣かなかったのか……。父は小学校教師でね。また宿直がある時代で、親父と一緒に学校に泊まった思い出があります。膝の間に座らされて、上を向いたら、髭がジョリジョリと痛かったな」
田原は母と姉2人、妹1人という女系家族。父の死後、母・千代子さん(85)は、姉2人をしばらく父方の実家に預け、田原と妹を連れて、甲府の実家に戻っている。喫茶店や化粧品会社で働いて、女手一つで子どもたちを育てた。母の苦労を見て育った田原は、負けず嫌いのやんちゃ坊主。野球が大好きな少年だった。
「給食費を払うのが精いっぱいだったり、クラスで物がなくなると、僕が疑われたり、そういう母子家庭への偏見は多少、あったと思いますよ。生活するのがいっぱいいっぱいだったこともあるでしょうけど、それへの反骨精神もあって、たとえば父親参観のときに『なんで、親父がいないんだろう』って思うじゃないですか。負けん気も強かったし、かけっこでも勉強でも負けるのはいやだった。絶対、自分は、人としてでかくなって稼ぐぞという気持ちは、たぶん誰よりも強かったんじゃないかな」
中学時代は、やんちゃ仲間と野球チームを掛け持ちしながら、小遣いくらいは自分で稼ごうと、新聞配達を始めている。甲府工業高校土木科に進学すると、「3年間でスターになる」と、心に決め、ジャニーズ事務所に履歴書を送った。返事はなかったが、ならば自分で行くしかないと、高校1年の夏休みに、上京。ジャニーズ事務所の門をたたき、以後、研修生としてレッスンに通った。
「ジャニーズに行くとき、おふくろからは反対も賛成もなかった。一度決めたら、テコでも動かない僕の頑固なところは誰より知っていましたから。15歳から、往復6時間かけて、毎週末、レッスンに通った3年間は、俺自身、よくできたなぁと思うし、コツコツやる姿をおふくろも見ていた。帰りは、いつも特急あずさでした。ジャニー喜多川さんがチケットを買ってくれて。あのジャニーさんが、ホームまで見送ってくれたんです。30人くらいの研修生が毎週、当時、テレ朝の旧社屋の真ん前にあった第一リハーサル室でレッスンをして。夜8時のあずさで帰るんですが、新宿から帰る子どもらを引き連れて、ジャニーさんが、列車の時間までインベーダーゲームで遊ばせてくれてね。あずさに乗ると、みんながバイバイと見送ってくれた。帰りのあずさの2時間半は、さすがにもんもんとしてね。光が見えないなか、どうなるんだろうという思いもあったけど。俺、絶対、スターになるというのはあったよね。あのジャニー喜多川が、あんなに入れ込んでくれたわけだし、それに応えなきゃと思ったし。ハングリー的なガッツは尋常じゃなかったでしょうね」