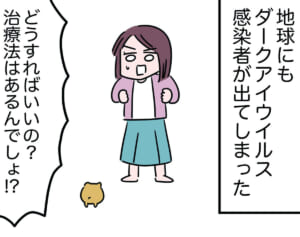<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>
どれほどの時が経っただろう。常人ならば吐き気を催すに違いない光景に、まるで磁石に引き寄せられる砂鉄ように魅入っている明美は気付いてないが、健作のタバコがフィルターを残して燃え落ちている。それに気付いた健作が、握り締めた明美の手を解こうとしたその瞬間、淵を覗いていた三体の陽炎が、揃ってこちらへ向きを変えた。そしてそのまま、現れたときと同じくユラユラと揺れながら、ゆっくりと二人の車のすぐ横を来た方向へと通り過ぎて行く…。
と、その瞬間。通り過ぎようとする三体の内の一体が、グゥーとその身を折り曲げるようにしてフロントガラスを覗き込み不気味に嗤って見せたのだ。
車中を覗き込むその顔を、明美は生涯忘れることは出来ないだろう。なぜなら、不気味に嗤うその顔は、それまで何も無かった顔の辺りに、見紛うはずも無い健作の顔が貼り付いていた。ただ、明美の知る健作と違うのは、およそ健作が絶対にするはずの無い凶悪な相をしていたことだ。
耳まで裂けた真っ赤な口を歪めて嗤ったその目は明らかに明美を見ていた。明美は正しく焦点が合ったことを確信し、心臓がひとつ鼓動を止めたのを感じた。
「どうした? 明美、大丈夫か?」
我に返った健作は、そのまま胸の辺りを押さえて俯いてしまった明美を抱きかかえるようにして声をかけた。ついさっきまで強く握っていた手から体温が無くなっている。頬にはびっしりと冷たい汗を吹き出させ、呼吸も荒く不規則になっている。健作は、もう一方の掌で明美の背中をゆっくりと撫ぜ摩った。
「…ありがとう。…もう平気。大丈夫。…大丈夫だから」
大丈夫とは思えなかったが、健作には、それでも少し呼吸が落ち着いてきた明美の、冷たくなった手を揉み解して暖めるくらいのことしか出来なかった。
喧騒がもたらす安らぎ
しばらくして車を出すと、そのまま家には戻らずネオンサインが瞬く賑わいに向かって車を走らせた。どこへ向かうとも言わずハンドルを握る健作の隣で、ウィンドー越しに流れるヘッドライトを目で追いながら、明美はこれまでに起きた様々な出来事の順列組み換えに忙しく頭を使っていた。そうでもしていないと、フロントガラス越しに見た醜悪な顔を思い出して声を上げそうになる。
そんな明美の頬に、行き過ぎるヘッドライトがふた筋の涙を照らしていた。

あの瞬間、アレは明美の心を覗いた。あの醜く引き攣れた嗤いは、決して覗かせてはいけないモノに覗かせてしまった明美の慄きと後悔を、簒奪者特有の鋭い嗅覚で嗅ぎ取った優越感の顕れに他ない。
明美にとって、これほどの屈辱はなかった。それはまるで、名も無き無頼に純潔を踏み躙られたような…。曾祖母から祖母を経て、遥かに永い時を守り続けた血脈を汚されたような悔しさに声もなく涙がこぼれた。
市街を右に見ながら環状線を北へ。目指すは、お昼はランチを楽しむママ友で賑わうスイーツが自慢のファミリーレストランだ。
「どうだ…。少しは落ち着いたか? ここなら人が居るし、ゆっくりできるから。ご飯でも食べてさ…それから帰ろうぜ」
あのまま家に戻っていたら、二人して深刻になってしまっただろう。いつもは、こんな風に見知らぬ人に囲まれるなどもっての外だが、今夜は違った。健作がオーダーした暖かいスープが、冷たくなった明美の身体を内側からほぐしてくれるようで心地良い。張り切ってハンバーグセットを頼んだ健作が、300グラムの和風ハンバーグを見る間に平らげてしまう姿が平和だった。
「お義母さんには申し訳ないけど、たまにこういうボリュームが欲しくなるんだよな」
今年で38歳になる健作は食欲も旺盛で、年甲斐も無い野菜嫌いを「肉食」を標榜することで誤魔化している。それにしても、こう目の前で貪られるとなんだか深刻な自分が滑稽に思えて、明美もつられて笑ってしまった。
「ほらな。やっぱり食卓は朗らかに囲まないと!」
健作の言う通りだ。たとえ物思いに沈んでいても、食卓を囲むときは笑顔でいたい。ただそれだけで、スプーン一杯のスープが温かく、ありがたいものに感じられる。少し落ち着いた明美は、スープボウルから顔を上げると改めて店内を見回した。

ちょうど今頃は、普通の家庭ならば夕飯を終えて団欒のひと時を迎えているだろう。子どもたちはTVに噛り付き、そんな姿に大人は目を細めているに違いない。ランチ時はあれほど居た主婦の姿も無い。それでも店内は、カップルと若者たちのグループで三割がたテーブルが埋まっていた。
「なぁ、どうする? 少し落ち着いたら話してみないか? それとも、家に帰ってからにするか?」
まだ少し動揺していたが健作の要求は当然だ。本音を言えば、まだ何も話したくなかったが、と言って家に戻って二人きりで話し込むのもつらい。静まり返った部屋で、二人膝つき合わせて話すくらいなら、少しざわついてる方が話しやすいかもしれない。明美は、ロングピースに火を点けひと息深く吸い込むと、思い切りよく紫煙を吐き出し全てを話す心の準備をした。
子どもたちの霊が邪悪なモノではないという認識を持つ健作に、それでも話しておかなければいけないことは二つ。
一つは、この話を聞いている健作自身が狙われているということ。そしてもう一つは、父の死との関わりというわだかまりで始めたことが、今やそんなレベルでは無くなり、噂の怪奇現象そのものを解決せざるを得ないということだ。
健作にしてみれば、妻と娘の身に迫る危険の回避こそが協力する最大の理由だ。幸いにしてそれは杞憂に終わりそうだが、替わりに健作自身に危険が迫っているという状況を正しく認識させねばならない。そしてその危険は、一連の怪奇現象を究明することによって解決するはずだ。
しかし健作に、そんな危険な状況を正しく認識してもらうには、思い出したくもない今夜の一部始終を話すしかない。
逸る心と案じる気持ちが綯い交ぜになった複雑な面持ちで見詰める健作を前に、明美はひとつひとつ思い出しては吐き捨てるように、それでも要らぬ解釈が入らないように慎重に、ゆっくりと噛んで含めるように話し始めた。およそ30分ほどの話だが、聞かされている健作がうろたえるほどに、見る間に明美の疲れは増していった。
それでもやっと口に出来た開放感で、明美の気持ちは、身体の疲れとは裏腹にそれまでとは比べようもないほどに軽くなっていた。
明美が話をする間、じっと耳を傾けてくれていた健作と、それからしばらく、考えられる限りの今後の傾向と対策(?)を協議し一つ一つ確認していった。
そうして、健作の出した結論は…。
「凄い夜だったな。お疲れさま。なんて言えばいいかわからないけれど…。とにかく今夜、俺たちは、この一年間明美の地元を騒がせている元凶と遭遇したんだよな。それによって、明美が常々思っていた、子ども霊ではない別の…もっと邪悪な存在が確認できたわけだ。そしてもうひとつ、俺たちはとっても深刻な事態に陥ってるってことだよな」
いつもと変わらない口調ではあるが、まだ三口も吸ってないタバコを忙しなく揉み消す仕草に隠し切れない緊張感がうかがえる。甘く見ていたわけではないが、結局のところ明美に頼るしかない健作にとって、今日の一件は亜里沙と明美の無事が確かめられれば、後はロマンチックでスリリングな冒険譚ぐらいに思っていたところがある。それが一転、抜き差しなら無い状況に展開してしまい、少し混乱していた。
ほくそ笑む簒奪者
「さてと、そろそろ帰ろうか」
それでも、いち早く気持ちの切り替えが出来た健作がレシートを手に席を立った。そのままレジに向かおうとする健作を、追うような形になったことが明美には少し不満だったが、そんな風にいつもの負けん気が出てきたことに少しホッとした。そして改めて店内を見渡し、自分たちが随分と奥まった席に居たことに軽く驚いた。
“そんなに深刻な顔してたかしら…”
していたのだろう…。だからこんなに、出入り口から離れたテーブルに案内されたに違いない。そんな二人の悩みなどとは全く関係の無い若者たちが楽しそうに笑っている。それは、当たり前の生活を感じさせてくれる温かい光景だった。
などと、四人連れの男女が談笑するテーブルの横を通り過ぎようとした瞬間。一番手前に座り後頭部を見せていた男性の顔が、グルッと真後ろに向き直って
『随分と面白い家に住んでおる』
と一言。まるで沼の底から聞こえてくるようなくぐもった声をかけてきた。
「あっ」
明美の膝から力が抜けた。そしてそのまま、その場にへたり込んでしまった。

「おい、どうしたんだ。明美、大丈夫か?」
後ろからついてきていた明美の一言に振り返った健作が、座り込んでしまった明美の脇に手を差し入れ立たせようとしている。
「どうしたんだ、明美? 大丈夫か? あっ、すみません。ちょっと疲れてるみたいで」
見ず知らずとはいえ、すぐそばを通りがかった女性が倒れそうになった気配に驚き、眩暈でもしたのかと4人の男女が怪訝な顔で覗き込んでくる。少しふらついたが、健作に抱えられるように出口へと、まだ少し先のレジへと続くドリンクバーの縁につかまって歩く…。ドリンクバーでは、親子で来ている小学生くらいの女の子が一人、悪戯でもするように幾つものドリンクを飲み比べている。
『随分とおもしろいモノを持っておる』
まただ。今度は少女の顔が同じく真後ろに回り、同じようにくぐもった男の声で話しかけてきた。
健作に支えられていなければ、その場にうずくまってしまったに違いない。それでも、引き摺られるようにレジにたどり着いた。向こうの方で、さっき倒れそうになった明美に驚いた四人組が立ち上がってこちらの様子を窺っている。二度までも倒れそうになった女のことが気になって仕方ないのだろう。手助けでもするつもりだろうか、グループの一人はこちらへ駆けてこようとしている。
レジの店員は、そんな明美を心配するというよりは唖然として見ていた。まるで面倒な客でも見るような目付きだ。普段は温厚な健作だが、他人からそんな扱いを受けると途端に闘争心が頭をもたげる。面倒なんぞ起こしてないぞとばかりに、それでもどこか挑発するようにレジ横にレシートを乱暴に置き、店員の顔をまじまじと見返している。
『おまえも、随分とおもしろい娘を持っておる』
三度目の声の主はレジの店員だった。まだ20代前半と思われる店員は、およそ人間とは思えない醜悪な…それも健作の顔に変貌した瞬間に、歳老いた男の皺がれ声で健作に向かって声をかけてきた。
「おい。おまえ、今なんて言った!」
ほんの一瞬、気が抜けたように立ち竦んでいた健作が、気を取り直すと、今度は掴みかからん勢いで店員に詰め寄っていた。思いもよらず詰め寄られた店員は、そんな健作にただ驚いている。
「…いえ、なにも。…あ、2,200円です」
「…健作、2200円だって。…ねぇ」
健作の隣で同じように声を聞いた明美は、これがアレの成せる技と瞬時に理解していた。早く出た方がいい。このまま放っておけば、健作は益々エスカレートするし、店員も騒ぎ出すかも知れない。
明美は、一人では立って居られなかった女とは思えない確かな手つきで2200円を出してレジ横に置くと、それでも何か言いたげな健作の手を引いて店を出た。
窓ガラスの跡
「…明美、悪いな。俺、気が動転したみたいだ」
車に乗り込み少し落ち着いた健作が、最初に口にしたのがこれだった。おそらくは、生まれて初めて、これまで女房を通して知ったつもりでいた世界を自ら体験してしまったのだ。動揺するのも当然だ。それも、やっと身の安全を確かめたはずの娘に向けて、この世のモノでは無い男(?)から不気味な言葉をかけられたのだ。動転しない方がおかしい。

「ううん、私こそ。こんなときこそ、私がしっかりしてなきゃいけないのに。健作にばかり甘えちゃってたね…」
「そんなことはない。明美が、どれほど不気味なモノたちと戦っていたのかがよくわかったよ。…疲れたな。もう帰ろ」
と、エンジンを掛け駐車スペースからバックで車を出そうと、二人してリアウィンドウを振り返った瞬間、二人は凍り付いた。
小さいながらも4人乗りの狭いリアシートの向こう。後部座席のウィンドウガラスに、くっきりと4つの手形が付いている。左右二本の腕を思わせる掌はそれぞれに一定の間隔を空け、そのちょうど人間の顔が入る程度の間隔は、そこから何者かが車内を覗き見ていたことを連想させる。考えられるのは、『蛇の淵』の駐車場で健作の顔を持つ陽炎にフロントガラス越しに睨みつけられたときだ。あのとき、二人は目の前の陽炎に必死だったが、行き過ぎたかと思った残りの二体の陽炎も、実は二人を背後から観察していたのだ。
不気味な四つの手形に驚き戦慄を覚えはしたが、そのまま動揺し続けるには状況が切迫し過ぎている。二人は何も言わずに、固く唇を結んだまま急ぎ家路についた。
憑依
「突如として気分が悪くなる」「急に体の調子がおかしくなった」「不意に気力が失せてしまった」などなど、日常的に起こりがちなこれら原因不明の心身の不調。鋭敏な人は自覚することもあると思うが、そんな不調の影には少なからず、「憑依」があるとされる。現世を生きる肉体を持った者が、目に見えない霊的存在の力の影響下に置かれてしまう状態=憑依。日ごろから〝憑かれた相談者〟と相対することの多い真印さんによれば「とくに霊感が強くなくてもできるごく簡単な憑依への対処法はいくつもある」という。「朝日を浴びる、適度な運動をする、生活習慣を変える。粗塩を振りかける、塩を入れた湯船に浸かる、マントラ(真言)を唱える、などなど、憑いてしまったものを外し、心身を清める術はいくつもあります。どの方法をとるにせよ、身内が清浄になるイメージを強く持つことが重要です」(真印さん)。さらに、真印さんは笑みを浮かべながら、とっておきの憑依予防策も伝授してくれた。「とにかく朗らかに、心健やかに過ごすこと。笑い声のある処には、禍々しいモノは寄ってきません」。