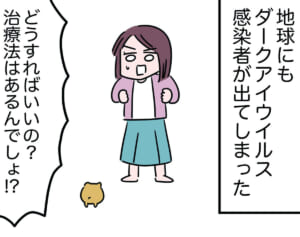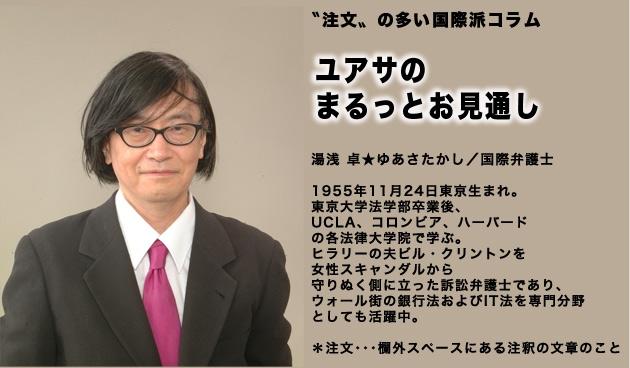
連載第28回 5月のアメリカは熱い!なぜなら、卒業式とは開幕式だから。
アメリカでは、卒業式のピークは5月。しかし、卒業式というよりも「開幕式」と呼ぶことのほうが一般的で、このあたりがいかにもアメリカ的です。
この「開幕」(英語ではコメンスメント)は、メジャーリーグの「シーズン開幕」と同じ表現・意味であり、緊張と興奮を感じさせる言葉なのです。
日本では卒業式と聞くと、謝恩会などを連想し、〝ほっと一息〟というゆったり感が付きまといがちです。が、しかしアメリカでは、卒業に、たとえて言えば、水泳のブレス(息つぎ)のようなニュアンスはまったく含まれていないのです。
「人生とは、熱い感動の波の連続!」というスーパーポジティブな発想がアメリカ社会には根付いており、その人生という難航路への旅立ちの日を「開幕式」と呼ぶのであると、国際弁護士ユアサは保証します。
ユアサも覚えています。
といっても、東大法学部での3月の卒業式は、授業と同じ広い教室の中だったので、「へえ~、教室はやっぱり大きかったんだ」以外の記憶は残っていません。
それに対して、UCLAロースクールの5月の卒業式は、ロサンゼルス五輪の体操競技の予定会場で行われたため、自分たちがアスリートになって前乗りしたかのごとき興奮を覚え、観客席の上方を思わず見上げた思い出が、今もまざまざと記憶に残っています。
以前、この連載で、長年の親友のフォージャー弁護士からユアサが若きキャロライン・ケネディ現アメリカ駐日大使を紹介され、その美しさに圧倒されたことを記しました。
実は、キャロラインはコロンビア法科大学院時代に学生結婚をしており、実にアメリカ的な感動の卒業式(=開幕式)を迎えました。
キャロラインはぷっくりおなかで卒業式に臨み、およそ1カ月後に長女が誕生します。やがて、次女そして長男にも恵まれ、子供たちに愛を惜しみなく注ぎながら、彼女は同時に腕利きの弁護士&腕利きの編集者としての道を歩みます。
キャロラインの開幕式には、わが子との〝親子の絆〟もあったのです。
ところで、今、毎日が開幕という、いかにもアメリカ的な存在感を持つ人物がニューヨーカーの注目の的です。我らがマー君、田中将大投手です。
マー君は、名門ニューヨーク・ヤンキースの先発投手のひとりとして強打者をきりきり舞いさせても謙虚さを忘れず、ファン全員の思いに常にほほ笑みをもってこたえ、他球団のファンからも一目置かれる存在となっています。
まい夫人もまた、マー君の食事面など健康・体調管理に細やかな気配りをしていることが、全米のマスコミでも数多く報道されています。
マー君の場合、何を「毎日開幕」しているかというと、やはり日本とは違うメジャーリーグ特有の中4日の登板ローテーションです。
日本では先発投手の登板間隔は、5日や、しばしば6日も空けていますが、アメリカでは投球数に上限を設けつつ、中4日登板が確立しています。このメジャーリーグの投手が避けることができない中4日ですが、マー君は見事に適応しています。
これは、マー君の挑戦者としての緊張感の持続に加えて、裏方に徹するまい夫人との名コンビの成果と言えましょう。
いかなる天才アスリートも、人間ですから疲労します。名コーチも名トレーナーも解消しきれないのは、人間的な内面の疲労の蓄積です。それを鮮やかに払い去っているのが、ふたりの「絆」と言えましょう。
キャロラインやマー君のエピソードをみると、〝人生とは熱い感動の連続〟と見るポジティブなアメリカ的発想にも、「絆」という特別な人間関係でないと越えられない壁があることを教えてくれているようにみえます。
日本でもよく言われますが、そもそも、一般論としてアメリカの学校は入るより出るほうが大変!なのです。
したがって、アメリカでは勉強の重圧が加速度的に増大し、〝卒業式=開幕式〟の緊張感がすさまじいとされる、というのは前述のとおりです。
でも、実はそれだけではない、のです。
ユアサのロースクール時代の親しい友人に、秀才の黒人学生がいました。彼は卒業を前に、恐らくはユアサにだけホンネを語ってくれました。
「タカシ、僕は、本当は卒業したくないんだ・・・」
こう言われて、ユアサは初めて「開業・開幕」だけではない、「卒業」という言葉の持つ重い意味を、アメリカ社会の中で思い知らされました。
この友人の黒人学生は、学内法律雑誌の「脚注担当の編集者」を任され、学内ベスト3に入るほどの秀才でした。
しかし、彼が学生時代に享受している学問や表現活動の自由が、キャンパスの外でどこまで味わえるのかは、極めて大きな疑問符が付く、社会の現実がありました。
アメリカ史上初の黒人大統領にオバマが就任する25年前の話です。
当時、アメリカのメディアで、人種的に一番不公正な扱いを受けているのは黒人であり、特に黒人男性であるという文章が、公然と記され、語られていたのを、ユアサははっきりと記憶しています。四半世紀の後に、黒人大統領が誕生するなど、大げさでなく、誰一人予測し得ない社会状況があったのです。
彼はユアサにはへこんだ内面を吐露しましたが、卒業の日までには、気持ちを整理したようで、弱みを誰にもみじんも見せない態度をとっていたのはさすがでした。
それでも、卒業直前にこんな出来事が彼との間でありました。
「タカシ!車では入れないのだが、どうしても本を借りる必要があって、少し遠くだけど一緒に歩いて借りに行ってくれないか?」
と、彼が頼んできたので、「オーケー!」とユアサは即答しました。
ただ、現場に向かうと、どうもそこかしこで危険な感じの人物が目に入ってきます。
ユアサは黒人学生が危なそうな方向に行くのを押しとどめ、回り道しながらも無事に本を借りることができました。
「ところで、どうして僕を連れて行ったんだい?」
ユアサがたずねると、彼は静かにアメリカン・ジョークで答えました。
「二人で行けば、タカシが弾よけになってくれるかもしれない・・・」
ユアサも負けずに返します。
「一つ忘れている。ユアサのバック・ステップは弾よりも速い(!?)」
その緊張の日々から、7年の歳月が流れたある日。
このアフリカ系アメリカ人の友人が、西海岸でラジオ局のオーナー兼ディスクジョッキーとなったとのニュースを、彼から電話で知らされました。
ユアサは飛び上がって心底喜びました。
友人は、彼なりの表現の自由を、自力で、このアメリカ社会の中で、つかんだのでした。
同時にユアサは、人種差別が根強く存在する現実社会での、その後の彼のタイトロープのように張りつめた長年の緊張の連続に思いをはせました。
そして、何よりロースクール時代の同期としての「絆」を、ユアサは強く感じました。
アメリカでは、表現形式としてはユーモアのオブラートに包むのですが、まず何より、相手が危機の時に命がけで守る、固い「絆」の緊迫感が人間関係の中心に存在している、と国際弁護士ユアサは断言します。
アメリカの「卒業式=開幕式」にまつわる緊張が半端なく強いのは、そこに「絆」があるからです。
そして、〝毎日が開幕である〟というアメリカ社会の発想は、〝絆とは心の青空にあって、決して沈まない太陽である〟という情熱によって支えられています。
だからこそ、「絆」もアメリカの「開幕式」も熱いのです。 (了)