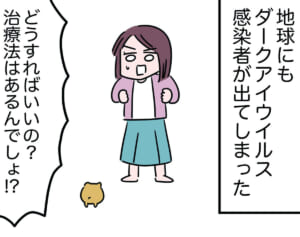――まず、2つ大きな質問を。なぜカメラマンかということと、なぜボクシングなのかということだと思うんです。
林 「なぜ」ですか。23歳で事故をしたんですけど。結局、中途半端なままで、やろうと思ったら何も形になってなかったんです。まあ、事故したときに思ったことが、これは本当なんですけれど、なんか中途半端にやってたからなんでしょうけど、「怒られた」的な感覚っていうのが、すごくあったんですよね。
――自分が事故にあったことが。
林 中途半端に、形だけ、カメラマンのアシスタント作業だけをひたすら覚えて、ひょっとして俺、カメラが何かわかってなかったわけですよね。個性的な人が多い業界じゃないですか。俺なんかやれるのかな、みたいな感じで、形だけの仕事をやってたんですけど。事故して、「中途半端だったからこんな目に遭っちゃったのかな」みたいな、「罰当たったのかな」的なところもあったんです。
結局そうなって、痛い目に遭って、からだ中すごい痛かったんですけど。そのとき初めて、「これは、やらなきゃダメなんだ」みたいな、自分の中で……。片手でこういうふうにですけど、なったときおかしくなったのがわかってましたから。ある種リベンジ的な思いもあったんだと思うんですね、そのときはね。
だから、周りからの反対もあったし。医者からもいわれましたよ。普通の障害者として、からだすごい痛いんだしって言って、一般企業でね、障害者の雇用枠があるし、そういうので働くものでしょう、みたいに。そういうものに、自分の中で、物申したかったっていうか、そうじゃないんだよっていうところに、こだわりがあったんだと思うんですよ。
――それを実際に行動に起こすのは大変なことじゃないですか。ましてやカメラマンって、やっぱり特殊な仕事だし。長くアシスタントしていたとなると、自分1人だけでやれるものではないっていうことも、わかっていると思うんです。そこらへんは、実際にやってみてどうですか?
林 カメラマンですか?
――はい。
林 カメラマン……、もともと、僕向いてないっちゃ、向いてな いです。こういうフリーの、そういう世界とかって。そういうのを感じてらっしゃるかもしれないですけど。まったく向いてないです、自分でそうやって、1人でガーっと営業したりなんやかんやって、向いてないんでしょうけど。
いです。こういうフリーの、そういう世界とかって。そういうのを感じてらっしゃるかもしれないですけど。まったく向いてないです、自分でそうやって、1人でガーっと営業したりなんやかんやって、向いてないんでしょうけど。
だから、最初は写真館(協同組合
日本写真館組合)に入ったんですよ、僕ね。アシスタントとしての作業はできなかったので、嘘ついて、ちょっとぐらい手が悪いですみたいなことを言って入って。そういうところから、撮ることを勉強していったんですよね。やってみて、そうですね……。仕事として成立するのはすごい難しい、僕の場合はすごく難しかったと思うんですよ。ていうのは、商業的に見ないで、お金を稼ごうとか、そこで儲けてやろうっていう発想はあまりなかったんですよ、実のこと言って。ただ、撮るっていうことを究めたかったというか、自分の中で。
ここで、吉田茂樹カメラマンが加わった。吉田カメラマンは、高校生の時にラグビーの全日本に招集されるほどの選手だったが、スクラムの練習中首の骨を骨折。一時は全身マヒの状態になるが不屈のリハビリで松葉杖を使い歩けるまでに復活。オレゴン大学に海外留学。帰国後はカメラマンとなった。
――お疲れ。吉田君です。
吉田 どうもです。こんにちはです。
林 こんちわっす。お願いします。
――隻腕のカメラマン、林君です。
林 林と申します、よろしくお願いいたします。
吉田 松葉杖のカメラマン吉田です。
――2人とも、なぜカメラマンなのかなっていうところは、すごくあるんですね。なぜ、カメラマンを選んだのかって。いろんなことがあったと思うんだけど。
吉田 実はもともと、ボクサーだったの?
 林 いえ、全然違いますよ。ボクシングは好きだったんですけど。
林 いえ、全然違いますよ。ボクシングは好きだったんですけど。
吉田 ケガはどうして?
林 ケガは交通事故なんですけど。引き抜き損傷っていう、背骨がいっぱいあるじゃないですか、そこから神経がバーっと出てるんですけど、そこから根本がバーンと抜けちゃって。上腕神経層って、いろんな神経が、ここから変換してこっちに行くじゃないですか。その回路がぐっちゃん、ぐっちゃんになっちゃったっていう感じだったんですよね。だから動かないのと、握って曲げることはできても、ほかは全部ダメになってしまって。結局、再建するために、呼吸する神経って肋間神経を使いましたけど、胸を膨らます神経っていっぱいあるらしいんですけど、僕はわかんないですけど。
吉田 僕も横隔膜が止まっちゃったんで。
林 それは怖いですね。
吉田 クビの4、5だったって……。
林 ああ、そこが一番多いんですかね。Cの4とか5っていうやつですね。
吉田 3、4だと、たぶん呼吸ができなくなっちゃうんですね。ケガをする前から、もうカメラマンだったんですか?
林 僕、アシスタントだったんですよ。スタジオマンっていて。だいたいそこからステップアップして、王道で行くんだったら師匠とか何かについて、それで独立してカメラマンっていうのが普通、あの頃はそうだったんですけど。僕はスタジオマンやってただけだったんで、技術を学んでた程度だったんですよね、その頃は。
吉田 どういう出会いで?
――吉永マサユキさんっていうカメラマンの兄貴を通しての。一番最初、何だったんだっけ?
林 毎月、毎月、吉永さんが会をやってたじゃないですか。
――吉永会で会ったんだっけ?
林 ええ、そうです、吉永会で。
――もう、悪い会ですわ、考えてみたらもう……(笑)。ある意味、業界のゴロみたいな連中ばっかりだよ。
林 僕らみたいな、若い人も呼んでもらって。なんか少しでも、つながり持ってっていうような、そんなふうに吉永さんが思って、企画してたと思うんですけどね。だいたい好きな若い人たちばっかりですから、毎月、毎月。
――また少しあれだね、復活したいけどね、あれもね。
林 そうですね。
――なぜカメラだったんだろう。カメラマンでなければならない必然性っていうのは?
林 僕ですか? 伯父がカメラマンだったっていうのがあるんですけど、僕のおじが。しかも、そういうドキュメンタリーの、当時の水俣病とかカネミ油症(1968年に北九州一帯で発生した食品公害事件)っていうんで、それを撮って訴えた本とか作ったんですけど。そういうのがどこかにあったんでしょうね。僕、何をやっていいかわかんなかったとき。
 何となく、じゃあやってみるか、みたいなノリで。伯父には何も相談もしなかったんですけど。何でって言って、何でしょうね。でも、いま、いろいろ……、結局、写真館で復活して。自分の作品っていうか、何かが欲しくて。結局、僕、臆病者ですから、何か人から言われなかったらできなかったんでしょうけど。著名な画家の方と会うことがあって、「君の作品って何だ?」って言われたときに、何もなかったんですよね。結局、写真館に戻ってやった程度のことだったから。そこで、「ああ、しまった」と思って、何かやらなきゃいけない、撮らなきゃいけないと思ったんです。
何となく、じゃあやってみるか、みたいなノリで。伯父には何も相談もしなかったんですけど。何でって言って、何でしょうね。でも、いま、いろいろ……、結局、写真館で復活して。自分の作品っていうか、何かが欲しくて。結局、僕、臆病者ですから、何か人から言われなかったらできなかったんでしょうけど。著名な画家の方と会うことがあって、「君の作品って何だ?」って言われたときに、何もなかったんですよね。結局、写真館に戻ってやった程度のことだったから。そこで、「ああ、しまった」と思って、何かやらなきゃいけない、撮らなきゃいけないと思ったんです。
そのとき、純粋にパッとボクサーを撮ろうと思ったんです、単純に。それは、もう本当にそう思った、何でかは、わかんないですけど。彼らって減量して、しかもこういう時代で、はっきり言って儲かることではないじゃないですか、あまりにもリスキーだし、何年やってもチャンピオンになれる人って、1人か2人ですよね、世界チャンピオンに。そういうリスクのある世界の中で、やっていってる彼らの息遣いっていうのは、もろに感じたかったんですよね。それを撮ることで僕は感じたいと、たぶん思ったと思うんですね。で、撮り始めたっていうか。
――でも、そのボクサーの中でもチャンピオンというか、……ではなくて、それは大嶋兄弟(大嶋宏成選手・記胤選手)であったりとか、よりコアというか、ハードなほうへいってるわけじゃないですか。
林 そうですね。だから、そこに関してなんですけど、僕、出会ってた人たちだけを撮っていったんですよ、本当に。たとえばいまだったら、チャンピオンクラスになる人とか、なれそうな人とかを狙って行ったら、それは撮らせてもらえます。それは長くやってきた関係で。でも、そうではなくて、僕が撮らせてもらった最初のジムっていうのは、できてまだ1年も経ってないようなジムだったんですよね。古口ボクシングジム(東京都板橋区)って、鬼塚さん(鬼塚勝也氏)を育てたトレーナー(古口哲氏)が開いたジム、ちっちゃなジムなんですけど。そこらへんの彼らっていうのは、もちろんプロボクサーになったばっかりの子らですけど。まだ、新米っていうか、4回戦ボーイじゃないですか。1戦とか2戦とかしてない。僕自身も、その当時っていうのはケガしたり、うんぬんかんぬんあったり、やっと世の中に復帰して、1年は写真館で働いて、まあ3年働いたんですけど、それからボクサーを撮り始めるんですけど。なんか、そういうスタートライン的なものも、同じような感じだったんですね。それも偶然だったんですけど、行ったジムっていうのは。
だから、当然彼らが出場する試合っていうのは、興業の一番最初のほうでしかないわけですね、客がまばらな、誰も注目してないところでっていう。そういうふうに出会っていった、1人、2人、3人っていう彼らを撮ることで、いつかはそういう満員の舞台で、チャンピオンになって……。何となく、そういう夢を見たわけですよね。
 ところが、現実としてはKO負けとかして、人が殴られる音とかも初めて聞いたし。そういう感じだったですよね。その生々しさっていうのは、バーンって、カッコつけてリングに上がってるだけではなくて、倒れまいとして、相手の脚にもしがみついてでもっていうようなのを、一番最初に見ちゃったんですよ、僕。わーっと思って。普通、カッコ悪いじゃないですか、そんなのって。でも、もう本能なんですよね。これを見たときに、ああーっと思って。やっぱり自分自身は、勝ってくれてたらええんやと思ったら、こんな生々しい現実を見せられて落ち込むんですけど。でも、それでも彼らはまたやっていくし。そこをきちっと撮っていこうと。僕が撮り始めたっていう、最初の選手たちを。そういう縁で、また広がっていったっていう感じだったんですよね。
ところが、現実としてはKO負けとかして、人が殴られる音とかも初めて聞いたし。そういう感じだったですよね。その生々しさっていうのは、バーンって、カッコつけてリングに上がってるだけではなくて、倒れまいとして、相手の脚にもしがみついてでもっていうようなのを、一番最初に見ちゃったんですよ、僕。わーっと思って。普通、カッコ悪いじゃないですか、そんなのって。でも、もう本能なんですよね。これを見たときに、ああーっと思って。やっぱり自分自身は、勝ってくれてたらええんやと思ったら、こんな生々しい現実を見せられて落ち込むんですけど。でも、それでも彼らはまたやっていくし。そこをきちっと撮っていこうと。僕が撮り始めたっていう、最初の選手たちを。そういう縁で、また広がっていったっていう感じだったんですよね。
大嶋君だけは、大嶋宏成だけは、求められてっていうか、いろんな作品を撮っていくわけじゃないですか。そしたら、ちょっと見せてたりとかして。ナンバー(『Number』)だったかな、ボクサーっていったら大嶋宏成が注目されてる人間だからって言って。こいつ撮ってみねぇかっていうのが、きっかけだったんですよね。
ずっと身近な選手ばかりではなくて、僕と同じレベルの選手ですね、言ってしまえば、その立場的な。その当時の大嶋っていったら、注目されたすごい存在だったから。そういう人間も撮るべきなんじゃないかっていう、幅を広げる意味で。で、リック吉村との日本タイトルマッチ(2000年2月21日)前でしたけど、お願いしに行って。なんとか撮らせてくれないかっていうことで、輪島会長(輪島功一氏)と大嶋にお願いして。
とにかく、あの頃、マスコミ毎日すごかったんで、「まあ、迷惑のないようにやってくれよ」みたいな感じで、それで大嶋を撮り始めたっていう。そういう感じだったんですけど。