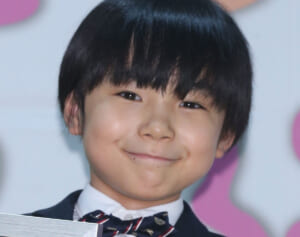「何の前触れもなく『オレ、役者を辞めて演出家になろうと思う』って言いだしたんです。それは収入が激減するということ。これはもう“結婚詐欺だ”と大騒ぎしましたよ。まさに無謀。才能があるのかどうかもわからないのによく賭けられるなって。ただ、自分が素敵だと思う人が新しい仕事に挑戦するなんて、ロマンチックだなと思いました」
演出家の故・蜷川幸雄さん(享年80)の妻であり、写真家・蜷川実花さん(43)の母、蜷川宏子さん(75)は、“あの日のまま”という幸雄さんの書斎で、そう語った。“世界のNINAGAWA”の急逝から100日。初めて明かす劇団立ち上げ秘話−−。
宏子さんにはもう一つの名前がある。’66年に蜷川幸雄さんと結婚したときは「真山知子」という芸名で女優をしていた。当時の幸雄さんは、同じ『劇団青俳』の俳優で収入は妻の半分。一家の大黒柱は宏子さんだった。
「でも、『子供のことは一切考えないでくれ』と言われたのはショックでした。人一倍幸せな家庭に憧れていましたから」
’68年、岡田英次、蟹江敬三、石橋蓮司らと劇団「現代人劇場」を旗揚げ。初の演出作『真情あふるる軽薄さ』の主役は宏子さんだった。
「わかるでしょ、あの性格。身内には甘くないぞと。『ダメだ。ヘタくそ』とほかの人の5倍は言われました。私の役はストリッパー。蜷川は真っ赤なブラジャーとパンティを身につけてほしいと言って染め粉で染めた。普通は女房の裸は見せたくないでしょ。でもあの人は『おっぱい出せよ』ですから」
初日を迎えた舞台は“社会現象”といわれるほどの大成功をおさめた。
「劇場で本物のデモが始まっちゃってね。今はもう当たり前だけど、役者が客席から出てきたり、客席下りてって舞台上げたりとか、全部最初に蜷川がやったことだと思う」
どんなに芝居が評判になっても収入は微々たるもの。宏子さんが働くしかなかった。
「映画やテレビに出演しては、劇団の経費用に引出しにお金を入れておくことが普通になりました。それでもあの人は高級レストランに行く。私が伝票を見て『おうちで食べたらお肉が何キロも買えたね』と言うと、不機嫌になる……。母が家に遊びに来たときも、“安い肉”ですき焼きをしたら、蜷川が『なんだ、まずい肉だ!』とすごい勢いで怒鳴り始めた。母も台所で『何よあの人。宏子のお金で買っているのに』と怒って(笑)」
非日常の目には見えないものに“贅沢”があると説く幸雄さん。宏子さんは顔を引きつらせながら「幸せです」と自分に言い聞かせていた。
「いつしか、『君はいつでも上機嫌でいいね』と言われるようになりましたね」
劇団は人気はあったが、一枚岩ではなかった。70年安保のまっただなか、デモに参加した劇団員が逮捕される。’71年10月、『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』の上演をもって現代人劇場は解散した。
「あんなに頑張っていたのにかわいそうと思ったら悲しくなって、お風呂のふたの上でわんわん泣いちゃった。『なんだか青春が終わった気がするね』と言うと、あの人もうなだれて『そうだな』って」
宏子さんは、景気付けに4年間貯めた“へそくり”を使うことを決意する。
「『これでネパールへ行くか子供をつくるか、どっちかにしましょう』と目の前にポーンと100万円を置きました。ネパールは結婚前から“いつか一緒に行こう”と2人で話していた場所です。迷わず蜷川は子供を選んでくれました」