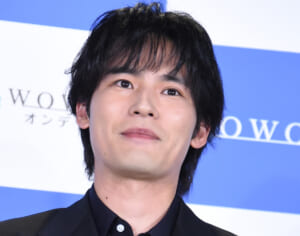「もう親もいませんし、娘も自立していますので、72歳になって、納得して、“死ぬ覚悟のある人間”だなと思っています。やり残したことなんて、死んでみないとわからないですよ」(’15年6月『いきいき』)
死という重いテーマを語りながら、どこまでも自然体の女優・樹木希林(73)。’03年の網膜剥離に続き、’05年の乳がんによる右乳房全摘出の会見、さらに’13年の「私は全身がん」という告白も衝撃的だった。
それでも「がんになってよかった」と語る独自の死生観をあらためて見せつけたのが、1月5日の新聞に見開き全30段・オールカラーで紹介された宝島社の企業広告。英国の画家ミレイの「オフィーリア」をモチーフに、シェイクスピアの悲劇『ハムレット』で小川で死を迎える美女に扮した樹木。「死ぬときぐらい好きにさせてよ」というコピーに、年明け早々、度肝を抜かれた人も多かったようだ。添えられた独白風の文章も彼女らしい。
もともと、がんを患う以前から、樹木の唯一無二ともいえる個性は際立っており、老いや死にまつわる名言は多い。
「若いころからきれいな人は塗っていくんですけど、私は取っていこう、取っていこうとしたんですね。くっついている飾りを全部、取っていこうって。そして、日常生活も削っていくと、なんにもいらなくなっちゃうんです。これがね、とっても調子いいんですよ」(’99年4月『久米宏対話集 最後の晩餐』)
その後、がん闘病を経て、病いの克服というより、むしろ共存するスタイルへ。
「がんがなかったら、私自身がつまらなく生きて、つまらなく死んでいったでしょう。そこそこの人生で終わった。がんというのはね、切って終わりじゃない」(’12年2月17日『週刊朝日』鎌田實氏との対談)
’14年1月には治療終了を宣言したが、がんとの関わりは続いた。
「がんというときに悲劇と思うか喜びと思うか(喜びというのは変だけど)、意味があると思うのかで、人生、生き方が全然違ってきます。年を取って、こんなこともできなくなったと嘆くか、うわあ、こんなこともできなくなっちゃうのかあと面白がるのか」(’14年5月『毎日が発見』)
日々の暮らしぶりも、そんな樹木流の哲学に裏打ちされていた。
「古くなった靴下やシャツも掃除道具として利用して、とにかく最後まで使い切ります。ものたちが『十分に役目を果たし終わった』と思えるように、始末する感覚で暮らしているのです。人間もそれと同じ。十分生きて自分を使い切ったと思えることが、人間冥利に尽きるってことなんじゃないでしょうか」(’15年4月『文藝春秋』)
もちろん、人生の締めくくり方も、またブレがない。
「自分の最後だけは、きちんとシンプルに始末すること、それが最終目標かしら」(同前)
死に方とは、生き方そのもの。年の始まりの今こそ、いつか必ず訪れる死について考えるべきときだということを、これら樹木の名言は教えてくれる。