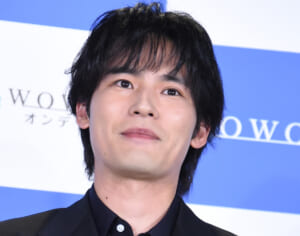「当時、若い女性の見るドラマ枠がフジにはありませんでした。そこで、それまでバラエティの『欽ドン!』を放送していた月曜9時をドラマ枠にしたのです。参考にしたのは、TBSの『男女7人夏物語』でしょう。TBSが開拓した恋愛路線を、勢いのあるフジテレビが奪って成功したわけです」
こう話すのは、中川右介さん(作家・編集者)。入手できうる映像はすべてチェックするなど、綿密な取材を重ね、『月9 101のラブストーリー』(幻冬舎新書)も上梓している。ある時は“トレンディ”な俳優たちの恋模様にヤキモキし、またある時は両親を失った6人きょうだいたちの強い絆に涙を流し……。’17年4月に30周年を迎える「月9」。そんな輝かしい歴史を中川さんの解説で振り返ってみよう。
始まりはテレビ局が舞台の「業界ドラマ」だった!
まだ「月9」という愛称すらなかった’87年4月に始まった『アナウンサーぷっつん物語』。ブームになっていた女子アナを岸本加世子が演じて話題を呼んだ。
「フジテレビがそのまま舞台となった恋愛ドラマ。本物のアナウンサーや『オレたちひょうきん族』の出演者が実名で登場し、バラエティに強いフジならではの“突き抜けた感”はありました」
【第2期】『びんびん』で「月9」の礎を築いた田原俊彦と野村宏伸
’87年8月からスタートしたのが、3作目の『ラジオびんびん物語』。その後、主演の田原俊彦は共演の野村宏伸と『教師びんびん物語』に出演。初めて平均視聴率20%台を記録するなど、初期の月9をけん引していった。
「田原は’80年代のトップアイドルでしたが、レコードの売り上げが下がってきていた。ドラマでアイドルが成功する大きな前例となったのが『ラジオびんびん物語』です」
【第3期】W浅野がけん引するトレンディドラマの量産!
’88年の『君の瞳をタイホする!』は浅野ゆう子が主演。このドラマを皮切りに月9の代名詞でもあるトレンディドラマが生み出されていった。そして3年後の’91年、浅野温子主演の『101回目のプロポーズ』が最高視聴率36.7%を記録。まさにトレンディドラマは絶頂期を迎えた。
「トレンディとは流行の先端という意味ですが、そこから転じて“華やかな都会を舞台とした若い男女の多重恋愛物語”として認識されるようになります。当時、月9のプロデューサーだった大多亮さんが『物語上の必要性からロケ地を決めるのではなく、話題になっている場所や若い人が集まっている場所を選んでロケ地にした』と語っています」
【第4期】野島伸司、坂元裕二……花開く「月9」が育んだ脚本家たち
フジが新しい脚本家を発掘する目的で’87年に創設したのが「ヤングシナリオ大賞」。第1回の大賞は坂元裕二、第2回は野島伸司が受賞した。月曜の夜は銀座からOLが消えたというほどの大ヒット作『東京ラブストーリー』(’91年)は坂元裕二脚本。鈴木保奈美演じるリカの“男のコ”っぽいセリフまわしは一部では反感も読んだが、新鮮な印象を残した。
「野島伸司脚本の『ひとつ屋根の下』(’93年)は、歴代1位の最高視聴率37.8%を誇っていますが、この年、彼はTBSでも『高校教師』をヒットさせています。まさにフジが生んで育てた脚本家が花開いた時代でした」
【第5期】女性プロデューサー&脚本家の時代に突入!
中山美穂が主演した『For You』(’95年)は、後に数多くのヒット作を手がけることになる栗原美和子の、初の単独プロデュース。脚本は中園ミホと小野沢美暁の女性タッグだった。
「W浅野、鈴木保奈美までは“女性が憧れる存在”でしたが、それは同時に、男性が作り出した女性像でもありました。それが女性のプロデューサーと脚本家によって等身大のヒロインを作り出すことに成功しました」
【第6期】「月9」最大のヒーロー木村拓哉がついに登場!
’93年、『あすなろ白書』の取手治役で木村拓哉が月9に初登場。2作目の出演となった『ロングバケーション』(’96年)は、山口智子との共演で平均視聴率29.6%。当時の歴代1位となった。
「その平均視聴率1位を更新したのは、やはり木村拓哉で’97年の『ラブジェネレーション』。そしてそれを抜いたのもまた木村が主演の『HERO』(’01年)。まさに木村こそ月9の申し子のような存在なのです」
【第7期】異色の作品『西遊記』など、なんでもありの「月9」に!
’00年代後半になると、香取慎吾主演の『西遊記』など、ドラマとしては変化球が目立つようになる。
「月9が視聴者のメインターゲットにしていた若い女性層が、夜9時に帰宅しなくなったのかもしれません。そこでより広い層を狙う企画も出て、成功することもありました。でも王道は恋愛ドラマであるべきだと思いますが。テレビをリアルタイムで見る人そのものが減っているのは止めようがありません。そんななかで月9が曲がり角に来ているのは事実でしょう。しかしこの30年間、時代を映す鏡としての存在はけっして色褪せていません。これからも常に時代に寄り添って、50年、60年と、テレビがある限り続けていってほしいドラマ枠です」