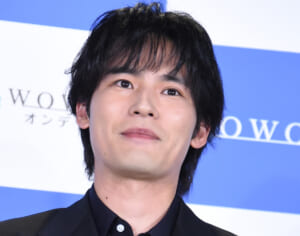「僕は戦争映画でカタルシス(鬱屈した気持ちが浄化されること)を描いてはいけないと思っています。カタルシスというのは不幸なことでも悲しいことでも、それに埋没してしまうとある種、気持ちがいいという状況になる。映画にはそもそも、そのカタルシスが濃厚にあるんです。だから非常に危険。反戦映画を撮っていても、結果的には好戦映画になってしまう恐れがあるんです。昨今、そういう戦争映画が多いんです。主題歌が流れるなか、かっこよく敬礼して大空に飛び立ち、敵艦に突入していく。ああ、次にこの国に何かあれば、僕だってそうするぞ、そういうカタルシスを生んでしまう。映画にはそういう怖い力もあるんです」
映画作家の大林宣彦さん(79)は、『転校生』をはじめとした“尾道三部作”など、名作の数々でみずみずしい感性をフィルムに焼き付けてきた。リハビリ療養中ということで杖こそ突いていたが、病気の前と変わらない、柔らかい口調で語り始めた。
大林さんにがんが見つかったのは、壇一雄の小説を原作とする新作映画『花筐/HANAGATAMI』(12月16日公開)に取り組んでいたときだった。『花筐』は、戦時中の佐賀・唐津を舞台に、「自分らしく生きて、自分らしく死にたい」と切実に願う若者たちを描く群像劇。
「昨年の8月のことです。映画の撮影に入る前に受けた検査結果から『骨に異常があるから、きちんと調べたほうがいい』と言われましてね。唐津の撮影現場に入って、さあ、いよいよ明日から撮影だという日に、唐津赤十字病院で念のため再検査を受けたんです。まず、異常がある骨を診てもらいと、がんが見つかった。続けて検査した大腸や胃は何も問題はなくて。最後に肺を調べてもらったら、ステージ4の肺がんだとわかった。余命半年と診断されました。それでも、撮影は待ってくれません。初日からいきなり2日間、徹夜で撮りました。そして、改めて病院に行ったら今度はいきなり余命3カ月と宣告されて。『たった2日間で余命が3カ月も減るっていうのは大変なことだぞ』と思いましたよ。ですが、自分でも不思議なほどネガティブな気持ちはいっさいなかった。それはやはり、伝えなければいけないメッセージがあるから。命懸けで撮らなければならない映画があるからなんです。僕には、大先輩から託された“遺言”があります」
映画の持つ力を誰よりも知っていたのが黒澤明監督だ。大林さんは50歳のとき、黒澤明監督の映画『夢』のメイキングを作るために連日のように、撮影現場で彼の間近にいる機会があった。『夢』は黒澤監督自身が実際に見た夢を原案にしたオムニバス映画。黒澤監督は大林さんに、映画にはならなかったがこんなストーリーを話してくれたという。
『ある日突然、世界中の人間が手にしている銃を投げ捨てるんだ。すると皆、両手が空になる。しょうがないから目の前にいる敵と抱き合う。そうすると“なんだかこのほうがいいな”と言って、世界から戦争がなくなる、そんな夢の映画だよ。世界中の人がこの映画を見て“本当だ、このほうがいい”と抱き合ってごらん。10人に1人が、いずれ100人に20人に増えて、“ああ、このほうがいいや”と思う人がどんどん増えていくよ。そういう映画を20年も30年も上映してごらん。映画を見た世界中の人がそう思ってくれたらどうだ、大林くん、そういう力と美しさが映画にはあるんだよ』
そして、黒澤監督はこうも大林さんに言った。
『しかし、平和を確立するのは時間がかかる。愚かな人間は、戦争はすぐ始められるけれど、平和を確立するには、少なくとも400年はかかるだろう。俺があと400年生きて、映画を作り続ければ世界を平和にしてみせるんだが……俺はもう80歳だ。人生がもう足りない。ところで大林くん、きみはいくつだ?』
聞かれるがまま、大林さんは当時の年齢を答えた。「50歳です」と。
『そうか、50歳か。ならば俺より少しは先に行けるだろう。そしてきみが無理だったら、きみの子どもが、さらにはきみの孫たちが、少しずつ俺の先の映画を撮り続けてほしい。そして、いつか俺の400年先の映画を作ってほしい。そのときにはきっと、映画の力で世界から戦争がなくなるぞ。だから、俺たちの続きをやってね』
「これが“世界のクロサワ”から託された、遺言なんです。そして、本当に世界から戦争がなくなったら、映画もいらないんです。皆が健康になったら医師が失業するようにね。同じように、戦争がない世界が実現したら平和を願い、平和をつくれる映画というメディアもいらなくなる。だから僕は映画がなくなる日を夢見ながら、映画を撮り続けてきたのかもしれません」