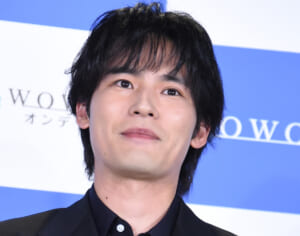「慶應ボーイが銀幕のスターになった瞬間。それが石原裕次郎(享年52)の登場です。まさに慶應ボーイのレジェンド的な存在ですね」
そう語るのは芸能評論家の城下尊之氏。高度成長期の時代、頭がよく、かっこいい、おしゃれで育ちのよさも際立つイメージの慶應ボーイは庶民の憧れ。芸能界入りは、「一流企業のエリートコースが約束されているのに、なぜ役者に!」と驚かれる時代でもあった。
当時、裕次郎の兄である慎太郎はデビュー作『太陽の季節』で芥川賞を受賞(’56年)したばかり。気鋭の新進作家として注目を集め、享楽的で無軌道な若者たちを指す“太陽族”は流行語となった。
このデビュー作が映画化され、ロケ先に現れた弟の裕次郎がプロデューサーの目にとまり、急きょ出演することになったというのは有名な話だ。
「当時の役者さんは下積みを経てスターになるのが主流。ですが、裕次郎さんは育ちのよさとあのルックスで、デビュー作に出演してから、たちまちスターになった。『太陽の季節』はもともと裕次郎さんの見聞きした経験をお兄さんに語り聞かせたことで生まれた作品で、主人公のモデルも実在の慶應ボーイ。裕次郎さんはその友人の役ですから演じるのも地で行けば十分だったのです」(城下氏)
加山雄三(81)も、デビュー翌年には、慶應ボーイを地で演じた『若大将』シリーズでブレーク。主役の田沼雄一は京南大学に通う老舗のすき焼き店『田能久』の息子、という設定でシリーズは全17作。若大将が社会人になっても続いた。
「まさに加山雄三そのものを主人公にした作品ですから、育ちがよく爽やかな好青年役をそのまま演じればよかったのです。シリーズが終わった後、新境地を開くため、スナイパーの役を演じたことがありましたが、こちらはものすごく違和感がありました」(城下氏)
イメチェンは不可能。爽やかなイメージを崩そうにも崩せないところも慶應ボーイの特性だ。
若いころから主役級。「慶應ボーイ」を売りにする必要性がなかったのか、あまり知られていないのが石坂浩二(77)。
「知性派で温厚なイメージですが、ふだんもあのとおりの方。時代劇では専門家並みに史実に精通し、時代考証もできてしまう貴重な存在です」(城下氏)
本人はいたって自然体でありながらも、育ちのよさが自然と周囲に伝わってしまう。そんな慶應ボーイの源泉となる“慶應”という組織の特質について、受験コンサルタントで『慶應幼稚舎』(幻冬舎新書)の著書もある石井至氏はこう解説する。
「慶應には『社中協力』というコンセプトがあります。塾生は一致団結して助け合い、社会に出ても互いに引き立て合う、といったような意味です。なかでもその精神を強く受け継いでいるのが、“生粋”の慶應ボーイといわれる『幼稚舎出身者』。彼らはコネも強力ですから、就職までは超一流コースを悠々と歩めるわけです」
しかし社会に出れば、当然そうした「看板」にも限界があるため、ダメサラリーマンに落ち着いてしまうケースも多いという。
「彼らは頻繁に同窓会を開いて、社会に出ても強い絆で結ばれています。育ちがいいので、社内でのポジションなんて、いちいち気にしないんでしょうね」(石井氏)
「天は人の上に人をつくらず」と説いたのは慶應義塾の創始者・福沢諭吉だが、石井氏によれば、「実際の慶應内には厳然たるヒエラルキーが存在し、その頂点にいるのが幼稚舎出身者」だという。いっぽうで、大学からの入学者は学力は高いけれど「キャンパスのエキストラ」という位置付け。要はどれだけ長く「慶應」に身を置いているかが重要なのだ。
こうした“塾内”ヒエラルキーのなかで、育ちのよさや、ブレない安定感といった「らしさ」を自然と培ってくる慶應ボーイたち。その存在は、まさに「一日にして成らず」なのかも!?