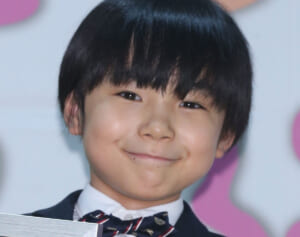創刊60周年の節目の年を迎えた『女性自身』。60年にわたる歴史のなかで、華やかに誌面を飾ってくれたスターや、女性の新しい生き方を提示してくれた有名人を再訪。“『女性自身』と私”の思い出を語ってもらいました!
「私が『女性自身』で記者をしていたのは、22歳の夏からの5年3カ月でしたが、実にいろいろなことを学ばせてもらいました」
元『女性自身』記者で、現在は出版・映像・文化イベントなどのプロデューサーとして活躍する残間里江子さん(68)。短大を出て、静岡放送のアナウンサーとして2年半勤務したあと「新しい世界を目指したい」と再上京した。
「この先、何をするかも決めずに辞めましたから、とにかく人に会おうと『1日最低10人の新しい人に会おう!』を実践していたある日、新宿のゴールデン街のバーで、偶然、『女性自身』編集部で人を探していると耳にしたのです」
指定の日に履歴書を持って訪れると、いきなりデスクと称する男性から“テレビ情報”というページを担当するように言われた。
「『まずはテレビ局に行ってネタを拾ってきなさい』と命じられたのです。『えっ、ネタ!? 拾う!?』と最初は戸惑いましたが、都内に6つあるテレビ局の番組宣伝部や広報部に日参しました。やがて、『この部屋に残間ちゃんのデスクを置いてやるよ』と、声をかけてくれる人まで出てきて。仕事は足でするものだと教わりました」
取材のアポイントを取るときには、「『女性自身』ですが……」と言った途端、電話を切られることを何度も経験した。
「私がどんな人間かなど関係なく、看板だけで。それでもなかには丁寧に取材内容を説明すると、最後は了承してくれる人も4割くらいはいました。こうした体験があったからこそ、今も仕事を続けていられるのだと思います。というのも、プロデューサーの仕事は、依頼・説得が主たる仕事ですからね。この『拒絶体験』には、すいぶん鍛えられました」
人との適正な距離感の取り方も『女性自身』の仕事を通じて教えてもらった。
「ちょっと親しくなったからといってズカズカ入り込まないことですね。山口百恵さんとの『蒼い時』の仕事がうまくいったのも、用事もないのに連絡などはしないというように、ベタベタした付き合いをしなかったからだと思います。あのころの『女性自身』を一言でいえば、『骨のある雑誌』ですね。みんな、必死でしたよ。誰よりもいいプランを出して、取材対象者にも食い下がって、少しでもジャーナリスティックな精神で伝えたいと、編集者も記者も気概がありました」
創刊60年を人間にたとえるなら還暦だ。
「『女性自身』も、暦を一巡りしたのですから、再びゼロ地点からリスタートを切れば、まだまだ大きな可能性を秘めた媒体だと思っています。昨今の『人生100年時代』や『女性活躍時代』は政治的スローガンのような気もしていますが、とはいえ、この流れをチャンスと捉えて、新しい自分を創造する女性も増えるのではないでしょうか。『女性自身』には、そんな女性の多様な生き方を肯定し、『自分の人生を諦めないで』と、応援し続けてほしいと願っています」