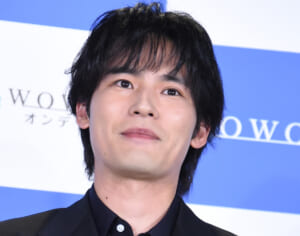「昨年11月ごろから、新作の公開日に照準を合わせて、大事をとって自宅で療養していました。父は何よりも、母のそばを離れたくない。とにかく自宅が大好きな人でした。亡くなる当日まで、寝室の窓から見える八重桜を眺めながら『きれいだね』と、日課のように話をしていました」
悲しみをこらえながら、本誌のインタビューに答えてくれたのは、4月10日、肺がんのため亡くなった映画作家・大林宣彦さん(享年82)のひとり娘、千茱萸さん。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により公開は延期となったが、大林さんが亡くなった日は、くしくも監督を務めた最新作『海辺の映画館−キネマの玉手箱』の公開予定日だった。
’16年8月、「肺がんステージ4、余命3カ月」という宣告を受けた大林さん。本誌はその1年後の’17年8月、そして2年4カ月後の’18年12月に、大林さんに2度インタビューをしている。
本誌記者に語りかける大林さんの口調は、まるで親がわが子に語りかけるように優しかった。そして自らの人生哲学を語る情熱は、宣告された余命を大幅に超えて生き続けた大林さんのエネルギッシュさを物語っていた。
がん闘病、家族の絆、そして映画にこめた「反戦」への思い……。監督が本誌に残した、約9時間にも及ぶ“魂のメッセージ”に、もう一度触れてみようーー。
「’16年8月、『花筐/HANAGATAMI』の撮影に入る前に受けた検査で、“骨に異常があるから、きちんと調べたほうがいい”と言われましてね。佐賀県唐津市の撮影現場に入って、さぁいよいよ明日から撮影だという日に、唐津赤十字病院で再検査を受けたんです。まず骨に異常があるということだったので、骨を診てもらったら、がんが見つかった。続けて大腸、胃を調べたらステージ4の肺がんだとわかった。このときは、余命半年と診断されました」
’17年8月、がん宣言の様子をそう教えてくれた大林さん。宣告は撮影が始まる前日のことだったが、大林さんは落ち込むどころか、撮影初日からなんと2日間徹夜で撮影をしたという。
「撮影後に病院に行ったら、今度はいきなり“余命3カ月”と宣告されて……。たった2日間で余命が3カ月も減るっていうのは大変なことだぞ、と思いましたよ。ですが、自分でも不思議なほどネガティブな気持ちにはいっさいならなかった。それはやはり、僕には伝えなければいけないメッセージがあるから。命懸けで撮らなければならない映画があるからなんです。だから、とても死んじゃいられねえやって(笑)」
大林さんにとって、がんとは“共存共栄するもの”。その捉え方は、驚くほどポジティブだった。
「がんが骨に転移していたのも、振り返ればありがたいことだった。最初に見つかったのは骨の異常でしたから。転移していなかったらがんが発見できなかった。つまりは今ごろ死んでいるわけです。もう『転移よ、ありがとう』と」
まさに命懸けで撮った映画『花筐/HANAGATAMI』は完成。だがその直後には、遺作となった『海辺の映画館−キネマの玉手箱』の企画が動きだしていた。
’18年7〜8月の猛暑のなか、同作のメインロケが、大林さんの故郷である広島県尾道市で行われた。
「がんになってからも、撮影現場にいるときは“死んでる暇がない”と思うぐらい元気が出る。僕は映画という免疫によって、生かされていると思っているんだよ」
’18年12月に取材に伺ったときは、まさに製作の真っ最中だった大林さん。当時、すでに年齢は80歳だった。
「体力がなくなりましたね〜。胸から上は元気なんだけど、映画は足で作るものだと、つくづく実感しました……」
珍しく弱音も口にしたが、ほほ笑みながら、すぐにこんなエピソードを話してくれた。
「がんになってから174センチあった身長が、今160センチを切っているので、14センチ以上も縮んじゃった。でもね、いつの間にか糖尿病が治ったんです。それと前立腺肥大で1時間に1回はトイレに行っていたのが、最近では8時間ぐらいトイレに行かなくても大丈夫になってね。何もしないで2つの病気が治った。これもがんのおかげかもしれない。何事も楽天的に考えればいいと思っているんです」
どんなときでも、自分が抱える苦境を前向きに捉える。大林さんの闘病生活は、そんなポジティブさがにじみ出ていたように見えた。
「女性自身」2020年5月5日号 掲載