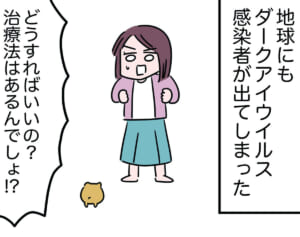去る1月31日に行われた全豪オープン車いすテニス男子シングルス決勝で、国枝慎吾選手はフランスのステファン・ウデ選手をストレートで下し単複3連覇を達成。同時に大会8度目の優勝も飾りました。車いすテニス界における国枝選手の実績は圧倒的です。グランドスラムと呼ばれる4大大会での優勝回数は、シングルス18回、ダブルス18回の計36回。男子世界歴代最多記録を誇っています。そして、14年には年間グランドスラムという偉業を達成しています。
9歳のとき脊髄腫瘍で下半身麻痺になり、車いす生活となった国枝選手。彼は、母親の勧めで小学校6年生から車いすテニスを始めました。強靭な精神力や圧倒的な練習量ですぐ頭角を現し、06年には世界ランキング1位に。以降、その座を譲っていません。これは本当にすごいことです。どんなスポーツでも世界一になった選手はいますが、その座を10年近く守るということは極めて難しい。頂上に上りつめた人間は、どこかでモチベーションを失いがちです。それはきっと、追い越すライバルがいなくなるからでしょう。
あるインタビューで国枝選手は「米国での試合中に突然、対戦相手ではなく内なる自分との戦いに目覚めた」と答えています。練習の目的は2位に勝つことでも1位を維持することでもなく、自分を別の次元へと昇華させていくことであると気づいたのです。ライバルは昨日の自分。昨日の自分よりも成長した明日の自分を作るため、今日努力するのが国枝選手なのだと思います。
このようにモチベーションを自分のなかに見いせる人は“あらゆる努力は自分の成長のため”という実感のもと、過程を楽しむことが可能になる。それは“練習に対する集中力”にもつながります。国枝選手のそれはすさまじいものがあり、「たとえ練習でも決勝戦を戦っているのと同じくらいの集中力と緊張感を持つことができる」と語っています。あたかも実戦のような練習を積み重ねた結果、あのとてつもない強さを手に入れたわけです。

私が感銘を受けたもう一つの理由は、国枝選手の“試練を受け入れて感謝する”姿勢です。私が彼ほどの病気をしたら、失意に陥ると思います。しかし国枝選手は病気を真正面から受け入れ、今生きていることが幸運だと感じることができる。そして努力できることに感謝を抱くことができる人間です。喪失に絶望せず、失っていないものがあることに感謝する。それを大切にする人生の素晴らしさを、彼は教えてくれた気がします。
そういう国枝選手にとって、「限界」の意味は一般の人と違うのだと思います。限界とは、最善を尽くした末にたどり着く最終地点。それは事後に確認するもので、事前に設定するものではない。限界は、人を楽にさせるところがあります。限界だと認めれば、人は諦められるからです。しかし、それが本当に自分の限界なのかは怪しい。
限界を設けるとは“できること”と“できないこと”を分けること。すなわち“可能性と限界の線引き”を意味します。重要なのは、その線引きが自身の努力で変えられるという事実であり、それに気づくことです。昨日の限界は今日の限界ではなく、今日の限界は明日の限界ではない。昨日の限界を、今日の努力を通じて、明日の可能性につなげていく。そうした人生のなかで、限界の領域はだんだんと小さくなっていくのです。
可能性の前で限界に逃げる人ではなく、限界の前で可能性を見いだせる人になる。頑なになっている自分を液体に戻し、信念という節を作る。そうすることで、揺れても折れない“竹のようなしなやかさ”を手に入れたいものです。
ジョン・キム 吉本ばなな 「ジョンとばななの幸せって何ですか」(光文社刊・本体1,000円+税)
吉本ばなな
1964年東京生まれ。’87年『キッチン』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。’88年『ムーンライト・シャドウ』で泉鏡花文学賞、’89年『キッチン』『うたかた/サンクチュアリ』で芸術選奨文部大臣新人賞、同年『TUGUMI』で山本周五郎賞、’95年『アムリタ』で紫式部文学賞、’00年『不倫と南米』でドゥマゴ文学賞をそれぞれ受賞。海外でも多くの賞を受賞し、作品は30カ国以上で翻訳・出版されている。近著に『鳥たち』(集英社刊)、『ふなふな船橋』(朝日新聞出版社刊)など。