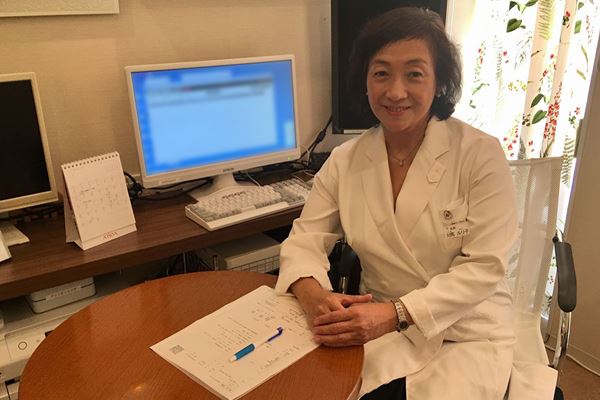東京の銀座と新宿で、「女性ライフクリニック」を開業する産婦人科医で医学博士の対馬ルリ子さん(62)。婦人科、乳腺科、内科、皮膚科などを備え、女性の心と体をトータルに診ている。対馬さんは、7都府県に緊急事態宣言が出た翌日の4月8日から、銀座のクリニックを開放。コロナ禍で、DV被害などを受ける女性たちの駆け込み寺として機能させてきた。
弱い立場に追いやられた女性たちに寄り添い、長年サポートをしている対馬さん。これまでの道のりは、決して平たんなものではなかった。
対馬さんは、東京大学医学部を目指し浪人するため18歳で上京。東大医学部は落ちたが、地元、弘前大学医学部に見事合格。78年、進学のため再び、故郷の青森に戻ることになった。
「東京は当時、ウーマンリブ運動のまっただ中でね。私も、いままで以上に、男女の性差について考えるようになっていきました。入学してすぐ“女医の卵の会”を結成しました。女子の卒業生に、結婚後も医師の仕事をしているかアンケート調査したり、医学部の学祭で“私たちの性を語り合おう”というシンポジウムを開いたり」
そのシンポジウムでは、考え方の古い教授とぶつかった。
「婦人科医の男性教授に、性をテーマに講演してくださいと依頼したら、『あなたのようなうら若き乙女が語る問題ではない』と言われてね。当時から、望まない妊娠をして、中絶を強いられる女友達が身近にいましたから、腹が立って。『セックスも妊娠も中絶も、私たちがいま直面していることなんです!』って、教授に抗議したら、渋々、引き受けてくれて。結果は、大盛況。打ち上げでは、その教授が、『僕が間違っていました』と謝ってくれたんですよ」
時代は、男女雇用機会均等法が施行される前の80年代前半。男性優位な医師の世界で、女性が認められるのは容易ではなかった。
「女性を助けられる産婦人科医になろうと思いました。しかしどこのドクターも、『悪いこと言わないから女の子は眼科か皮膚科になって、やさしいダンナさんを見つけたほうがいいよ』と言うんです。産婦人科は、24時間体制だし、手術や当直も多くて体力が要るから、と。女性は産婦人科の研修に入れてもらえないんですか、と聞いたら、うちは無理だ、とあちこち断られて。東大病院だけは、『そろそろ女性を入れようかと思っている』という感じだったんです」
対馬さんは、26歳で東京大学医学部産婦人科に入局。男性医師と同じ仕事をテキパキとこなし、実力をつけていき、44歳で「ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック」(現・女性ライフクリニック銀座)を開業。
次第に、対馬さんの活躍もあってか“女医ブーム”が到来。国も動きはじめ、各地の国立病院にも女医が女性を診る“女性外来”がつくられた。
「でも、あれは打上げ花火で終わったんです。研修を終えたばかりの女性医師を配置しただけ。DVでも更年期の話でも、研修を積まないと理解できません。結局、不採算部門だということで、潰されてしまったところが多い」
一方で、対馬先生のクリニックには、あちこちの産婦人科をさまよった結果、やっとたどりついたという女性たちの受診が増えた。じっくり話を聞くからこそ、見えてくるものがある。DVもそのひとつだ。
「長年DVを受けている人は、自己価値感が低いので、自分でDVを受けていると気づいてない人も多い」
背後にDVが隠れていると、治療の効果が上がりにくいという。
「ある患者さんには、治療をしつつ、家を出る相談にものっていました。ある日、その方は、夫にナイフで切り裂かれたバッグを持ってきて、『私、決心したから、先生にこれを証拠として持っていてもらいたいんです』と。彼女は、そのあと家を飛び出してシェルターに行きました」
数々の壁を乗り越え、立場の弱い女性を助け続ける対馬さん。コロナ禍でDV被害が増えている只中で、さらに支援の輪を広げていく。
「女性自身」2020年6月16日号 掲載