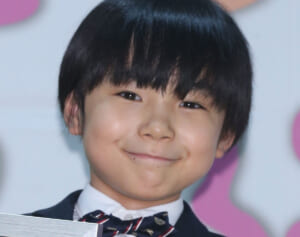’69年のバンド結成以来、常に日本のROCKの最先端を走り続ける『頭脳警察』。その頭脳警察が、実に18年ぶりにNEWアルバムを発表!そして、その活動のすべてを5時間14分―3部作に収めた『ドキュメンタリー頭脳警察』を公開するPANTA、TOSHIにロングインタビュー。

「止まっているということと、変わらないということは、違うんだよ」――PANTA
インタビュー/DJtaba 撮影/高田崇平 サポート/吉田茂樹
VOL.1
――今回は『女性自身』で取材できるというのは非常に光栄に思っています。
PANTA あ、フジロックのレポートありがとうございました(笑)。
――よろしくお願いします。今回作品を見させていただいて、ドキュメンタリーというのはレコーディングとは違うもので、すごく自分たちをさらすものじゃないですか。本当に視覚的にもさらし出すものだと思うんですけども、あえて今回PANTAさんとTOSHIさんがドキュメンタリーという行為をやろうと思ったきっかけとか理由というのは。
 PANTA きっかけはね、ファンクラブをやってくれてる須田君と瀬々監督が、頭脳警察の映画を撮りたいということで話しに来てくれたんです。そこからスタートしたんですけど、ただ、俺とTOSHIということであればそれでいいんですけども、自分が陽炎というソロバンドを始めたばっかりだし、いつ頭脳警察をやるとかそういうふうな、まあ、ずっと気持ちの中では継続してるんですけどね、いつやってもいいんですけど、今ソロで動いてる時に頭脳警察を出すわけにいかないから、そういう話をしたんですけれども、それでもずっと回し続けるということで、そういう時の監督の気持ちってどうなのかなあという。例えば、ある意味ロードムービーじゃないんだけれども、こうやってずっと二人を追っかけて、かつまた、こっちも頭脳警察をいつやるとかそういう着地点もないわけですよね。そんな中でカメラを回してた監督の気持ちを知りたいとこですよね、逆にね。
PANTA きっかけはね、ファンクラブをやってくれてる須田君と瀬々監督が、頭脳警察の映画を撮りたいということで話しに来てくれたんです。そこからスタートしたんですけど、ただ、俺とTOSHIということであればそれでいいんですけども、自分が陽炎というソロバンドを始めたばっかりだし、いつ頭脳警察をやるとかそういうふうな、まあ、ずっと気持ちの中では継続してるんですけどね、いつやってもいいんですけど、今ソロで動いてる時に頭脳警察を出すわけにいかないから、そういう話をしたんですけれども、それでもずっと回し続けるということで、そういう時の監督の気持ちってどうなのかなあという。例えば、ある意味ロードムービーじゃないんだけれども、こうやってずっと二人を追っかけて、かつまた、こっちも頭脳警察をいつやるとかそういう着地点もないわけですよね。そんな中でカメラを回してた監督の気持ちを知りたいとこですよね、逆にね。
結果的に、「時代はサーカスの象にのって」を発表して、いろんな複合的な要素が絡まって頭脳警察をやり始めるというところに至ったんですけれども、まあ、そこまでは非常に監督の中でもいろいろ葛藤があったと思いますよ。いつまで回したらいいんだろうとか。何か目標があって、例えばワールドツアーだとか武道館に向けてとか、何かそんなような着地点が見えてて、それまでの過程を追うという形であれば、ドキュメンタリーもどうやってそのストーリーを組んでいったらいいのかとかいろいろ考えも出てくるんでしょうけれども、こういった形で出口の見えない(笑)、着地点の見えない中で、カメラを回し続けるというのはどういう気持ちなんだろうなという。だから、結果的に250時間という…
――そうですよね。3部作ですもんね。
PANTA うん。
――どうですか、TOSHIさん、そのへんは。ドキュメンタリー、常にカメラがそばにいるわけですから。
TOSHI いや、でも、そんなに、というか、もうほとんど途中からは全然もう意識しないし、だから、格好もつけてないから(笑)。自分たちであれを見た時には楽しかったけどね、逆に。
――最近では、あがた森魚さんのドキュメンタリーもあって、あがたさんが組んだのは20代とか30代のスタッフだったらしいんです。で、その彼らが、20代、30代の人たちの入り込み方がすごく遠慮深くて、「もっと入ってこいよ」という感じだったと。そのへんの人間関係ちょっと難しかったなと。そういう意味では今回の撮影スタッフとかというのはどうだったんですか。
PANTA 本当に空気のような存在と言ったらいいのかな。まったく意識しなかったね。
TOSHI うん。
PANTA だから、逆にその試写を見せてもらった時に、「えーっ!もう少しカッコつけときゃよかったな」って(笑)。だから、友達からクレームがつきました。NGが。仲間のファッション関係、音楽関係。あまりに普段の自分たちと接する姿過ぎると。だから、こういう公の場なんだから、もっとパブリックイメージというかロッカーとか、やっぱりそれなりに着るものも含めてファッションも含めてね、カッコつけてほしかったって(笑)。今さら言ってもしょうがないけどっていう。友達関係からNGが出て(笑)。
TOSHI レコーディング中に寝てるんじゃないよ(笑)。
PANTA (笑)
――僕らの世代のリアル頭脳警察というのは、再結成の時なんですよね。やっぱり70年代は僕らまだ子供だったので。ちなみに僕は64年生まれなので。
PANTA ああ、そうですか。
――だから、その時の頭脳警察では、初めて見る画像もずいぶんあったりとかして、そういうふうに見ると、PANTAさん、ソロの活動があって、TOSHIさんはいろんな方とのサポートとかドラマーとしてのTOSHIさんのイメージがわれわれ強かったんです。そういう中であえてお2人にとって40年目の今、頭脳警察とは何だったんですか。
PANTA どうでしょう、40年目の頭脳警察。
TOSHI 40年目の頭脳警察? 気がついたら40年なってましたって(笑)。
PANTA フォードGT40っての大好きでしたけどね(笑)。
TOSHI でも、なんか長くなればなるほど元に戻るじゃないけど、10代の時の感覚にどんどん戻っていくような。
PANTA 年取ると子供に戻るんですよ(笑)。
TOSHI なんか今回のレコーディングも、昔ね、本当にセカンドとかファーストをやってる頃の勢いでというか、そういう感じでレコーディングもやったしね。
PANTA 奇しくもというかこう、いういろいろ取材してて、ある音楽評論家がね、「PANTAさん、これ新曲じゃなくて、当時書きためてた曲ですか」とか質問が出てきて、「一応全部新曲だよ」つって。「いや、セカンドアルバムの頃に書いてた曲なのかと思った」。
TOSHI そうだよね。そういう感じですよね。
PANTA そんな感じ(笑)。
TOSHI うん。初心に戻ったんじゃないけど(笑)。
PANTA シンプルというか。
TOSHI うん。昔の10代っていうかね、ハタチの頃の感じだった。
――ドキュメンタリー中に「変わらない、止まらない」って言葉があって、まさにそのとおりの活動をされたと思うんですけど、これすごい難しいことじゃないですか。
PANTA そうですね。
――変わらないということはあるけど止まっちゃう人っていっぱいいて、例えば今のミュージックシーンって懐メロ化がどんどん進んでる。カラオケができてから、切り取られた時代の歌を今歌うみたいなことってすごく多い。先日、ドアーズでライブを見させていただいて、収録されてないバージョンの「俺たちに明日はない」とか「Born To Be Wild」とか。今「Born To Be Wild」を頭脳警察がやるのかというところにすごいビックリしたんですけど、逆にそこを維持できたというか、維持してこれたものというエネルギーはどこに?
TOSHI (笑)
PANTA 何でしょう。酒ですか。女ですか(笑)。
TOSHI 私の場合は、やっぱり好きだからだよね(笑)。これに尽きる。
PANTA うん。好きが一番ですね。逆に今の世代、好きなものが見つからないというのはね、非常につらいと思いますよ。あまりに情報が氾濫していて飽和状態になっていて、自分が好きなものが選べない、見つからない。別に不登校児童の話をするわけじゃないんだけど、拒否するのはいいんだけど、何か自分の好きなものに向かって邁進する、無我夢中になる。例えば恋でもいいですよ。恋にたとえれば本当に盲目になるじゃないですか。それと同じように、やっぱり好きなものに向かったら何の犠牲もいとわないんですよ。
TOSHI 人から見たら苦労だけど、別に苦労じゃないもんな。
PANTA そうそう。
TOSHI というとこもあるもんね。
PANTA 演劇人なんか見てても、徹夜で大道具作って、自分でチケット売って、そういうのを当時のロックバンド、当時のね。ロックバンド、いやアンプを運ぶのかったるいとかね、もう見せてやりたいなと思った。好きってのはこういうことなんだよって。生半可にね、有名になりたいとか、カネを儲けたいとか、女にモテたいとか、そんな気持ちじゃ絶対できない。まあ、それはそれでやるのも全然OKだけど、動機なんてね。でも、好きだったらやっぱりもっと追求するはずだよね。向上心も出てくるだろうし。好きが自分を夢中にさせるという、いまだにその夢中は続いてますね。夢の中と書いて夢中だけどさ(笑)。
TOSHI (笑)
――いや、僕は、ちょうどPANTAさんがスイート路線のLPを出された時が思春期だったので、もろに聴いてる僕らは、別にそれを拒絶ではなくて素直に受け入れさせていただいたんですね。ああいうスイートなラブソング。でも、頭脳警察のファンの方々って、やっぱりパブリックイメージをすごく頭脳警察に持っていて。今考えて、不買運動というのが実際にあったということが僕らはちょっとピンと来なかったわけでして。TOSHIさんの1部の言葉の中に、やっぱり頭脳警察というのに戦う何かを託してる人たちがいたというか、なんか頭脳警察があること、自分を乗せていくみたいものがあったと思うんですけど、そういうファンとのズレじゃないですけど、そこらへんというのは何か、活動してる中でフラストレーションみたいなのがやっぱりあったんですか。
PANTA あるね。
TOSHI いや、70年代の後半なんてもう、ジレンマとフラストレーションと(笑)、それしかなかったよね。
PANTA うん。
――そこはかなり強烈なものだったですか。
TOSHI うん、強烈っていうかやっぱり、うん……なんかやっぱり疲れた、本当に疲れたって感じだけどね。
PANTA だから、オーディエンスというかお客さんというか、望むものと自分たちがやりたいこととのズレがね、極端にあったから。純粋なロックバンドというものがあって、その政治的なものとかそういうのはある種、ウソではないけれど亜流というか、一部、ごくごく一部でしかない。