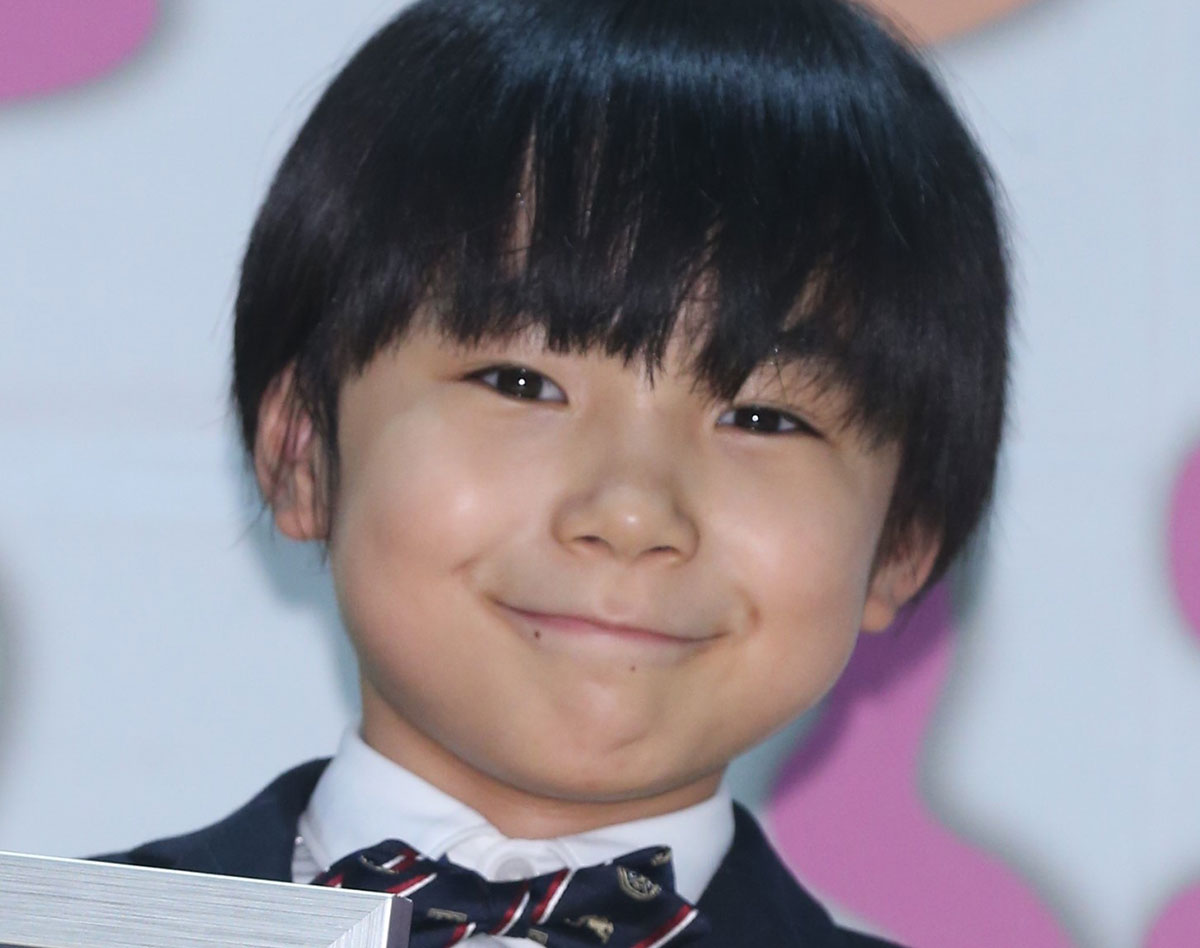「福山雅治が主演ということでフジテレビも宣伝に力を入れていた『ラヴソング』ですが、半分ヒューマンドラマで、残りが恋愛ドラマ……。フジテレビの“月9”を、そんな中途半端なドラマにしたら、もったいないです」
そう語るのはコラムニストのペリー荻野さん。鳴り物入りでスタートした『ラヴソング』だが、かなりの苦戦を強いられた。視聴率は初回こそ10%超えしたものの、その後は低空飛行を続け、“月9”の平均視聴率の史上最低記録を更新するといわれている(6月10日現在)。ペリーさんが続ける。
「月9といえば、フジテレビの看板ドラマ枠。キラキラと星のように輝くトレンディドラマを生み出してきました。でも、そのほとんどが、ストーリーには重きを置いていませんでした。実際、『物語を覚えている?』といわれても、多くの人は答えられないでしょう。それでも夢中で見ていた……。それがトレンディドラマなのです」
’88年の月9『君の瞳をタイホする!』で始まった“トレンディ路線”。都会を舞台に恋愛と流行を交えて描いたドラマは、若い女性の心をつかんで離さなかった。とくに浅野温子、浅野ゆう子の“W浅野”が主演した『抱きしめたい!』が印象的だとペリーさんが言う。
「トレンディドラマは“すごく遠い夢”ではなく、普通の女のコでも手が届きそうな“近い夢”を見せてくれました。“普通のOLがキレイな部屋に住めるもんか!”ということはさておき、W浅野が着こなしていた服の情報が、番組の最後には衣装クレジットとして流れる。ファッション以外にも、食べ物、住まい、ヘアスタイル、会話など、ドラマとはいえストーリーはいつも置き去りで、あたかもカタログ雑誌をそのまま映像化したようなもの。でも、流行を追うことで、自分を満たそうと思っていた若者たちにとって、ちょっと手を伸ばせば届くようなアイテムが、たくさん散らばっていたのが、この頃のドラマでした」
ドラマウオッチャーで、エッセイストの田幸和歌子さんは「フジテレビといえばやっぱり『ロンバケ(ロングバケーション)』ですが、ほかのドラマでも、常にチャレンジしていました」と語る。
「深夜ドラマ『やっぱり猫が好き』の脚本を書いた三谷幸喜さんをシリアスなドラマに起用した『振り返れば奴がいる』が象徴的です。“喜劇しか書けない”と嫌がる三谷さんに無理やり脚本を担当させたことで、『古畑任三郎』シリーズが生まれました。またストーリー展開があまりに早くジェットコースター系ドラマといわれた『もう誰も愛さない』もフジテレビのドラマらしい作品です。多重人格者、殺人、復讐劇がどんどん出てくる“とんでも展開がてんこ盛り”。きわめつきが伊藤かずえさんの生首ゴロリというシーン。ファンから抗議があったそうですが、今ならクレームがスポンサーに殺到するでしょう。今にしてみれば放送されていたのが不思議なほどの“おバカドラマ”ではありますが、みんな没頭して見ていたんです」
そんなフジテレビの攻めの姿勢が、視聴者の心を揺さぶったと、田幸さんが続ける。
「深津絵里さん主演の『きらきらひかる』は、郷田マモラのマンガを原作としたドラマです。しかし、独特の画風のマンガとはまったく異なり、オシャレに主人公を変化させて、ドラマに落とし込んでいました。また常盤貴子さんと深津さんが共演した『カバチタレ!』もマンガの実写版。しかも主人公が男性だったのに、性別を変えて作り込んだドラマです。どちらもおじさん雑誌で連載されていたマンガのドラマ化ですが、世界観を重要視しながら、巧妙なアレンジを施して、女のコたちを夢中にさせてくれました」
ペリーさんがこんなエピソードを語ってくれた。
「フジテレビは、他局に比べて遅れて開局した後発のテレビ局。挑戦者の自負がありました。’60年代に一世を風靡した時代劇『三匹の侍』は、日本で初めて、人を斬るシーンに音をつけました。それを担当したのは、フジテレビの社員で、のちに映画監督になった五社英雄さん。肉や野菜を切って、リアルな音を作り出して、視聴者の度肝を抜いたのです。フジテレビといえば、そのころから、常識にとらわれず、時代を先取りして、面白がるのが特徴。そんな野武士的な発想や空気感が、’80年代後半にブームとなったトレンディドラマにも受け継がれていったのでしょう」