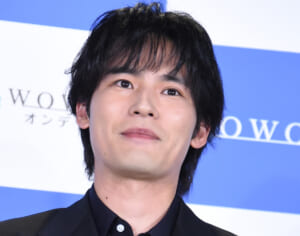「この世界に入って30周年なんですが、あまり実感がないんです。『もう30年?』という感じ。いまだに師匠の門を初めてたたいた16歳のときのままの気持ちです」
こう話すのは、落語家・林家きく姫(47)。’87年に林家木久蔵(当時)に入門し、前座時代からバラエティ番組などで活躍。’01年秋には、東京の女性落語家としては4人目の真打昇進を果たした。そんな彼女が、師匠である林家木久扇(79)と入門当時のことを語り合った。
木久扇「最初に訪ねてきたの、あれは春だっけ?」
きく姫「4月ですね。師匠の事務所に行って、玄関のチャイムを鳴らしたら、扉の向こうから『いませんよ〜、いませんよ〜』って師匠の声が聞こえたんです」
木久扇「ふつうは『落語が面白いから』とかが入門理由なんだけど、アナタは違うんだよね」
きく姫「師匠がテレビで『いやん、ばか〜ん……』とやっているのを見て、『あれ、これはジャズの“セントルイス・ブルース”じゃないか、あの曲をこんなふうに替え歌にするなんて、なんてすごい人なんだ』と感動して、『弟子入りしたい!』と思ったんです。でも師匠が落語家だという認識はなくて……」
入門後は順調に仕事が増えていったものの、男社会である落語界では戸惑うばかりだったというきく姫。根は明るい彼女も、よく落ち込んだという。
きく姫「師匠のおそばにいるだけかと思ったら、寄席で高座のお手伝いもしないといけないんです。そこにはいろんな師匠や先輩がいらして……」
木久扇「おじいさんだらけ、みんな介護しなきゃ」
きく姫「あはは。そこで師匠方の着替えを手伝ったり、お茶をいれたりするのですが、お茶はただ出すのではなく、一人ひとりに薄いお茶、ぬるいお茶、濃いお茶と好みがあって、それを全部覚えないといけない」
木久扇「相手に聞いちゃいけないの。そんなことしたら、気が利かないって言われちゃう」
きく姫「それにご挨拶しても「きく姫ちゃんはいつやめるんだい?」とか言われて、悔しくて悔しくて」
木久扇「落語の世界は新人を褒めたりしないからね。『よろしくお願いします』『そう、チビだね』とか。周りはみんな男だから、着替えのための個室もない。あれは大変だったよね」
きく姫「着替えをのぞかれたり、胸をさわられたりなんて日常茶飯事で。そのうちに長いスカートの下にステテコをはいていったりして、男の人に交ざって着替えができるようになりました。恥ずかしがるより堂々としていたほうが誰も気にしないんだってことも、そのときに学びましたね」
木久扇「当時はセクハラなんて言葉もなかったし」
きく姫「一人ひとりのお茶の好みを覚えて出すってことも、気持ちよく高座に上がってもらうよう気働きができるようになるためだと理解できるようになりました」
木久扇「(うなずきながら聞いている)」
きく姫「『素敵な服ですね』と褒めたら『お前は俺をバカにしているのか』と怒られてビックリしたり。目上に対して、ものを言うのは失礼なことだという考え方ゆえなのですが、こうした状況になかなか慣れず、戸惑ったり悩んだり、落ち込むことはありました。正直、やめたい、死にたいと思ったこともありました」
木久扇「きく姫は真面目な性格だからね。それに、子どものころにお母さんを亡くして、10代のときからお父さんの面倒も見ていたから、大変だったね」
きく姫「でも私が悩んでいたときも、師匠はいつも『人生なんて意外と簡単』『間違えてもいいんだよ』って明るく笑っていらしたので、とても救われていました。『私もそういうふうに軽やかに生きていきたいな』と元気をもらっていたんですよ」