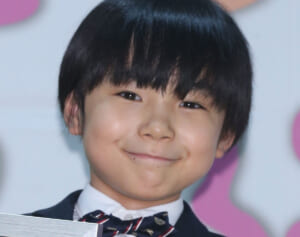「最新作の『北の桜守』の舞台は北海道。初めて高倉健さんと妻役で共演した『動乱』(’80年)でも、北海道ロケの思い出があります。サロベツ原野で、私が長襦袢一枚で雪原に倒れるシーン。昼休みには極寒に耐えられなくて、ロケバスに駆け込みました。ふと外を見ると高倉さんが一人、吹雪の中に立っていらして。二・二六事件の将校の役作りで、ご自分の気持ちを持続させるためだったんですね。この北海道での撮影の日々を通じて、高倉さんの映画作りにかけるストイックな姿勢を見せていただいたことは、その後の私の女優人生でも貴重な体験でした」
こう語るのは、現在公開中の『北の桜守』(滝田洋二郎監督)で、映画主演作が120本という節目を迎えた吉永小百合さん(73)。この作品では、『北の零年』(’05年)、『北のカナリアたち』(’12年)に続き壮大な北海道を舞台に描かれる“北の三部作”の完結編でもある。
吉永さん演じる“江蓮てつ”は、出征した夫の形見のようにして庭の桜を守っていた。太平洋戦争末期には樺太から息子と共に北海道に引き揚げる。戦後は極貧の生活を送りながらもたくましく生きていく。息子役で堺雅人、その妻に篠原涼子、夫役で阿部寛らが共演している。
「『北のカナリアたち』のときに知り合った稚内の映画館主の方より、『樺太の乙女たちの悲劇を映像に残したい』という話を聞いたことから、映画作りが動き始めました。私自身も資料を集めたりすると、女性電話交換手9人が自決する真岡郵便電信局事件など、信じられないような悲劇が多かったんです」(吉永さん・以下同)
映画の中で、てつと子どもが乗っていた設定の引揚げ船に、昭和の大横綱・大鵬の家族が乗っていて、命からがら樺太から北海道に逃げてきていた事実なども判明した。
「映画全体はもちろんフィクションなんですが、いろんな史実を取り入れて物語が作られています。戦争って、どこが勝った、負けたじゃなくて、要は人を殺すことなんだという事実を、絶対に忘れちゃいけない。映画を通じて現代の人にも、わかりやすくこうしたメッセージを伝えることは大事なことだと思います」
大好きな北海道だが、冬の厳しさは過酷。昨年2月半ばのクランクイン早々、吹雪の中、子どもたちと重さ30キロの橇(そり)を引いた。
「けっこう大変で、腰にきちゃったんです(笑)。あっ、これはいけないと思って。夏には重い米を背負って逃げたり、息子役の堺さんと海に入るという、もっとハードなシーンも控えていましたから。それで、初めてジムに通い始めたんです。ずっと続けている水泳の仲間たちが、ちょうど誘ってくれて。トレーナーの方にも付いていただいて、バーベルを使ったスクワットも頑張りました。驚いたのは、ジムに行ってみると、同世代くらいの女性たちが本当に多かったことですね」
10代にして吉永さんの映画女優としての道を決定づけた『キューポラのある街』(’62年)。若い命そのものを象徴するように、主演としてスクリーンの中を走り続けていた。吉永さんはいまも、映画に対して当時と変わらない情熱を持ち続けている。
「もう前のようには走ることはできませんけれど(笑)。現役でいるために、地味にでも努力は続けたい。ですから、この映画のキャンペーンが一段落したら、ジムには本格的に通いなおそうと考えているんです。もう少し、映画の世界で自分らしく走ってみようと思っています」