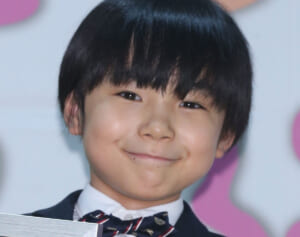「母親に認知症の兆候が表れはじめたとき、『最近、母さんおかしくない?』と先に周囲が気づいて、本人はさほど自覚なんてしていないように見えました。でも、『すぐ忘れる、バカバカバカ』と母親のメモを見つけて、“本人がいちばん傷ついているんだ”ということに気がついたんです」
そう語るのは、作家の阿川佐和子さん(64)。9月28日、小説『ことことこーこ』(KADOKAWA)が出版される。同小説は、40歳を目前に新たな仕事と親の介護を抱え、人生の岐路に立った女性・香子が、自分の道を見つけて歩み出す姿を描いた家族小説だ。
認知症でもの忘れがひどくなった母・琴子が自分のために書いていたたくさんのメモを、香子が見つける場面は、阿川さんが認知症の母親の介護をするなかで体験したことがベースになっている。
「確かに、小説の中には、実際に私が体験したことをけっこう使いました。ほかにも、主人公の香子は一度使ったラップを洗って干して、また使うシーンがあるんですが、実は私も同じことをしていまして、よく周りから『信じられない』とあきれられます……。だってコップの飲みかけのお茶を冷蔵庫に入れるために使ったラップって、そんなに汚れないじゃない。捨ててしまったら、ラップから『もうちょっと働きたい』と言われそうな気がして、レモンを包んであげたりしてるんです」(阿川さん・以下同)
香子の家族と同じように、阿川さんの両親は当初2人で暮らしていた。しかし、父親(故・弘之氏)が自宅で転んで頭を打ったり、誤嚥性肺炎を起こしたりしたため、’12年初めより入院することになる。
「私が子どもだったころから、父は『老人ホームに入れと言われたら俺は自殺する』って宣言していました。でも、父が転んで以降、高齢者2人だけの生活を続けさせるのは無理だと判断したんです。だからといって、きょうだいの誰かが親と同居するのは難しいということになりました」
入院させたものの、家に帰りたがる父親を見て、「よし、戻ろう」と何度も口から出かかったという。
「でも、そうなったら私が全部仕事を辞めなきゃいけなくなる。24時間父と母のケアをして、ご飯も作ってなんて生活ができるのだろうか?あるいは、24時間対応の看護師さんを雇うとしたらどれほどお金がかかるか……。それで父に『ごめん、ここはひとつ』と病院にいるように説得しました。すると、父は切ない表情になって『わかってる』と。かわいそうだなとは思ったけれど、おかげで仕事は続けられました」
’15年に父親が病院で最期を迎えるまで、阿川さんはきょうだいとともに両親の介護生活に奮闘した。
「とにかく人手が必要だったから、つねにきょうだいで会議をして、ケア担当のシフト表を作りました。診察に行ったとき、担当医に言われたことを、パソコンに打ち込んで情報を共有したり、もうそれは阿川家の“一大プロジェクト”でしたよ(笑)。夫も協力的で、いまでも私の仕事が遅くなったとき、母をデイサービスに迎えに行ってくれたり、母の食事も、近くの料理屋さんに連れていって、2人で食べてくれることもあります」
サポートがあったとはいえ、阿川さんへの負担は大きかった。しかも、体調は万全ではなかった。
「昨年くらいまでは、更年期障害に悩んでいましたね。ちょっと前髪が顔にかかるだけで、『ああうるさい!』とイライラしたりするんですよ。真夏は、腕が太いからノースリーブは着ないことにしていたんですが、気取ったこと言っている余裕もなくなって。とにかく暑いんですよ。更年期障害って」
そこで阿川さんは、イライラを軽減させる方法を考えた。
「一つずつ、小さなイライラを取り除くということから始めてみました。たとえば、原稿の締切りが明日にまで迫っていたら、『ごめんなさい今週は無理かもしれない』とお願いしてみる。『じゃあ来週の金曜日で』と言ってもらえたら『やった!』って一つ軽減するでしょ。前髪を短く切り、ノースリーブを着る。『醜い腕をさらすことになるが、みんな許せ!』と宣言すれば、また一つ楽になれる!」
(取材:インタビューマン山下)