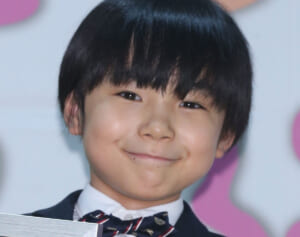「立て板に水だった父が言葉に詰まるようになって……。すぐに長年交流のある主治医の鎌田實先生に電話したら、神経内科医の先生を紹介していただき、パーキンソン症候群の可能性を告げられました。ただ、担当医の先生からは『永さん、とにかく仕事は続けましょう』と言われたんです」
こう語るのは、映画エッセイストの永千絵さん(59)。千絵さんは昭和を代表するマルチタレント・永六輔さんの長女。約10年にわたる笑いと涙の介護の日々を『父「永六輔」を看取る』(宝島社)にもつづっている。妹はフリーアナウンサー・永麻理さん(57)だ。
病気の前兆が表れたのは’08年。千絵さんは、ラジオから流れてくる父のトークに異変を感じたという。薬が効いてパーキンソン病は小康状態になったものの、’09年には前立腺がんのマーカーPSA値が高いことが判明する。再び主治医の鎌田医師に連絡し、3カ月に1度、治療のために茨城県つくば市に通うこととなった。
さらに’11年、六輔さんは自宅で転倒し、大腿骨頸部骨折となり2カ月の入院を余儀なくされる。このときは手術の翌日にラジオの生放送があって、慌てたという。
「『一度も休んだことがないから休みたくない』という父の気持ちをくんで、電話で出演させていただいたり、その後も、ベッドの上で収録したりしてなんとか乗り切ることができました」
そして退院後は、千絵さんの夫・良明さん、妹の麻理さんとの3交代制で実家に通うように。’02年に母・昌子さんが逝去して以来、六輔さんは一人暮らしをしていた。
「夫は父とは血がつながっていないことで、ほどよい距離感をとれるし力仕事も頼める。車いすを使い勝手よく改造してくれたり、男手があることは心強かったです」
六輔さんのマネージャーでもあった良明さんは、車いすを押して現場へ。仕事場でのサポートは、良明さんの担当だった。
「私は“父・永孝雄(本名)”をサポートするという分業でした」
私生活の面では、以前から親交のあった女性がケアマネジャーだったことから一任し、自宅ではヘルパーさんも頼み、万全の態勢を整えた。そのため千絵さんも、映画エッセイストとしての執筆を続けることができた。全員が生活のすべてを介護に費やすことなく、少しずつ手抜きができる状態をつくる。そんな理想的な“チームワーク介護”を、一家で力を合わせて実践した。
そして’15年、六輔さんは82歳にして最後となる冠番組『六輔七転八倒九十分』を始める。このころ、安心して仕事ができるよう「紙パンツ」の着用をすすめた際、着用するか否かで議論にもなった。
「『僕が紙パンツをはいたらあなたは安心なの?』と聞かれたので、『そうだね。安心だね。でもきっと孝雄くんも安心できるよ』というやりとりがありました。信頼する鎌田先生が『僕もはいています』とあっさりとおっしゃったので、私たちも『イザとなったら試してみても』と、気が楽になりました」
’16年の年明けは、家族全員で迎えられたものの、1月末からPSAの数値が上がり、入院。病院嫌いの六輔さんは3カ月で退院し、自宅介護の日々が始まった。
千絵さんが週に4日泊まり、ほかの日は麻理さんと良明さん、さらに在宅医も定期的に来訪。泊まりのヘルパーさんも週一でお願いするという介護生活のなか、6月末、冠番組はついに終わりを迎えた。そして7月7日、六輔さんは83歳で逝去。その前夜は、リビングで千絵さんと麻理さんと3人でのひと時を過ごし、六輔さんは好きなアイスキャンデーも口にした。まだまだ頑張れそうだと希望の持てた夜でもあったという。
「母も息を引き取った、同じリビングで。私より一歩遅れて入ってきた次男が声を上げて泣いていました。『こんなに泣いてくれるなんて』と感動したくらいで、私としては急なことで、あっけにとられていたという状態です。本当に寂しい気持ちになるのは、1年、2年たったころからでした」
いまでも家族で集まって六輔さんの話をするときは、笑いが絶えないという。
「こうして笑いながら話せることが父の目指した大往生だった――いまはそう思えるんです」