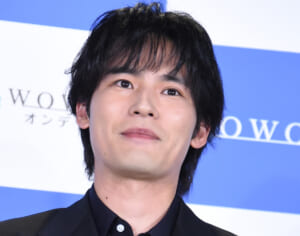「(自身の人さし指で肺を指しながら)時々ここで暴れたがるがんは駄々っ子にしか思えない。表現者は会話人間ですから、僕の体にすみついた以上、“俺の命がある限りは飼ってやるから、いい子にしてろよ”と、いつも話しかけています。がんとは共存共生。“オマエも長生きしたければ、俺に優しくしろよ。俺が死んだらオマエも死ぬんだからな”って(笑)。今はちゃんと言うことを聞いてくれていますよ」
’16年8月、肺がんステージ4、余命3カ月という宣告を受けた映画作家・大林宣彦監督(80)。その後2年4カ月が経過した今も、新作映画『海辺の映画館-キネマの玉手箱-』(’19年秋公開予定)の編集作業を毎日続けるなど、その精力的な活動は健在だ。
がんと共存して、改めて考えたことがあると監督はいう。
「地球からしたら、戦争をやめられない人間こそが、がんだっていうことですよ。勝つためだけに国に殺され、たくさんの人々が不幸になる。僕はたとえ餓死してでも“戦争は嫌だ!”と言う、子どものころに体験した戦争の理不尽さを後世に伝え残す。その思いだけで、妻と共に映画を撮っている」(大林監督・以下同)
だが、監督は映画で表現をするということは、実は怖いことでもあると話す。作品には理解より誤解がつきものだと、こう語る。
「芸術は個人の主観。その時代の傾向やトレンドなどにも大きく左右されます。そんな当てにならないデータが評価されていくわけだから、やはり怖いですよ。今度の新作も戦争中の映画。現代の若者たちが幕末日本や第二次世界大戦中の中国戦線、原爆投下直前の広島にタイムスリップします。現象だけを見ると、戦意高揚の映画に思われるかもしれない。勝って喜んでいるシーンもある。自分でも笑えない幕間喜劇という難しい作品に手を出したな、と思っています」
今年の7~8月の猛暑の中、新作映画のメインロケが、20年ぶりに大林監督の故郷、広島県尾道市で行われた。
「体力がなくなりましたね~。胸から上は元気なんだけど、映画は足で作るものだと、つくづく実感しましたよ。20年ぶりの尾道は、だいぶ変わっていましたね。昔は高齢者が多かったけど、今は空き家が再生されたり、若い人たちが移住していて、廃虚になっていた家がカフェになっていたりも。若者は古いもの、不便なものを愛する力がありますね」
尾道ロケには、全国各地から多くのエキストラが参加。7月上旬の西日本豪雨では、尾道市も一時断水。撮影スケジュールの変更も余儀なくされた。
「エキストラの皆さんに助けられましたね。“昔、あの映画を見ました”“監督に感動をもらったので恩返しができました”とか、そういう声をいただくと、これは映画の力だな、と実感しました。僕の映画を見た当時の、その人たちの喜びや悲しみ、すべて含めて『映画にありがとう』という気持ちを全身に感じましたね」
現在、監督は映画の完成に向けて編集作業の真っただ中だ。
「今、(大病や事故など)何事もなければ人類は120歳まで生きられるそうです。だったらそれまでの予定を入れるのが、人間としての責務だと思っています。だから僕は、“あと30本映画を撮る”と言っているんです。未来のことはわからないけど、そのつもりでいないと生きていることにならないと思っているんです」
来年2月、日仏交流160周年の文化交流イベントで、『HOUSE/ハウス』(’77年)と『花筐』(’17年)がフランスで上映される。
「久しぶりにパリの街を妻と2人で歩きたいね」
大林監督の映画への情熱はまだまだ続く――。