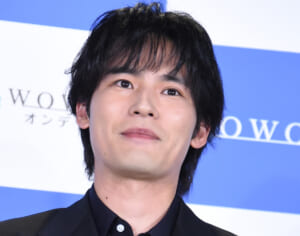「母は、この3月で98歳になります――もうすぐ白寿。ただ、いまは介護施設にいて、私が何かを囁きかけても、私のことを、息子だとわかってくれることはないんです」
こう話すのは、落語家の六代・桂文枝さん(75)。’66年に三代目・桂小文枝に入門、「桂三枝」としてデビューし、芸歴は53年目に突入している。ライフワークである「創作落語」は、現在までに290にのぼる作品を手がけてきた。
日曜昼の『新婚さんいらっしゃい!』(テレビ朝日系)ではユーモアあふれる司会として知られているが、この番組は「同一司会者によるトーク番組の最長放送」として、ギネス世界記録に認定されている。
そんな文枝さんは、’18年10月、初の自伝『風に戦いで』を出版。「母」について公で語るのは、この自伝が初めて。文枝さんがいまだからすべてを話せる、“母への思い”とは――。
「旧陸軍にいた父は持病の肺結核を悪化させていて、私が生後11カ月のときに亡くなりました。私を抱えて父の実家を出た母は、羽振りのよかった叔父の屋敷にお世話になることにしました。庭がやたら広く、玄関を出て郵便受けに行くまでがずいぶん遠かった記憶があります。戦後の焼け野原や食糧難、闇市--そういった“生きる必死さ”とは無縁な生活でしたね」
しかし5歳のとき、そんな生活が一変する。
「大阪市内の小さな製材所の3畳一間に、母子2人で暮らすように。母は、叔父の知人だった製材所の社長さんに雇ってもらい、事務作業とまかないの仕事をするようになりました」
だが数年後、製材所は材木街を襲った大火事で全焼してしまう。今度は母の兄の家に身を寄せることになった。
「おっちゃん(母の兄)の家は本当に粗末で、いわゆるバラックでした。そのころ母は、月曜日から金曜日まで料理旅館に住み込みで働き、土曜日になると帰ってくる生活でした」
当時母は30代前半。文枝さんはそのころの母をこう振り返る。
「小学生の私と2人で暮らそうと思えば、安アパートを1部屋借りて住むこともできたはずですが、母はそうしなかった。おっちゃんにわが子を預けて、“女の人生”を謳歌したい時期でもあったんでしょう。週末の夜遅くに帰ってくる母は化粧や酒のにおいがして、すごく嫌だった記憶がある。母を遠くに感じたものです。その後、母は再婚するのですが、私は最後まで猛反対しました。彼女からすれば、“母ひとり子ひとり”の人生に疲れたのかもしれませんが、当時の私には納得できませんでしたね」
そんな母が学校に来る運動会について、「この日だけはとても嫌だった」と文枝さんは吐露する。
「日ごろの母親業の後れを取り戻そうと思ったんでしょう。目いっぱいのおしゃれをして、たいそうなごちそうをお重に詰め、仕事仲間を2~3人引き連れてきて、ゴザを敷いて陣取るんです(笑)。運動音痴の私は足が遅く、徒競走はいつもビリ。それやのに、ほかの子どもより豪華な弁当が広がるのが嫌やったんです」
これまで文枝さんが明かしてこなかった母の素顔、そして親子の歴史。いま、そのことを語ろうと思った動機をこう語る。
「現代の母親は、どうも生きづらさを抱えているのではないかと映ったんです。共働きでも家計に余裕がない世帯は多いなか、虐待などの痛ましい事件も連日、報道されています。“完璧な親”を目指しすぎて、親子関係が崩壊してしまうケースもあるんやないかと。それに比べれば、母はけっこう自由に生きてきたと思うんです。母のように、『ちょっとええ加減』なくらいが『ちょうどええ加減』の子育てかもしれませんよ、と。それでも、ひとり息子はこんなに立派に育ちましたからね(笑)」