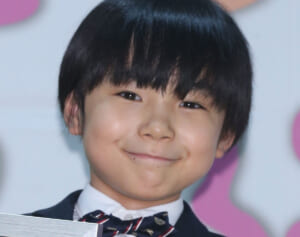阿川佐和子(65・以下、阿川)「うちはいま、認知症の母(91)をきょうだいとお手伝いの方とローテーションを組んで、在宅介護しています。その合間にショートステイで外泊サービスを利用しているんです」
ヤマザキマリ(52・以下、マリ)「私の母(86)は北海道の実家の近くに住む妹が、在宅介護をサポートしてくれていました。それが、認知症に加え、パーキンソン病も併発して……。足元がおぼつかなくなり、今年1月、部屋で倒れているところを妹に発見されて、入院しました」
阿川「高齢者専門の施設なの?」
マリ「専門ではないですが、認知症患者が多い病院なんです。我が強い母ですから、同室の人と合うわけがないと思っていたのに、4人部屋で和気藹々と過ごしています。お互い、会話はまったく成立していないんですけど、ワイワイ楽しそうでした」
小説家、エッセイストの阿川佐和子さんの母親は、昭和2年生まれで、現在は91歳。父は作家の阿川弘之さん(’15年没、享年94)。外では温厚だが、家庭内では絶対君主で、専業主婦だった母親は振り回されていたという。
漫画家のヤマザキマリさんの母親は、昭和8年生まれの86歳。北海道に渡り、札幌交響楽団のビオラ奏者として、2人の娘を女手一つで育て上げた。
親の介護が始まったのは、阿川さんが57歳、ヤマザキさんが49歳のときだった――。
マリ「佐和子さんは、どうやって親の認知症がわかったんですか?」
阿川「8~9年くらい前かな。あるとき、長年、実家で働いてくれた家政婦さんが電話で『こんなこと、私から申し上げるのも何ですが、奥さまがヘンです』って。もともとトボけてるからなあって言ったら『そういう問題じゃありません』って、ピシッと言われたんですね。それで“ついに来たか”と」
マリ「母は、80歳を過ぎたあたりから、物忘れが目立ってきたんです。でも、犬の散歩も欠かさず、毎日、元気そうでした。あるとき、北海道の実家に帰ると、母が外に立って青ざめた顔で『変な外人さんがうちに来ちゃって!』って。あわてて家に入ると、外国人が出ている料理番組が放映されていて、それを見て、うちの台所に外国人が来たのだと勘違いしたようなんです。そうした症状が増えて、ようやくレビー小体型認知症(症状の1つに幻覚がある)だと診断されました」
阿川「うちの母は、いまだに、自分でできることはいっぱいあるんです。お医者さんに行って、勝手にパソコンをのぞいたとき“アルツハイマー”という文字を見て、『誰のこと?』って聞いたりね」
マリ「本人も認知症だって認めたくないですよね。母も『一過性のもの』『疲れているだけ』と抵抗していましたから」
阿川「いままで、自分を見守ってくれていた親が、だんだん壊れていく姿は、子どもとしてもつらいもの。だから、初期のころは特に必死になるよね」
マリ「グレープフルーツの匂いが認知症に効くと聞いて、アロマを嗅がせたり(笑)」
阿川「私も最初は何でも真面目に、完璧にこなそうとしていました。母は心臓病も抱えていたから“薬を必ず飲ませないと危ない”って、神経ピリピリさせてるの。だから薬袋ごと、どこかにしまって見つからなかったりすると、叱りつけちゃうんですよ。『どうして!』って。すると母も泣きだしちゃったり。マリちゃんも、やりすぎたことってない?」
マリ「ありました。北海道に帰ると“わー”っていろいろ言ってしまうから、そばで介護してくれている妹から『お姉さんが来ると、お母さんがビクビクする』って言われました。こうなるとお互いが疲弊しますよね」
阿川「仕事も、通わないとダメなようなものは辞めて、ある程度自分のペースでできる原稿の仕事しかできないかなって、ほんの一瞬だけ考えました」
マリ「1対1になると、周りが見えなくなってきますよね」
阿川「そんなとき、昔なじみの友人と会う機会があって、彼女たちに救われました。『アガワさ、介護は1~2年でなんとかなると思ってるでしょ。10年かかるかもしれないんだよ』って言われて。“え! 10年、冗談じゃない”って」
マリ「今から必死になっても、そんな長期戦、戦い続けることはできないですよね」
阿川「10年ですまないかもしれないし。だからできる限り、手を抜けるところは抜いて、自分1人で背負わない。これを聞いて、すごく心が楽になって。友人との井戸端会議もバカにならない」
マリ「夫の実家のあるイタリアでは、みんな井戸端会議好き。普通に高齢のおばあちゃんを車いすに乗せて連れていったり。それは当たり前に受け入れられ、『シニョーラ(おばさま)、元気そうで』って歓迎されます」
阿川「そうやって、介護する側、される側も外につながることって大事。この間、取材である主婦の方の質問を受けたんです。『お姑さんの介護が始まったので、週に1回の習い事をやめたほうがいいでしょうか』って。周りの家族は“習い事なんてやってる場合じゃないだろう”という空気になるかもしれませんが、私は『やめちゃいかん』という答え。私だって、母を置いて、好きなゴルフをやることもありますが、“悪かったな”という後ろめたさを持っていると、次に“ようし、やってあげようじゃないの”とやさしくなれるもの」
マリ「そうね、滅私奉公はいけないと思う。北海道で母をそばで見てくれる妹も、一時期、介護でいっぱいいっぱいになって。髪はボサボサだしストレスで太ってしまって。“やばい”と思って『もういいよ、お母さんのことはいいから出かけておいでよ』と、コンサートのチケットを買って送ったりしました」
阿川「自分にとって、リフレッシュできるものを最低1つ持っていないと、逃げ場がなくなります。逆に自分のためだけの時間を持つことで、介護をするエネルギーが湧いてくるものですよ」
現在でも、認知症の症状は少しずつ進んできているが、母たちは平和で穏やかな日々を過ごしている。
マリ「最近は、イケメンの青年介護士さんに『リョウコさん』と下の名前で呼んでもらって、ポッと頬を赤らめています」
阿川「認知症になると、女がよみがえってくる説もありますよね。フェロモンって大事」
マリ「入居者が集うホールでダンディな男性がいたら、『あそこにすごく寡黙で、ハンサムな人がいるんだけど』って。いまでは私と女友達のような会話もしています」
阿川「私も母が認知症になったばかりのころは、お風呂に一緒に入ったりしていましたから。すっぽんぽんになって、何十年ぶりかしらね。1回、お風呂で倒れて以来、1人では入れられなくなって」
マリ「1人でのお風呂は怖いです。うちは3回、救急車を呼んでいます」
阿川「一緒にお風呂に入ると『あんた随分おなか出てるわね』っておなかを突かれたり、こっちも突き返して『イヤン』と言われたり。そんなことをしながら、全身チェックもできるんです。湿疹を見つけて『かゆい、かゆい』と言っているのはこれが原因か、とか、巻き爪が痛そうだなとか」
マリ「監視されるよりも、一緒にお風呂に入ったほうが母も安心しますよね。私も、今年の冬、母と妹と一緒に、温泉に行ったんです」
阿川「あら、えらい」
マリ「貸し切りのお風呂に入れて、みんなですっぽんぽんの状態になって。そのとき、また一段と心を許してくれたというか、恥ずかしがらなくなりました」
阿川「甲冑を脱いでくださったのね。一緒にお風呂に入るのは、母と娘だからできること。一方で、最近では、認知症が進んで、だんだん、私のことを、母の姉だと勘違いするようになりました。『誰だかわかる?』って、指を私のほうに向けると、指先にある鼻を見て『お鼻ちゃん』と言ってみたり。そういう知恵の回り方がすごいんだけど」
マリ「私も、名前を忘れかけられています。マリじゃなくて、『娘』って言われることも」
阿川「『さ』がつくでしょって、ヒントを出しても、ウフッと笑ってごまかしたり。でも娘ってわかるから『娘子ちゃん』と言ってみたり。深刻になることも多いけど、そのあと必ず笑いがあるんです」
マリ「介護を通して、親子の距離がぐっと近くなった、新しい母娘関係を築けているような気がしますね」