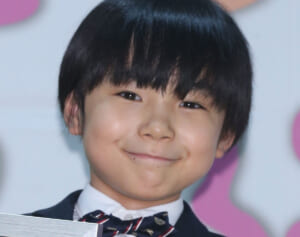灼熱の爆風に体を焼かれ、がれきの下敷きとなって息絶えていった子どもたち。短い人生の最後、子どもらが残した思いの丈を、女優たちはその身に引き受けるように、静かに語り、ときには呻きまた、ときには叫ぶ。短くも重たい惜別の言葉の数々が、言霊となって見る者の胸に迫る――。
6月24日の東京・日本橋劇場。朗読劇『夏の雲は忘れない ヒロシマ・ナガサキ一九四五年』が今年も幕を開けた。
朗読劇の端緒は1985年、戦後40年という節目の年のこと。演出家の木村光一さんが設立した「演劇制作体・地人会」が上演した『この子たちの夏 1945・ヒロシマ ナガサキ』だった。以来、34年間にわたって、戦前生まれの女優たちが、被曝した母子の手記を朗読する形で公演は続いてきた。なかでも、初演からずっとこの舞台に立ち続けたのが、一人芝居『化粧』をはじめ、数多の映画、ドラマ、舞台で活躍してきた女優・渡辺美佐子さん(86)だ。
「毎年、夏はこの舞台のためにスケジュールを空けてきました。最初から、これはずっと続けていくと、心に決めていましたから」
そして現在、全国で順次公開中の映画『誰がために憲法はある』では、朗読劇の舞台裏や、女優たちの舞台にかけるいちずな思いが紹介されている。さらに、渡辺さんは映画の中で、擬人化された日本国憲法「憲法くん」も演じる。
「女優生活も長いので。これまで、いろんな興味深い役を演じてきましたけれど、まさか日本国憲法を演じる作品に出合えるなんてね」
渡辺さんはこう言って愉快そうに笑うが、朗読劇、そして憲法くんに通底するのは、彼女の平和を求める切なる思いだ。
“初演”から34年の長きにわたって続いてきた朗読劇。日本橋劇場では、女優たちの熱のこもった朗読に圧倒されたのだろう。客席のあちこちから鼻をすする音が漏れ聞こえてきた。終演後、客席が明るくなると、目頭を押さえる人や、ぼうぜんとして立ち上がることができない人も少なくない。
「私たちも、最初の公演の稽古では、みんな泣いちゃって大変でした。涙で台本が読めず、稽古にならないの。自分で読んでいても、ほかの人が読むのを聞いていても泣けてきてしまってね。木村さんから怒られましたよ。『読み手が泣いて、どうするんだ!』って。だから、いまも必死になって、涙をこらえて読んでいます」
朗読劇は被爆地である広島、長崎でも上演された。
「私、ふだんは舞台でもなんでも、緊張して足が震えるなんてことないんです。でも、広島と長崎で朗読劇を初めてやったときは、怖くて怖くて、ガタガタと震えました」
ベテラン女優をそこまで追い詰めたものはなんだったのか。
「申し訳ないというのか……とても複雑な気持ちでした。現実に原爆の被害にあわれた方、悲惨な体験をされた方たちの前で、これから私たちがしようとしてることって、いったいなんなんだろう、という思いがありましたね。本当につらい思いをされた人たちの、またそのつらさを呼び覚ますようなまねをしてもいいんだろうかって」
上演後、恐れていたようなクレームは一切、なかった。それどころか後日、こんな話を伝え聞いた。
「当時の広島や長崎では、被曝したことを隠している人も少なくなかったんです。自分のことより、子や孫の就職や結婚に支障が出ることを心配して、多くの人が口をつぐんでいた。ところが、私たちの劇を見てくださったある女性が『あの日のことを体験した自分たちが、知っていることを伝えなければ』と、勇気を振り絞って語り部になってくれた。それは本当にうれしかったですね」
’07年、朗読劇を主催した地人会が活動を停止。23年続けてきた朗読劇も幕を閉じるかに思われた。
「それを木村さんから伝えられたとき、私たち女優の中に『続けたい、続けなきゃいけない』っていう思いがあったんですね。それで、皆でいくばくかのお金を出し合って、女優18人で『夏の会』というのを立ち上げたんです」
朗読劇の継続はかなったが、そこは全員が表舞台の人間だ。裏方の事務仕事や宣伝、会場の手配など、慣れないことばかりで手を焼いた。渡辺さんは「苦労したけど、続けてきてよかった」と話す。
「新たな語り部の方が生まれたこともうれしかったですし、各地の学校で上演したことで、子どもたちが原爆のこと、戦争のことを『普通の生活が奪われてしまうことなんだ』とわかってくれたこともうれしい。朗読劇との出合いが将来、彼らが『戦争は嫌です!』というための原動力に、きっとなってくれると思うんです」
じつは、渡辺さんたちの朗読劇は、今年が最後の夏になる。
「女優18人で始めた夏の会も、11年続けていく間に、亡くなった方がいて、病気療養中の方がいて……気付けば11人になってしまいました。私も立派な後期高齢者ですし、そろそろ皆、体力的に限界なんです」
若い世代の演劇人たちに、あとを継いでほしいとは思っていない。渡辺さんは笑顔でこう続けた。
「同じことを続ける必要はないと思うんです。若い人たちが、若い人たちなりの感性で新しいものを作ってもらえたら。私たちのまいた種が、新しい実を結んでくれたらいいなと思います」