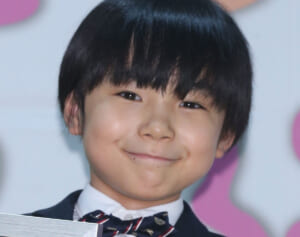このひと存在感あるね~、そのうちメジャーになるよ……で、なんていう役者さん? 強い独創性が伝う眼差しと佇まいは一見すれば忘れない、でも顔と名前が一致しない。そんな俳優がブレイクし“時の人”と化すに及んで「ああ、やっぱり」と合点するもの。
内田慈――「うちだ・ちか」と読む37歳、この機会にご記憶のほどを――。
’20年は、総合視聴率で過去最高の記録を打ち立てたテレビドラマ『半沢直樹』、波瑠(29)と松山ケンイチ(35)が主演した映画『ホテルローヤル』と、いずれも話題を呼んだ映像作品で存在を示した、舞台演劇出身の実力派俳優である。いや、これまでにも数々の注目作品に出演してきている彼女は、すでに映画界でも並み居る名監督をして「この人で撮ってみたい」と思わしめる存在であった。
ヒロインに抜擢された10年『ロストパラダイス・イン・トーキョー』では白石和彌監督、11年の『恋の罪』などで園子温監督、14年、『きみはいい子』で呉三保監督、そして、16年の『下衆の愛』などでは内田英治監督と、いずれもいまをときめくトップクラスの監督作品で、強烈な印象を残してきた。そんな彼女の待望の主演映画『レディ・トゥ・レディ』(監督・脚本:藤澤浩和)が、12月11日より公開される。
内田が演じたのは、アラフォーの“売れない女優”一華だが、なんでもこの役には自身の若手時代がダブッてみえたのだと振り返る。
「役者の仕事に恵まれず、アルバイトなどで家計をやりくりしている女性が、30代後半になる一華。家電量販店の売り子のシーンなんかは、バイトと稽古でクタクタだった頃の経験が生きましたね……」
聞けば、神奈川から上京して一人暮らしを始めた駆け出しのころは、阿佐ヶ谷の“家賃2万5千円、四畳半、風呂なし”アパートに住んでバイトに明け暮れる日々だったという。
いま30代の彼女だから、もちろん「平成」に入ってからのオハナシだ。そんな世界に「自ら飛び込んだ」というユニークな半生を、じっくりと振り返ってもらった。
■
「けっこう教育熱心で、厳格な両親のもとで育ったんです。父(78歳)が自営の学習塾をしていて、母(74歳)は専業主婦、子どもは三姉妹で、私はそのいちばん下でした。小学生のころまでは、まだ第二次ベビーブームで塾の生徒さんも多かったのですが、中学、高校になるころには少子化の影響が出て……母も働きに出始めていました。
最初に『お芝居』というものに興味が向いたのは、高校3年の夏休みのことでした。そのころは、フツーに大学受験するつもりでいたんですが、いろんな不安や不満もありながら、『なんだかワクワクしないな~』という、煮え切らないような、なにか持て余すようなものがあったんでしょうか……。
そんなとき『大人計画』の松尾スズキさん(57)がテレビに出ていらして、『こんなに面白い、ヘンな人がいるんだ!』とクギ付けになっていると、最後に『好きな言葉は?』と聞かれて、松尾さんは、『平等って言葉ですね、だってありえないじゃないですか』とおっしゃった。
私は、あんまり友達もいなくて、青春を謳歌しているタイプでもなかったんですが、いわゆる『きれいごと』が引っかかる時期でした。そんな時期に“ありえない返答”をするアイロニーのセンスが、当時の私にピタッときたんですね。『いずれ、この人がいる世界に行きたい』と」
映画・演劇をはじめ、あらゆる芸術の登竜門とも言われる日本大学芸術学部の門を叩いたのは、01年のこと。
「横浜市の自宅から“通い”でした。私は文芸学科で、1年生から10人くらいのグループでゼミ誌をつくります。小説家希望、記者希望といろいろあるなかで、私は『漫画』を選んでいたんですね。筆ペンを使って書くような、柔らかなタッチの絵を描いていました。テレビドラマ『ハロー張りネズミ』(17年)では、実際に漫画家役を演じたので、そこでの経験が生きました(笑)。それから、演劇学科の演技コースに潜ってもいました」
しかし、大学は半年で中退している。
「いろんなことがかみ合わない時期で……。芝居をすることにも、親は大反対でした。それで家出同然に実家を出て、芝居を始めた。劇団などに所属はせず、勝手にやることになったんです」
舞台俳優を目指す人は、昔もいまも、どこかの劇団で研究生として始めるか、プロダクションなどに所属してオーディションを受けていく、などのパターンがほとんどだろう。
しかし内田には、所属する劇団も、事務所もない。もちろん、大学の演劇サークル引き受けでもない、まったくフリーでのスタートだったという。
「初舞台は『ラフカット2002』という“若手の登竜門”という位置づけのお芝居で、19歳でした。未経験OKでしたので、そのオーディションで受かって。風俗嬢の役を演じました」
生活も当時は“極貧”そのもの。
「そのころは阿佐ヶ谷に住んでいました。寺山修司さん(享年47)、爆笑問題の太田光さん(55)など、阿佐ヶ谷と縁のある方が好きだった影響ですね。四畳半の風呂なし、2万5千円のアパートです。銭湯代を浮かせようとして、深夜1時半になると、閉店の2時までのラスト30分が『100円引き』でしたので、最終電車で阿佐ヶ谷駅に着いても直で行かずに一度、家に帰って洗面道具をもっていくのがタイミング的にちょうどよかった。でも、バイトか稽古でヘトヘトになって家に帰っているので、そのまま寝ちゃって、よく入りそびれていましたね。翌朝、水道で頭を洗っていたんです(笑)」
同世代の「ひとり暮らし女性」の多くは「ワンルームマンション、オートロック」を望み、インターネットもすでに普及、セキュリティ意識が急速に浸透した時期に、昭和然としたアナログ暮らしをしていたことになる。
「珍しいですかね……。網戸もなくて、開けっ放しでいたんですが……夜中に『なんか痒い!』と思って足をみたら、ゴキブリが這っていたり(笑)。『ここまでの経験したことないだろう』というようなね。そんな生活に憧れがあったのかもしれないですね」
アルバイトも多種に及んだ。
「特別にいまに生かされた経験はないんですけど、経験としては面白かったですね。長かったのは、雀荘の運び。ほかには、パン工場の作業員、コールセンター……『俳優あるある』ではないんですが、スケジュールが不規則で、シフトが組みづらいので飲食店だと難しかったんです。店頭の売り子は、パンをスーパーでセールする人。『5コ、250円です!』とか言って(笑)。それから、結婚式場のバイトもしました。模擬結婚式のモデルですね」
演劇の世界を目指すきっかけとなった『大人計画』のオーディションも、このころ受けているというが、花開くのはまだまだ先。しかし、このユニークな生活が、内田の女優人生を形作ったことは間違いない。
(取材・文:鈴木利宗)
【INFORMATION】
映画『レディ・トゥ・レディ』(監督・脚本:藤澤浩和/主演:内田慈、大塚千弘)12月11日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開