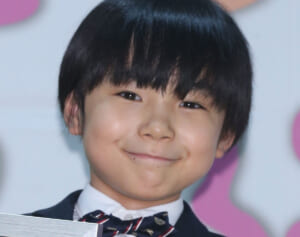住んでいた場所は違っても、年齢が近ければ「そうそう! わかる」って盛り上がれるのが、青春時代におなかがよじれたお笑い番組の話。各界で活躍する同世代の女性と一緒に、“あのころ”を振り返ってみましょうーー。
「中学では器械体操部に入って、一生懸命、練習に取り組んでいたから、テレビを見る時間はものすごく限られていて……。土曜まで頑張って、くったくたに疲れて、それでようやく好きなテレビにたどりつけるんですね。それが『オレたちひょうきん族』(’81〜’89年・フジテレビ系)でした。ホント、楽しい時間なんですが、日曜の朝からまた厳しい部活が始まるので、エンディングでEPOさんの『DOWN TOWN』が流れると“ああ、休みが終わっちゃう”と、ちょっとした絶望を感じたりしていました」
歌手、女優など幅広く活躍する濱田マリさん(52)は、関西出身ということもあり、小学校時代からお笑い番組は大好きだった。’80年、濱田さんが小6のときに漫才ブームがやってきた。その中心にいたお笑い芸人が集結して、’81年にスタートしたのが『オレたちひょうきん族』だ。
お気に入りのコーナー、キャラを数え上げたらキリがないが、とくに印象に残っているのが『ひょうきんベストテン』に登場した「うなずきトリオ」だ。
「漫才ではツッコミを担当する、ビートきよしさん、松本竜介さん、島田洋八さんのユニット。ふだんはボケの“引立て役”の3人が“主役”となって歌う『うなずきマーチ』が衝撃的で。曲も面白いだけじゃなく、とってもキャッチーでオシャレ。それもそのはずで、後で調べてみたら、作詞・作曲はあの大瀧詠一さんなんですよね」
ほかにも明石家さんまの『アミダばばあの唄』は桑田佳祐が作詞・作曲、安岡力也扮する「ホタテマン」が歌う『ホタテのロックン・ロール』には内田裕也が作詞に参加するなど、『ひょうきん族』から生まれた曲には、当時すでに一流といわれていたミュージシャンが制作にかかわっている。
「ふざけているようで、しっかり作り込まれているから、番組全体のクオリティがめちゃめちゃ高い。“面白いことを、ド真面目にやる”ことのスゴさ、大切さは『ひょうきん族』から教わりました」
そう感じたのは、器械体操部を高1でやめ、夢中になれるものを失ったからかもしれない。
「技ができたときはうれしいけど、最初に挑戦するときは怖いし、練習もキツい。しかも強豪校でかなり真剣にやっていたから、後輩に追い越されたりすると、プライドがボロボロになる。楽しいことより、つらいことのほうが多かったんです」
両親から「体操をやめて何をするんだ」と言われるたび、“私に何が残っているんだろう”と悩み、誇れる“何か”を探した。
「そんなとき、部活を続けていたら出合わなかった、ちょっと不良の友人に、『難波ベアーズ』や『十三ファンダンゴ』といったライブハウスに連れていってもらったんです。常連のお兄さんやお姉さんにいろんな音楽を教わったり、ステージに上がらせてもらったりもしました」
音楽の道に入り、結成したバンド「砂場」は『三宅裕司のいかすバンド天国』(通称・イカ天、’89〜90年・TBS系)にも出場。
「私たちの音楽はとんがっていましたが、ついでに態度もとんがっていて、審査員のみなさんから酷評されました(笑)。でもなぜか、ベストボーカリスト賞をもらうことができて。トロフィを神戸まで大事に持ち帰りました」
同じころ、ショートコントなどを取り入れたエンターテインメントバンド「モダンチョキチョキズ」にゲスト参加し、『新・オバケのQ太郎』をカバーした。
「面白くて楽しい曲ですが、メンバーはすでにプロとして活動していた人ばかりで、演奏のクオリティが抜群に高いんです。そこがスゴかった! 自分で言っちゃってますけど(笑)」
“面白いことを、ド真面目にやる”ーー『ひょうきん族』にも通じるギャップがレコード会社の目に留まり、’92年にメジャーデビュー。現在の女優業にもつながる人生の転機を迎えたのだった。
「たけしさんやさんまさんとお仕事でご一緒する機会にも恵まれ、すごい幸せなことをやらかしていると思うんです。さすがに声をかけるのも恐れ多くて“『ひょうきん族』のファンでした”なんて言えませんけど。でも、私のセンスや仕事へのスタンスは、10代のころに『ひょうきん族』から教わり、磨かれたんです!……って、そう思っていいですか? ずうずうしいかな? それほど大好きな番組です」
「女性自身」2021年3月16日号 掲載