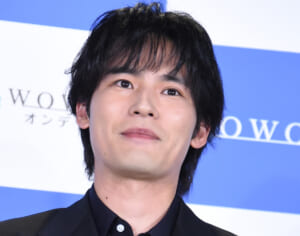■親しい人の死を悲しむ日を卒業し、前を向くことがいちばんの供養
生島さんが故郷・気仙沼を訪れることができたのは、震災から1カ月ほどがたってのことだった。漁業が盛んで海の恩恵を受けて発展してきた町は、同じ海からの脅威の前に壊滅していた。
「町並みが、変わり果ててしまってました。僕のなかの気仙沼は、空も海も真っ青、そんなイメージが強いんです。でも、その日は曇り空で、海もどす黒く沈んだ色をしていて。町じゅうがぬかるんでいて、それに臭いが強烈でした。打ち上げられた魚が腐敗した臭いと、油の臭いが混じったような……、あの臭いはこの先も、一生忘れられないと思います」
生島さんが故郷の惨状を初めて目の当たりにした4月初旬。そこには震災から1カ月ぶりに、ようやく帰宅が許された人たちがいた。気仙沼市役所に勤めていた、生島さん旧知の2人。小中高と同級生だった廣野純朗さん(70)と、いとこの佐藤健一さん(67)だ。
彼らが1カ月も帰宅できなかったのは重責を担っていたから。廣野さんは会計課、佐藤さんは危機管理課、それぞれの責任者だった。
震災後、行方不明の妹夫妻の情報を得るため、生島さんが頼ったのが佐藤さんだった。
「警察から入る亡くなった人、行方不明者の名簿、それに、避難所に寝泊まりしている人たちの名簿を夜中、手が空いたところでくまなくチェックしたんですが……。当時、パソコンも通信機器も使えないなかで、本当に残念ですが喜代美ちゃんの情報を見つけることはできませんでした」
一方、混乱のただ中にあった市役所で、お金の管理を任されていたのが廣野さんだ。被災し稼働できなくなった金融機関の再開にも奔走した。また、支援金や義援金の窓口も。後日、生島さんが東京で集めた義援金の管理も任された。
「私は会計課にいたので、生島も『あいつなら金のことも大丈夫だろう』と思ったんでしょうね」
2人には、震災直後に脳裏に刻まれた、生々しい記憶がある。廣野さんのそれは、ある音だった。
「潰れ、水につかった車のクラクションが、あちこちで突然鳴るんです。市役所が静まり返った夜中になると、よく聞こえてきて。まるで断末魔の叫びのような、それは物悲しい響きでした。あの音はいまも耳にこびりついてます」
佐藤さんは、ある光景を目にして、悔しさにかられたという。
「雪がやんだ後の、当日の夜。湾のほうにはまだ真っ赤な炎が見えるんです。でも、空を見上げると雲ひとつない夜空に星がさんぜんと輝いていて。ひどい皮肉ですよ。満天の星の下に広がっていたのは地獄絵図ですから。神様が本当にいたら、なぜこんなひどいことをするのかと、恨めしく思いました」
一方、生島さんは東京に戻って以降、仕事をまっとうすることに、より傾注していった。
「僕の役割ってなんだろう、そういつも考えてました。もう長いこと行方不明のままの肉親がいる、その悲しみを抱えながら、同じ境遇の人の痛みもわかりながら、伝えるべきことをきちっと伝える、それが放送人としての僕の務めだと、そう思うようにしていました」
それまで以上に仕事にまい進した。そして、震災から3カ月が過ぎたある日、新聞記事に目が留まった。
「それを読んで、僕はとても納得できた。その記事では、東北地方のお坊さんが『卒哭忌』という言葉を解説していたんです。卒哭忌とは百箇日法要のことで、親しい人を亡くし嘆き悲しむ日々からその日を境に卒業して、前を向き生きていきましょうということ。それが故人のいちばんの供養になる、とも書かれてました。
つらいし、決して忘れることなどできません。でも、亡くなった人のぶんまで、2倍も3倍も生きることを謳歌する、それが遺った者のすべきことと僕は思うようになりました」