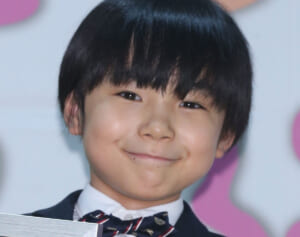〈みなさん、どうもありがとうございます。みなさん、本当にどうもありがとう。私が選んだ結論、とてもわがままな生き方だと思いながら、押し通してしまいます。8年間、一緒に歩いてきたみなさんが『幸せに』って、そう言ってくれる言葉がいちばんうれしくて。
みなさんの心を裏切らないように精いっぱいさりげなく生きていきたいと思います。いま、みなさんに『ありがとう』っていう言葉をどれだけ重ねても、私の気持ちには追いつけないと思います。本当に、私のわがままを許してくれて、ありがとう。幸せになります〉
80年10月5日に行われた「山口百恵ファイナルコンサート」で、ラストソングとなった『さよならの向う側』の前に百恵さんが語った全文だ。ときに涙も交えての感動的なトークだったが、実はすべて“アドリブ”だった。コンサートの構成を担当した演出家の宮下康仁さん(70)は、それを手に懐かしげに当時をふり返る。
「台本作りでは百恵さんと何度も打ち合わせしましたが、あの箇所には、“最後の語りを”とあるだけ。実際のところ、当日はコンサートもクライマックスを迎えるなか、込み上げてきた自分の思いを、そのまましゃべったんだと思います」
昨年10月のNHK BSプレミアムに続き、今年1月30日にNHK総合でこの引退コンサートが再放送された直後、雑誌はじめマスコミはこぞって当時の百恵さんの輝かしい活動ぶりを報じ、ツイッターでも「百恵ちゃん」がトレンドランキングを独占。
当時は“百恵”“ねえさん”と呼び合う親友として知られていた小柳ルミ子(68)も、もちろんNHKの放送を見たと話す。
「ずっと泣きながら見ていて、改めて思いました。あえて当時と同じ呼び方をさせてもらいますが、いまでも『百恵が大好き』だと!」
〈みなさん、いつかこのステージがみなさんのなかで思い出と呼べるそんなときがきたら、そっとふり返ってみてください。このほんの数時間、このなかの込められた1曲1曲の歌、みなさんの思い、私の思い、すべてを思い出してください。思い出だけは消えることなく、いつも残り、そして、いつでも蘇るものだと思います〉
まさしく今回の40年ぶりの“再会”を予言するような言葉は、26曲目の『不死鳥伝説』の前。宮下さんは「すごいよね」と驚嘆しながら三たびこう繰り返した。
「ここも、台本にはまったく書いていないわけで、まさしく彼女の言葉です」
その後、ラスト前の『歌い継がれてゆく歌のように』を、涙とともに歌い終えた百恵さんがステージから去り、再び登場したとき、会場のあちこちから、ファンの女性たちのうっとりするようなため息が洩れ聞こえた。
いよいよファイナルとなる舞台上には、ウエディングドレスを思わせる純白の衣装と同色の髪飾りを身にまとった百恵さんがいた。純白のドレスで、「幸せになります」とのラストメッセージを残した百恵さんは、全28曲を歌い終えると、白いマイクをステージ中央に置いて、人々の前から立ち去った。
野口五郎(65)は、そのシーンを鮮明に覚えていた。
「僕の隣の席は、(西城)秀樹でした。彼女がマイクを置いたとき、僕や秀樹だけでなく、アーティスト席の全員が、客席のファンの方たちより率先して、スタンディングオベーションをしたんです」
ファンの多くが、茫然としたまま観客席から立ち去れないでいるころ、バックステージでは、もう一つの別れのドラマが続いていた。最後の舞台をやり終え戻ってきた百恵さんを、アン・ルイスや岩崎宏美、阿木燿子らが迎える。
証言するのは、小柳ルミ子。
「ステージ裏では、ふだんは人前では泣かない百恵も、さすがに泣いていて。みんなでハグし合いながら、しばらく泣いていました。私は年上ですが、大きな宝物をなくしたような気持ちだったんです」
その後、武道館のレストランで、報道陣をシャットアウトした打ち上げが行われた。小柳が続ける。
「事務所は違う私ですが、百恵本人から『ねえさん、出て~』とせがまれて、参加しました。すると、あの気丈なはずの百恵が、ずっと私の手を握って離さないんです。最後の最後まで無事に終えるのを見守って、という意味だったのかもしれません。
ただ、もう百恵に涙はありません。すでに歌手・山口百恵ではなく、“奥さんになるんだ”という気持ちに切り替わっていたのでしょう。私は、この場で、友和さんに百恵のことを、『ほんとにいいコだから頼むよ』と告げたことを覚えています」
阿木燿子の音頭で乾杯を終えると、百恵さんも挨拶に立つ。
「昨日の夜はなかなか実感を持てませんでしたが、でも若さですね、今朝はすっきりした気分で朝を迎えました。今日までほんとうにありがとう。私は幸せでした」
その後も関係者やスタッフの一人ひとりに挨拶をし、感謝の思いを述べながらビールを注いでまわる姿があったという。
パーティが終わり、その日初めての安堵の表情をした百恵さんが友和の愛車で帰っていくと同時に、長かった一日が終わった。そして私たちは、彼女の残した言葉どおり、「80年10月5日」を、その名曲の数々とともに、いつまでも記憶し続けることになる――。
「女性自身」2021年3月23日・30日合併号 掲載