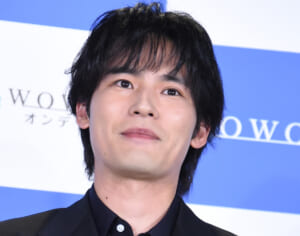■王貞治の娘として感じていた息苦しさ
一方で“王貞治の娘”として、厳しい家庭に育った息苦しさもあったという。
「『お父さんに迷惑がかかるようなことをしてはいけない』が母の口癖で、高校生になっても、友達とコンサートに行くなんて、とんでもないことでした。ただ、家に脅迫まがいの手紙が来ることもあったそうなので、娘たちを守るためという意味もあったのだと、いまとなってはわかるのですが、当時の私にはそんなことまで考えが及ばなくて」
さらに小学校から高校まで通った私立の一貫校は、お嬢さま学校として有名で、校則も厳しかった。
そんな境遇のなか、思春期を迎えた理恵さんには、自然と反抗心が芽生えてくる。
「複雑な気持ちを抱えながら過ごしていた高校生活で、いまでもよく覚えているのは、文化祭の準備に追われて、学校に遅くまで残っていたときのこと。最終下校時に放送される“追い出しソング”がなぜか、尾崎の『15の夜』(’83年)だったんです。薄暗くなった校舎で聴くと、まるで歌の世界に入ったかのような感覚になって、衝撃を受けました」
お嬢さま学校特有の雰囲気のなかで、「尾崎を聴いている」とは誰にも言えず、1人でレコードを集め、尾崎にのめり込んでいったという理恵さん。
「家にも学校にも反発する気持ちはあるけど、何にもできない自分がいて……。尾崎が歌う自由や愛や夢は、すごく共感できたんです。『ダンスホール』(’85年)という曲を聴いて“親が絶対に許してくれないダンスホールって、どんなところなんだろう? 華やかな女性がたくさんいるんだろうな”って、想像にふけったりすることもありました」
高校を卒業後は、青山学院大学に進学。
「尾崎が付属高校を中退していたので、同じ学校に通うことに、勝手に運命を感じていました」
社会に出て30年近くたった現在も、“尾崎愛”が色あせることはない。
「尾崎と出会った曲でもある『15の夜』はいまでも大好き。『僕が僕であるために』(’83年のアルバム『十七歳の地図』に収録)は私の元気ソングで、ゴルフ場に行く車の中でかけたり、モヤッとしたとき、スッキリするために聴いたりしています。尾崎の曲のように、ちっちゃなことで傷ついたり、人間関係に悩んだりしたとき、心に寄り添い、バチッとハマる音楽が、’80年代にはたくさんありましたよね」