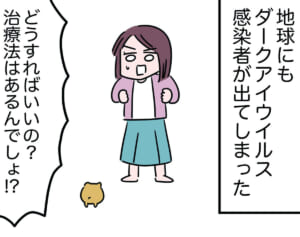<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>
「もしかすると、明美の見てきた話から思いもかけない事実が判明したかも! …でさ、今夜は皆既月食だってさ」
一通り明美の話を聞き、どうやら銀門が月か星に関わるということを知った健作は、さっそくパソコンを取り出した。開け放った窓から流れ込む冷気が肌を刺すだろうに、こちらもやはり興奮しているらしく全く頓着していない。どうやら、銀門の謎だけでは無い、なにか重要なキーワードに辿り着いたようだ。
「その謎の祈祷師の一族だけどさ、刺青をして弓を持ってるんだったよな」
「…そうよ。それがどうかした? 刺青なんて、昔の人は…呪術的な意味でもしてたんでしょ。ほら、今でも狩猟民族とかってしてたりするじゃない。それに弓ったって、私たちが知ってるようなちゃんとしたモノじゃないわよ。もっと短い、玩具みたいなヤツよ」
少年の背や集落の男たちに見た弓は、明美が学生の頃見た弓道部員の使う弓に比べて短く、ドキュメンタリー番組で紹介される未開地の狩猟民族が使う弓に似ていた。
「断定はできないけど、どうやら明美の見た少年たちは、俺たちが歴史で習った大和民族とは異なる部族のようだな」
「えっ、それってどうゆう事?」
「う~ん、難しい所は端折るナ。お義父さんの書物によれば…あ、これこれ。この本によれば、神武天皇の東征記に、神武天皇が戦った相手を“身を文けて”と記してあるんだよな。この“身を文ける”ってのは身体に刺青を施していることらしい。加えて少年や、集落の男が手にしていたという短い弓。この弓って文字に人を重ねてごらん。そして、その上に部首の一部を引けば…ほらわかっただろう? …攘夷とかに使う夷だよ。夷敵とかにも使うよな。要するに、弥生人とされている大和民族とは異なる部族を指す言葉だよ。肌に文字を描き弓を持つ人…。まさに、神武東征記に出てくる蝦夷のことじゃないか」
健作は興奮している。
「なるほどね…。だから私、彼らに奇妙な親近感を覚えたのね…。これで納得できたわ」
「…って、何が納得できたんだよ。明美の御先祖様って何人なんだよ」
「ん~面倒臭いわね。それは今はいいから、問題は銀門。そっか、銀門は月食よ。よかった! 健作、有難う! 月食かぁ…。『大地に覆い隠される』だわ。そうよ、月食よ月食のことだったんだわ」
「俺もそう思う。銀門が開く…きっと月食のことだ。でも、月食は今夜だぜ。間に合うのか? まだなにも準備できてないんだろ?」
思いがけず解けた最後の謎に上ずらせた声を背に、明美はさっきまで黒玉を握り締めていた手を開き、封印の朱に紅く染まった、気功家が労宮と呼ぶ掌の中心を見詰めている。

『命迸る掌を紅き戒めに染めし者、閉ざされし銀門の彼方に邪を封じよ』
明美の脳裏に、決して口を開くことの無い〈口の大きな男〉の言葉がこだましていた。
明美が幼い頃からずっと抱き続けた違和感。それは、日本人として生を受けたものの、亡くなった父以外の誰にも覚えることのない親近感と、自分が、皆が言う日本人とは異なる意識を内封していることだった。誰にも語らず『きっと私は、ここに居るみんなとは違う部族の裔なんだわ』と、子どもの頃からずっと思い定めて生きてきた。
食が始まるのは午後10時23分。まだ夜明け前の西の空には、食を今夜に控えた十四夜の月がうっすらと残っている。食が始まるまでに、準備を整えておかなくてはいけない。それから眠らずに話し合った二人は、母の作った朝食を食べながら朝のニュースを食い入るように見詰めていた。
『昨夜半、市内絵山町の自宅で上村静江さんの遺体が発見されました。遺書らしきものはなく、昨年夏に一人娘を事故で亡くして以来、心療内科への通院歴があり、事故と自殺の両面から捜査は続いています』
TV画面には、一昨日二人で訪ねた親子三人で暮らしていたはずの、まだ新しい小さな家が映っていた。
恐れていたこととはいえ、ここまで忠実に不幸の予感が的中するかと二人は呆然とした。そして、そんな二人の耳に、番組の最後に再び現れた陽気なキャスターの〆のコメントが虚しく響いた。
『今夜は久しぶりの皆既月食です。お天気もよく、夜になっても快晴ですから絶好の観測日よりとなるでしょう。県下全域で夜の天体ショーが楽しめるはずです』
悲しみの現場
先日訪ねた上村静江の家は、朝から大変な騒ぎになっていた。
小さな庭を備えたつましい家の周囲には、物々しく立ち入り禁止の黄色いテープが張り巡らされ、入り口近くには二人の制服警官が立っている。それを遠巻きにして野次馬が囲み、さながらそこは、TVドラマに出てくる殺害現場の趣だ。この家の主人である夫は、第一発見者でもあり事情を聴取するために警察署に連れていかれているらしい。
「自殺でしょ。旦那さんが見つけたんだって…」
「奥さん、少し変になってたから…」
「本当嫌よねぇ。なんだか自殺ばっかり続いて気持ち悪い」
口さがない野次馬の群れに身を沈め、界隈の住人たちが言い募る事故の状況に耳を傾ける。皆、勝手なことを口走りながらも、同時に周囲の話にも興味深々で耳を傾けている。少しでも話の接ぎ穂が手前に伸びてくれば、自分の話を中断してでも即座に乗り換え乗り換えして器用に物語を紡いでいく様子に改めて野次馬根性と言われるバイタリティを痛感させられる。
事件のあらましはこうだ。昨夜遅く、眠っているはずの妻が居ないことに気付いた夫が、バスルームで手首からおびただしい血を流す静江を見付けた。その後、駆け付けた救急隊によって応急処置が施されたが、すでにその時には失血死の状態で、けたたましくサイレンを鳴らしての救急搬送も無いまま警察に連絡されたという。
帰りの車中、明美はじっと外を眺めたまま口を開こうとしなかった。
「どうした? もしかして、なにか責任でも感じてるのか?」
「…嫌になっちゃうわね。…あの日彼女が言ったことは、間違ってなかったのよ。だって理沙ちゃんは、帰りたくても帰れなかったんだから…。確かに、あのお母さんには理沙ちゃんの声が届いてたのよ…」
「明美が責任を感じる必要は無いと思うぜ。こうなったのは、絶対に明美のせいではないし、明美に出来ることはやったと思う」
「…私って、一体なにをやってるのかしら…。コノ世の者には届かない声やビジョンを伝えることでなにかの役に立てればと思ってきたけど、結局のところなにも出来ないでいる。彼女だって死にたいわけじゃなかったはずよ。ただ、お譲ちゃんの死を認められなかっただけなのよ。そして、可愛い娘に一目会いたいと願っただけなのに…」
「でも、考えようによっては、これで彼女は娘さんの元に行けたんじゃないか」
「…駄目なのよ! …可哀想だけれど…」
励まそうした挙句、思いの外に強い口調で否定されてしまった健作は、そのまま何も言い返せずに黙ってしまった。
願ったわけでもなく持って生まれた能力と、それに伴う責任の重さと限界に、明美は強く打ちひしがれていた。やっと開いた口は重く、ただ最後の「駄目なのよ」の一言だけを怒ったように強い口調で言い放ち、気まずい雰囲気のまま二人は黙ってしまった。
無限の闇
50万都市とはいえ、郊外の田園地帯には刈り取られた稲穂の切り株を晒す冬枯れた景色が拡がり、車内に漂う虚しさを一層掻き立てていた。
訳も分からず流れ込んで来る他人の意識に翻弄された少女時代、明美は嫌な思いばかりした。そして咲き誇る娘の頃を迎えても、少女時代に植え付けられた他人に対する不信感は容易に拭えず、気が付くと明美はいつも一人だった。物心付く頃から、同じ年頃の子どもと遊ぶよりは一人で居るほうが好きだったし、姉妹ですらも煩わしいと感じた。なぜなら、そんな彼女たちの無邪気で無防備な心が、往々にして明美を傷付けたからだ。それでも健作というパートナーと出会い、亜里沙という分身を得たことで明美の中で何かが変わった。以来、幼い頃に見た、祖母や曾祖母がしていた霊的な存在や異世界との交信を見様見真似で始めた。特に宣伝したわけでもないが、いつしか様々な相談者が訪ね来るようになり、誰言うとも無く、そんな明美を占い師とかスピリチュアルカウンセラーと呼ぶようになっている。
正直、明美は嬉しかった。何が嬉しいかと言って、長年明美自身を苦しめてきた特異な能力で、思いがけず他人に喜んでもらえることが嬉しかったし、何より他人との交流を厭わなくなった自分自身を頼もしくすら感じた。
しかし今回の事件は、そんな生易しいものではなかった。明美は自分を頼ってきた相談者の訴えの真偽も見定められずに、察知している危機から守ることも出来なかったのだ。
そして、一人の人間がこの世から消えた。
上村静江の死は、また一つ明美に、決して癒されることの無い傷を刻みつけた。

『待って。…お願い』
車に戻ってから、ずっと黙って前方の一点を見据えたままの明美は、懸命に祖母と交信していた。最初は、亡くなった静江を探していたのだが、なかなか静江が見つからず、そうするうちに祖母が現れたのだ。
『もうお止め。…あの女は、現れはせんぞね』
『おばあちゃん、彼女はもう行ったの?』
『知らん。…自ら命を断つなど許されてはおらん』
『待って…』
すでに、そこに祖母は居ない。ただ、静江との交信が無駄であることだけを告げて閉じてしまった。
「生も死も魂ですらも、皆、転生の中にある。光の中に昇って行けりゃあええが、そこから外れるんを地獄と呼ぶんぞね」
まだ幼い頃に、祖母に聞かされた言葉を思い出した。生きている者はもちろん、死んでしまった者ですらも輪廻転生のサイクルの中にあり、何度も何度も、光の中に入って行けるよう修行を繰り返させられる。そのサイクルから外れてしまうことは、〈地獄〉と呼ばれる無限の闇に陥ることだという教えだ。
明美にとっては当たり前の法則だったが、それでも、娘を探し求める母の姿を、あの日リーディングに現れた静江の悲痛な叫びを消し去ることはできなかった。
「きっと今頃は再会できてるわ。でなきゃ可哀想過ぎるもの」
「…そうだよな。…そのために死を選んだんだからな」
明美は嘘を口にした。すがるような思いで祖母と交信してまで確認したこととは真逆の言葉を口にしていた。
輪廻転生の理はおろか祖母の教えも知らない健作だが、明美の言葉が単なる慰めでしかないことはわかった。それでも、自分たちの無力を許されるよう祈りながら頷き返していた。明美は、そんな健作を見ようともせず、紅く染まった両の掌を凝っと見詰めた。
愛娘の不慮の死を悼む若き母親が、まるで後を追うように自らも死を選んだ。余りにも悲しい出来事だったが、それでもまだ一連の事件が決着したわけではない。それどころか、人を自死に誘う禍々しき波動は、いよいよその姿を現して明美たち夫婦に迫って来ている。隣で紅く染まった掌を見詰める明美の様子に、健作は並々ならぬ決意を感じていた。
覚醒
家に戻ると、明美は何も言わずに座敷に籠もった。何をすればいいかもわからない健作は、それでもパソコンを開いて月食の観測予想を調べている。時々、気になって座敷の外まで行ってみるのだが、なんとなく襖を開いてはいけないような雰囲気が漂っていて同じところを行きつ戻りつしていた。
どれほどの時間が経っただろう…。祖母と曾祖母が長年祈りを捧げた神棚の前で、明美は瞑目したまま身じろぎもせず座り続けていた。
やがて静かに目を開いたかと思うと、顔の前で合わせた両掌にフッと勢いよく息を吹き込むと二度柏手を打つ。そして紅く染まった右の掌を、正座した右膝に指を揃えて開いて載せ、同じく紅く染まった左手で握りこぶしを作ったかと思うと、左側に置かれた黒玉の上でゆっくりと円を描き始めた。すると黒玉は何度か明滅を繰り返し、やがて「ブンッ」と下腹に響く鈍い音をさせて細かく振動を始めた。

見る者が見れば、黒玉が「ブンッ」と音を鳴らして振動を始めると同時に明美の身体が淡いオレンジ色に輝きながら震えていたのが見えたに違いない。
そんな明美が端坐する座敷には、鼻腔をくすぐる金臭い匂いが漂っている。
いかにして手に入れたのか、明美はついに黒玉を秘具とする術を習得していた。
閉じられた襖が開くのにどれ程の時間が経っただろうか。足の早い初冬の夕陽が西の山端に傾きかけた頃。ようやく姿を現した明美は、廊下を行きつ戻りつしていた健作とぶつかりそうになった。
「やっとお出ましか。そろそろ動き出した方がいいんじゃないか? 月食が始まるのは10時前だから、まだ時間はあるけどな…」
健作は、なかなか姿を現さない明美に内心やきもきしながらも、咄嗟に調べるだけ調べた皆既月食のタイムテーブルを口にした。そんな気持ちを知ってか知らずか、まるで見知らぬ他人でも見るかのように無表情な明美は、まるで健作の背後でも見ているような隔たりを感じさせる冷たく冴えた眼をしている。
面立ちも少し違う…。ほんの束の間に幾つか歳を重ねたような不思議な落ち着きを見せていた。
「どうする? 出掛けるのか?」
「そうね、まずは腹ごしらえ…。お腹すいたでしょ」
そういえば、義母が作ってくれた朝食もそこそこに家を飛び出してから、今まで食事のことも忘れていた。明美に至っては、健作が泥水と呼ぶ起き抜けのコーヒーを飲んだだけで、一切食事は口にしていなかった。
死
「死」とは何か? 古来、様々な文化や、また時代によって定義は異なるが、現代においてもまだ不確かな部分が多い。医療においては「自発呼吸の停止」「心拍の停止」「瞳孔の開き」を死の三兆候とするが、これとて臓器移植が盛んに行なわれるようになった現代においては、確実な兆候とは言えなくなっている。と同時に、亡くなった子どもの髪や爪がわずかの伸びるのを「生きている」と、荼毘に付すのを拒む親が居たりもする。いずれにしろ、近親者の「死」に対する認識と覚悟は、残された者に重くのしかかる。
常々、「死とは卒業」と語っている真印さん。「今世における課題をクリアできたなら、もう再び生まれ変わることはありません。そう言う人は、高い神格を持ってはるかに高い次元に戻れるのです」という。そして、真印さんは自らの誕生の瞬間を振り返った。「私は生まれ落ちるその時『ああ、また辛い思いをするんだ』と、とても残念に感じました(苦笑)」。そして「死は痛みや苦しみの無い世界へ行くことです。ですから、何も悩み苦しむことはありませんよ」と微笑んでみせた。そんな彼女はさらに「日々、今世における課題を積極的に見付けては、それを正しくクリアすることをゲームのように楽しんでいる」とも話す。真印さんのような心がけを誰しもが持つことができたなら「死」、そして「生」を、もっと前向きに捉えることもできるのかもしれない。