
<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>
「あんたの持ってる力っていったい何なの?」
姉妹とはいえ、良子はずっと不思議だった。良子が言う力とは、明美が亡くなった父と言葉を交わした特殊な能力のことだ。
「…うん。多分そう。…でも、別に特別扱いなんてされて無かったわ」
「なに言ってんのよ。アンタ、パパに叱られたことある? おばあちゃんにだって…。アンタだけよ、おばあちゃんが部屋に一人だけ呼びつけたりしてたの。これでも私はアンタの姉なんだからね…。なんとなくだけど、アンタが特別なんだってことはわかってたわ。アンタっておばあちゃんと同じなんでしょ。…パパもなの? そうよね。パパはおばあちゃんの子どもだものね」
「…パパは少し違うと思う。パパは『怖い』んだって。だから、自分で封印していたみたい。それに、おばあちゃんとも違う気がする。でも、そんな力があるのって私だけって思わないでよね。だって、パパがおばあちゃんの子どもってのと同じように、私たち三人は、みんなパパの子どもでおばあちゃんの孫なんだから」
「そうね…。そりゃそうだわ。でも、アンタだってわかってるでしょ。三人の中でも、きっとアンタだけにおばあちゃんみたいな力があるのよ。なぜだかわからないけれど…。そんなことは、私は小さい頃からわかってたわよ。さっきも言ったように、これでも私はアンタのお姉ちゃんなんだから」

幼いながらに姉妹は祖母の特異性を理解していたし、大人たちが「毛物祓い」とか「憑き物落とし」などと口にするのを耳にしていた。それだけで姉妹は、祖母や祖母に連なる自分たちが何か特殊な存在であることを理解できないまま思い知らされてきた。
「おばあちゃんは、パパにも似たような力があるって言ってたわ。でも、パパに聞いたらそうじゃないって。『お前みたいに整ってない』って言ってた。それと『怖くてやめたんだ』とも言ってたわ」
「やっぱりそうだったのね。…わかった。じゃあ、今みたいになにかわかったら私にも教えてね。それと、もしもまたパパとお話しができたら、私が心配してるって、夢でもいいから会いに来てって言っておいて」
姉妹の中で最も温厚で冷静な良子の声は、咎めだてるように始まり涙声へと変わっていた。そのまま部屋を出て行こうとした良子に、明美がたまらず声をかける。
「お姉ちゃん、ちょっと待ってくれない」
振り返った良子の前に、さっきまでとは違う何か思い詰めたような妹の顔があった。
聞き漏らしたサイン
「なに? …なにかあったの?」
途端に言い知れない不安が良子の胸を締め付ける。
「さっき、大丈夫だって言ったじゃない。…まだなにか? パパになにか起きたの?」
「…ううん。別になにかがあったってわけじゃないのよ。ただ、パパは最後になにか言おうとしてたのよね」
「なにそれ? パパはまだ他になにか言ってたの」
「……」
「なによ。ちゃんと言いなさいよ」
「別に隠してるわけじゃないの。ただ、ちゃんと聞き取れないまま途切れちゃったから…。でも、なんだか嫌な感じなのよ。もしかしたらパパは、パパが死んだ後のことでなにか不安なことがあったんじゃないかと思うの。それも、もしかしたら普通じゃないこと」
「普通じゃないことって?」
良子の顔が曇った。さっきまでの、自分には無い力を持って生まれた妹に対する嫉妬と誇らしさがないまぜになった感情とは違う、何ともいえない胸騒ぎを感じていた。
「お母さんも美由紀も居ないんだから正直に言ってよ。アンタ、なに考えてんの?」
「うん。パパにも見えてたはずなのよ。…確かにパパは、『パパはこの力が怖いから封印したんだ。だから、明美のように見えたり聞こえたりしないんだよ』とは言ってたけれど、パパにだって色々と見えていたはずなのよ。…おばあちゃんや私みたいじゃなかったかも知れないけれど…」
「待って…。それがなにか、パパが言いかけたことと関係あるわけ? それに、アンタが言う『見える』とか『聞こえる』ってなに? なにが見えて、それがパパとどう関係してるっての?」
明らかに姉はバランスを失いかけていた。
「ごめんお姉ちゃん。私、パパが居なくなって、それでもやっと話せたから少し興奮してるみたい。ごめんね、気にしないで」
「…もぅ…せっかく好い気分になってたんだから。やめてよね。…はいはい。もう、アンタも寝なさい。明日は、また朝から忙しいんだから」

いつもの良子なら、こんな中途半端な逃げ口上で納得するはずが無い。だからと言って、これ以上妹を責めることに意味の無いことを知っている姉が、肩を落として部屋を出て行った。ここにも一人、最愛の者を亡くして祈りを捧げる者がいる。何をどこに向けて願えばいいのか…。皆が、祈る先を求めていた。
その夜、明美は父の枕元に座り、少しずつ弾力を失い白蝋と化していく頬を見つめながら朝を迎えた。
朝の儀式
朝を迎えはしたが、気持ちが昂って何も手につかない。
明美は、まさかこんなことになるとも知らずに夫の健作と一人娘の亜里沙を連れて帰省していただけだし、長女の良子も、急を聞いて高松から夫の哲也と一緒に駆け付けたという有様だ。美由紀が居るのは当然だったが、それでもこれだけの人数が揃うことなどこの数年なかった。
一人母だけが慌しく朝食の用意をしているが、いざ娘たちが起きてきてみれば、皆一様に眠そうな顔をして一向に箸をつけようともしない。テーブルには、綺麗な半熟の黄身を乗せた目玉焼きと鮭の切り身が並んでいる。作った母ですらも手をつけないでいたが、それは何も父の死を悼んでのことではない。亡くなった父こそ、朝昼構わず旺盛な食欲を誇る男だったが、娘たち三人は、おしなべて母の「朝はダメ遺伝子」を受け継ぎ、こんなどんよりとした朝食風景を常としている。
「お義母さん、このお味噌汁、本当に美味しいです」
「あらそう…。そう言ってもらえると嬉しいわ。でもお味噌は、そこの農協で売ってる普通のお味噌なのよ」
たまらず手を伸ばした味噌汁を、良子の夫・哲也が褒めちぎる。娘たちからは聞くことの無い褒め言葉に母が頬を緩める。
「…なに言ってるのよ。私だって同じお味噌を使ってるわよ。そんな、私の料理が下手みたいなこと言わないでよ」
良子も明美も、男どもがあまりに母の味噌汁を褒めるものだから、お味噌だけは、同じものを送ってもらっていた。
「いや~本当に美味しいですよ、お義母さん。ほら、亜里沙も食べてごらん」
そんなつもりは無いのだろうが、義理の息子二人による奇妙なお追従合戦となった。声を掛けられた亜里沙は、インスタントコーヒーの入ったマグカップを手に、不機嫌極まりない顔で食卓の一点を睨んでいる。見ると、向こうのソファーに座る三姉妹はもちろんのこと、母の礼子までもがマグカップを手に暗い顔をしている。それは、奇しくも同じ遺伝子を持って生まれた五人の女が密かに守り伝える儀式のようで、どうやら同じ印象を抱いたらしい哲也と健作は顔を見合わせた。

こうして始まる新しい一日を、最愛の父が不在のまま過ごすことの違和感を、5人の女が苦いコーヒーとともに飲み下す姿が哀しく切なかった。
結婚して10年。健作は、毎朝この光景を目にしている。明美は無類のコーヒー好きで、特に起き抜けのコーヒーは欠かせない。
ただ問題は、それほどのコーヒー好きにも関わらず、コーヒー本来の味に対するこだわりがあるように思えないことだ。明美が自分で淹れたコーヒーを、間違えて一度口にしてしまった健作は、以来、明美の淹れたコーヒーを「泥水」と呼んで遠ざけるようにしていた。にもかかわらず、家ではもちろんのこと外出先でも、必ずといっていいほど明美は喫茶店に入りたがる。そして、まるで結構なコーヒー通かのような口ぶりでオーダーする。しかし、悲しいかなそのオーダーを伝えるウェイトレスも、したり顔で豆を挽くマスターも、明美が毎朝「泥水」を飲んでいることなど知るわけもなく、そんな明美を一級のコーヒー通として扱うのだ。そんなシーンに出くわすたびに、健作は一人バツの悪い思いをする。
そんな「泥水」を平気な顔で啜る女が五人並んだ光景は、ある種の神々しさすら感じさせた。
父の葬儀
午後には、明日の告別式会場へと移動し通夜をすることになっている。葬儀社の車が到着し亡骸を外に運び出すと、そこには会場までは足を運べない町内のご老人が20人ほども集まり静かに手を合わせていた。こんな当たり前のしきたりも知らないでいた家族は、ご老人たちが集まってくることも知らずにいたことを恥ずかしく思い深く悔いた。そして、父の亡骸に手を合わせて見送ってくれる名前も知らずにいた方々に深く頭を下げた。
夕刻、しめやかに始まったお通夜の席では、続々と集まってくる義父の兄弟を前に、健作が可笑しいくらい緊張していた。
「おい。あの迫力のある女の人は?」
「あれは敏子おばさん。パパの妹よ。…挨拶回りのときに会ってるわよ」
虫の知らせとでもいうのだろう。突然の父の死は、それまでは仕事を理由に寄り付こうとしなかった実家に、なんとなく夫婦揃って帰った久しぶりの帰省中の出来事だった。
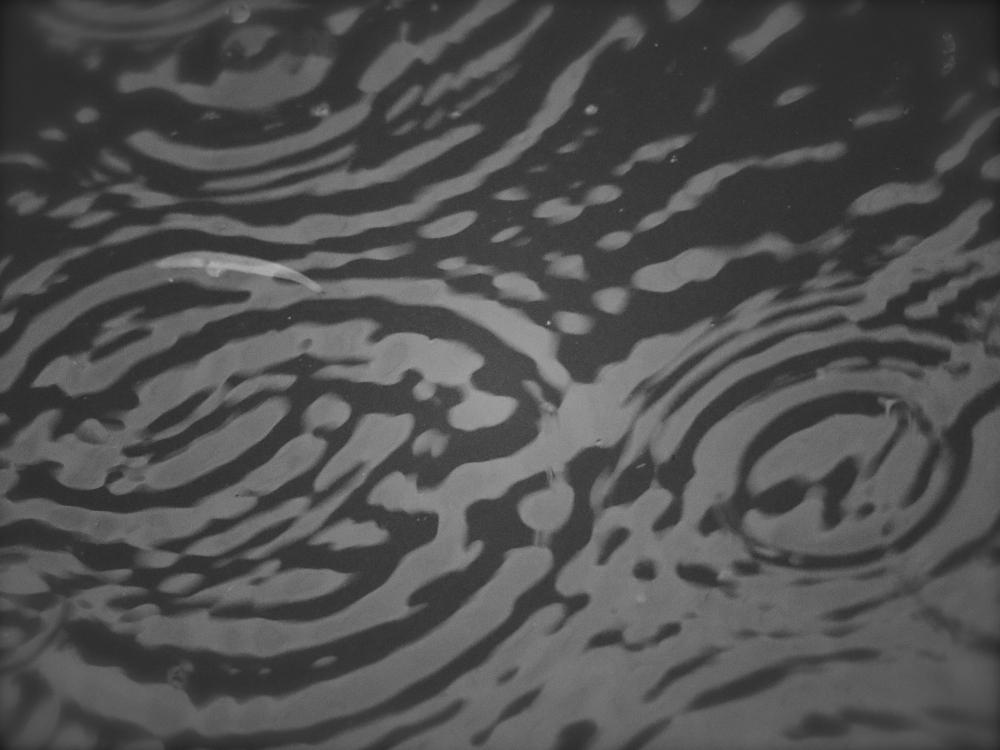
前回明美の親戚と顔を合わせたのは、二人の結婚を報告する挨拶回りだから、もう10年以上も前になる。10年も会っていない嫁方の親戚の顔など覚えているはずもない。
その夜はそのまま通夜会場に泊まり、翌日は朝から、喪服の着付けや準備に姉妹はてんてこ舞いをさせられた。
告別式は、亡き父の意思を尊重して、お太夫さんもお坊さんも呼ばない友人葬に決めた。松山ではまだ珍しいらしく、父の友人だった互助会の社長ですら自社で行うのは初めてだと話していた。それでも、自社で行う初めての「友人葬」が親交の深かった父とあってか、見積もった金額以上に立派な式を用意してくれた。参列者は400人を越え、田舎町のとうに引退した中学教諭にはおよそ似つかわしくない賑やかな式となり、参列者からも「とても良かった」と温かい言葉をかけられ、姉妹は胸を撫で下ろした。そんな告別式の会場から、父の亡骸を乗せたステイションワゴンと親族が乗るバスが斎場へと向かう。
市内の北東に位置する山の中腹にある斎場には、祖母が亡くなった際に一度来たことがあった。当時まだ小学生だった明美は、祖母を亡くした寂しさよりも、いとこ達が集まったことの興奮や、葬儀のしめやかさに心を奪われ気もそぞろだったのを今も後悔している。祖母は神道を崇拝していたらしく、近くの氏神様からやってきたお太夫さんがあげる祝詞に、笑いをこらえたものだった。
今、父の亡骸とともに向かっている斎場は、そんな恐ろしくも悲しい思い出の場所。しかし、いつの間にか建て直された真新しい斎場は、以前の寒々しさなど微塵も感じさせないモダンなビルに変わっていた。
見事に礼服を着こなした男性が、美しい一礼と共に滞りなく父親の最期のイベントを執り行ってゆく。
およそ一時間の休憩の後、拾骨室に呼び集められた一同の前に白い骸骨と化した父がストレッチャーに乗せられて現れると、そこかしこからすすり泣く声が聞こえてくる。しかし明美は、すでに父との交信が叶った以上、魂の戻るわけもない亡骸に興味はなく、ただ1000℃を超える炎で焼かれ、触れる者の指先を焦がす遺骨の熱さに驚いていた。
『今頃パパはどこにいるのかしら? これって見えてるのかなぁ?』
何一つ飾り気の無い拾骨室を見回してみたが、案の定父の痕跡は見当たらない。
帰りの車中にはもう悲しみの色も無く、後方に陣取った叔母たちが世間話に花を咲かせている。やがてバスは告別式の会場へと戻り、宴席を囲んでの精進落しとなった。
親戚とはいえ、普段は何の交流も無い人たちと過ごす苦手な席ではあったが、それでも、父のために集まってくれた方々に姉妹はお酒を注いで回った。バスの中でもそうだったが、父の姉妹である叔母たちは仲が良い。とにかく、話が止まらない。
何を話しているのかと時折耳を傾けてみるが、とりとめもない世間話に興味を失いかけたとき聞き慣れない言葉が飛び込んできた。
そしてそれは、明美を更なる苦衷と恐れの世界へと誘う呪詛にも似た言葉だった。
葬儀
葬儀のしきたりや、たしなみは、全国各地方ごと、また宗教や宗派によってさまざまであるが、全国ほぼ共通して見られる風習が、参列者が帰宅時に使用する「清め塩」だろう。その名の通り、穢れを払い、心身を清めてくれるものだが、真印さんは、覚えておいていただきたいことがいくつかある、という。まず一つは「ここで言う〝穢れ〟とは決して故人の霊ではなく、そこに集まってくる様々な邪気のこと」だという。さらに「清め塩をお使いになるときは①玄関の敷居をまたぐ前に使う②胸・背中・足元の順に使いましょう」(真印さん)。玄関をまたいでしまうと、穢れを家の中に招き入れることになるのだそうだ。ちなみに真印さん自身は「どうしても嫌な感じが拭えない時は、写経を6枚胸元に入れて参列します」という。これから、葬儀に参列する予定のある人は、参考にしてみてはいかがだろうか。
著者プロフィール
那知慧太(Keita Nachi)愛媛県松山市出身 1959年生まれ
フリーライターを経てアーティストの発掘・育成、及び音楽番組を企画・制作するなど、東京でのプロデュース活動を主とする。現在は愛媛県に在住しながら取材・執筆活動に勤しむ。『巳午』を処女作とする。








