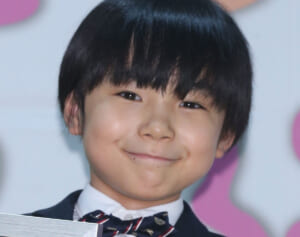「『今回のがんは、これで完全にOKです』。担当の医師たちからこう宣言されたのは、昨年の10月2日。それから2カ月に一度定期検査をしていますが、結果はずっと異常なしで。いまは治療はしていないし、普段の生活も元気だったころとほとんど変わっていません」
作詩家で、直木賞作家のなかにし礼さん(77)は、2012年に食道がんを発症。このときは陽子線治療によってがんを克服した。彼に食道の裏側、気管支に近いリンパ節に再びがんが見つかったのは昨年の2月初旬だった。しかも担当医師たちから「今回は、陽子線は使えません」と宣告された。そのうえがんは気管支に密接していて、がんが成長して気管支を突き破ると死に至る――という極めて危険な状態だった。
「がん手術は昨年の2月25日。でも、がんを取り除くことはできなかった。あまりにもがんが気管支に密接していて、無理にがんを切除しようとすると気管支に穴を開けることになる。つまり穿破(せんぱ)する危険性があって。僕が『穿破』という言葉を医師から聞いたのは退院する3月2日ですが、女房(元歌手・石田ゆりの由利子さん=64)と息子(43)、娘(33)は手術の直後、僕がICUにいるときに聞いたそうです。『穿破』すると、最悪の場合ほとんど即死、最長でも4日ぐらいしか持たない。しかも、穿破は手術したその夜に起きる可能性が非常に高い。この話を聞いた娘は、失神してソファに倒れ込んだそうです」
手術後、なかにしさんに穿破は起きなかった。だが、その恐怖はずっと付きまとった。
「起きなかったのは、あくまで結果論で、退院後も僕はずっと穿破と向き合って――たとえて言うなら『いつ暴発するとも知れないピストルを頭に突き付けられた状態』で日々を過ごすことになった。先生からは繰り返し『1日1日を大切にしてください』『週単位で人生を考えてください』と言われるし、いつ穿破が起きるか本当に怖くて……。毎晩、女房と『きょうも終わった』『よかったね』と言って、夜中に何も起きませんようにとハイタッチして床に就きましたが、僕は『たぶん桜の花は見られないだろうな……』と思っていました」
生きようという意思を持ちながらも、なかにしさんは淡々と自らの死の準備を始めたという。
「自分の密葬やお別れの会の段取りをしたり、戒名を考えたり……そんな僕のそばにいた女房は心中穏やかではなかったはずだし、大変だったと思います」
2人が結婚したのは43年前。由利子さんは当時19歳だった。翌年には長男が誕生した。
「彼女は『僕あっての人生』で、口には出さなかったけれど、僕がいなくなったら『自分はどうなるんだろう……』と、さぞかし不安だったはずです。そのストレスからでしょう。いつも明るい彼女がだんだん暗くなって、やせていった。心配で食べられない、眠れないということで。それでも彼女は、僕が入院している間、毎日通ってくれた。僕が気に入っている店の弁当を持って」
死を覚悟するほどのがん闘病。それは周りの家族の心にも大きな影響を与えていたのだ。
「彼女はうつ状態になっている――と感じた僕は『精神腫瘍科に行って相談してきなさい』と。入院していた病院には、精神的に苦しんでいるがん患者や、看病する家族の精神面を医学的に支える『精神腫瘍科』があったので。そこへ行かせて、処方してもらった薬を飲んだら食欲も睡眠も回復して、彼女は日に日に元気になりました」
2度目のがん闘病は、なかにしさんに新たな気づきを与えた。それは――。
「がんと闘いながら思ったのは『僕がいなくなったら女房は大変だ』ということが、ものすごく如実にわかったということ。つまり彼女への思いや“愛”がわかった。子供たちに対しても同じことが言えるけれど。同時に、女房と子供たちがいかに僕のことを愛しているか、大事に思っているかということを痛感したことも確かです。それだけに、これからは女房をより大事にして生きていかなければいけないと思うし、もの書きとしては、命のある限り書き続けていきたい。僕は『書くこと』にしか興味がないですから」