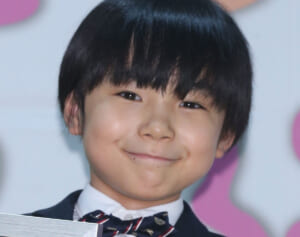情けない男って言われてそれほど新鮮な感じはしないんだけど。
第77回アカデミー賞で5部門にノミネートされ、脚色賞に輝いたハリウッド映画『サイドウェイ』が、日本人キャストによるリメーク版『サイドウェイズ』と
なって10月31日より公開されます。小日向文世演じる道雄と生瀬勝久演じる大介がアメリカ・カリフォルニア州のワイナリーを巡る旅で、20年前と今が交
錯するさまざまな出来事が重なり、人生を見つめ直す、という作品。主演を務める小日向文世さんに作品のことから、役者を目指した若かりし頃のことまでお話しいただきました。
 ——この度の映画『サイドウェイズ』とハリウッド映画『サイドウェイ』を見比べてみて、『サイドウェイズ』は主人公が日本人なので、日本人がアメリカにいるってことで、国民性の違いがわかって面白かったです。
——この度の映画『サイドウェイズ』とハリウッド映画『サイドウェイ』を見比べてみて、『サイドウェイズ』は主人公が日本人なので、日本人がアメリカにいるってことで、国民性の違いがわかって面白かったです。
小日向文世(以下、小日向):はいはいはい。それは良かったー。アハハ。そういう風に見ていただけると本当に嬉しいです。
——ぼくもそうでしたし、読者の人の中には“リメイクってどうなの?”と思われる人もいると思うんですが、小日向さんが考える2つの作品の違いを教えてください。
小日向:まあ、あの、冴えないパッとしない男と女好きの男っていう設定はね、日本版も変わらずにそうしているんですけど、圧倒的な違いは“日本人がアメリカの地に渡って”ってとこなんですよね。生瀬(勝久)さん演じる大介も、向こうの奥さんをもらおうとしてて、すっかり向こうの空気になじんでいるようだけど実は日本を捨てきれないというか。向こうの人との結婚の1週間前にミナって日本人の女の子に出会って「やっぱり俺は日本人のほうがいいのかな?」 って思ったりね。やっぱり日本を捨てきれないというか日本人の血が騒ぐというか。ぼくが演じた道雄は、それのもっと典型的な日本人として、アメリカの地で英語でワーっと言われて立ち尽くしちゃう、そういう男です。その道雄の姿を日本のお客さんが見て「ああ、きっと自分もこうなるんだろうな」とか「ああ、わかるわかる」とかって親近感を持っていただけたらな、って思うんですよね。舞台がカリフォルニアのナパバレーという場所で、もちろんワイナリー巡りも見所の一つだと思いますけど、ワインがあまり好きじゃないって人やお酒を飲まない人にとっては、興味がなくなっちゃうっていうかね、そればかりだと。それだけじゃなくってね、日本人がアメリカの地で頑張っていたり、なにかそこで恋をしてしまったりとか、アメリカの地にいるからこそ起こることが面白いんじゃないかな、って。
——大介が「ウップス」って言ったりとか。
小日向:そうそう、なにがウップスだよ、ってね。そういう感じですよね。
——その「ウップス」を道雄がつっこむ感じがすごくわかるな、って思いながら見ていました。登場人物のように、実際にキャストのみなさんも日本人スタッフが6人のなかで1ヶ月間過ごされたということで。道雄のように戸惑うこともあったんじゃないですか?
小日向:もう言葉に関しては戸惑いまくりですよね。基本的にほぼ英語はダメなんで……。なんとなく英語だから、聞き慣れているから、こういうことを言っているんじゃないか、と、ある程度想像できて、わかったりはするんですよ。特に仕事に関して、照明部さんや音響部さんが何かを説明してくれるじゃないですか、マイクを仕込みます、とかね。もうちょい大きな声で喋ってくれ、とか。照明だったらもうちょっと手前に入ってくれればあたるんだけど、とか。そういうことはだいたいわかるんですよ。でも、日常会話になったとたんに全然わからない! その度に通訳さんを探してね(笑)。だから1ヶ月もいるとだんだんね、しょっちゅう「おはよう」ってね、朝、すごい笑顔でね「グッモーニング! 文世」とか「グッモーニング! 道雄」とか言われてね。どんどん仲良くなって行く感じはわかるんだけど、なればなるほど突っ込んだ話をしたいのにできなくて。とにかく笑ってごまかすしかないんですよね。「OK! OK!」ってやたら愛想のいい人になって。なんだか、小日向と道雄が重なっちゃったな、って感じでしたね。
 ——その感じ、とてもわかります(笑)。ところで、プレスシートに「ハリウッドで最も情けなさそうな二人」って書いてあるんですが。
——その感じ、とてもわかります(笑)。ところで、プレスシートに「ハリウッドで最も情けなさそうな二人」って書いてあるんですが。
小日向:その文句、さっきちょろっと聞きました。向こうの、ハリウッドの20世紀フォックスの人が出来上がった映画を見て、まさにこの日本人二人は情けない! ってことを言ってくれたのか、キャスティングの段階で経歴とか写真とかを見て、この二人を情けなさそうだから使いたいって言ったのか。アハハ。映画を見て、出来上がったのを見て「情けない男二人だね」って話で盛り上がったんじゃないですかね? ぼくはそのフレーズを誰がどう考えてつけたのか知らないんですよ。
——てっきり履歴書的なものを見てついたのかと思っていました。
小日向:アハハ。たぶんそれは違うと思いますよ。生瀬さんなんかは情けない、っていう印象はないもんな〜。でもこの映画のなかではほんとに、どうしようもない男を演じててほんとにハマってるな、って思いますけどね。ぼくはね、情けない男の役、けっこう多いんですよ。だから、情けない男って言われてそれほど新鮮な感じはしないんだけど。
——映画の中で、20年って時間の流れを主人公たちはよく感じていると思うんですけど、小日向さん自身、20年前の89年は自由劇場にいらっしゃいましたよね。
小日向:ちょうど文化村のシアターコクーンのこけら落としに参加しているころですね。
——当時は、おそらく“知る人ぞ知る”という、舞台でご活躍されているときだと推測するんですけど、「20年」に限らずに俳優になってから「あのときは若かった」とか「あの時代は大変だった」とか、若かりし頃を振り返って思い出せるエピソードがあれば教えてください。 小日向:役者を目指してね、役者になろうと思って、それにはまず劇団に入らないといけないと思って入ったのが自由劇場でした。1977年で23才のときなんですけど。当時はもちろんまともに役ももらえないし、劇団ではまったく生活費を稼げないんで、アルバイトが本業みたいになっちゃうんですよ。それで、初日が近づくと、アルバイトを1週間くらい休まないといけなくなるんですけど、そうなるとすぐにクビになったりね。だからとにかく夜中のアルバイトができるところとか、そういうところばっかり探していましたね。ぼくは、西麻布の自由劇場ってところにいたときに、横断歩道をはさんで真向かいにあったゲイバー、「プチシャトー」っていう老舗のゲイバーなんですけど、そこと、自由劇場の霞町の交差点を六本木にあがっていく途中にあるオナベバー。レズバーですね。そのころって、そういうのばっかりやってるんですよね、夜中にできるから。やっぱりその頃は元気でしたね。“自分は俳優として一人前になれるんだろうか?”ってことも、何の確信もないのに意外と不安じゃないんですよね。ただ、毎日が新鮮で、人前で何かを演じるってことが楽しくてドキドキしたりして。そして、夜中はアルバイト。それの繰り返し。そのころのことは、はっきり覚えているんですよ。今から32年前か。ついこの間のようですね。
小日向:役者を目指してね、役者になろうと思って、それにはまず劇団に入らないといけないと思って入ったのが自由劇場でした。1977年で23才のときなんですけど。当時はもちろんまともに役ももらえないし、劇団ではまったく生活費を稼げないんで、アルバイトが本業みたいになっちゃうんですよ。それで、初日が近づくと、アルバイトを1週間くらい休まないといけなくなるんですけど、そうなるとすぐにクビになったりね。だからとにかく夜中のアルバイトができるところとか、そういうところばっかり探していましたね。ぼくは、西麻布の自由劇場ってところにいたときに、横断歩道をはさんで真向かいにあったゲイバー、「プチシャトー」っていう老舗のゲイバーなんですけど、そこと、自由劇場の霞町の交差点を六本木にあがっていく途中にあるオナベバー。レズバーですね。そのころって、そういうのばっかりやってるんですよね、夜中にできるから。やっぱりその頃は元気でしたね。“自分は俳優として一人前になれるんだろうか?”ってことも、何の確信もないのに意外と不安じゃないんですよね。ただ、毎日が新鮮で、人前で何かを演じるってことが楽しくてドキドキしたりして。そして、夜中はアルバイト。それの繰り返し。そのころのことは、はっきり覚えているんですよ。今から32年前か。ついこの間のようですね。
——ついこの間のようなんですね。
小日向:そして89年というと、今度、自由劇場が文化村のシアターコクーンってところで、1年間ずーっと舞台ができるっていう、そういうフランチャイズになって、そこでまた6年間。36才から42才までいましたね。その6年間はとっても濃い時期でしたね。
——毎日毎日舞台ですか?
小日向:ほんとに! 芝居漬けで。そのころはアルバイトをせずにすんでいたんで、ほんとに芝居に集中して。1本幕が開くと、昼間は次の舞台の稽古をして、何度も同じ物をやっていけるっていう「レパートリーシステム」というのにしていたので、だいたい2週間から4週間稽古をして、すぐに次のを開けるっていう状態でした。それでたまに新作も、っていうそれの繰り返しで。稽古、本番、稽古、本番が延々続きましたね。ほんとに! 1年中、舞台のことだけに関わっていたという。