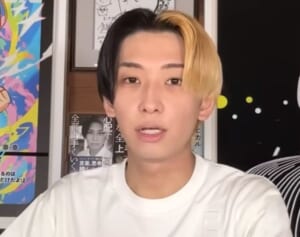乳がんを経験し、講演などの活動を行う女優の音無美紀子さん(67)と「がん哲学外来」理事長で、がん患者やその家族と対話し、生きる希望を与えている順天堂大学医学部の樋野興夫教授(63)。2人に1人が罹患する時代に、がんやがん患者とともに生きてきたお2人が、病いにどう向き合えばいいかを語り合った。
音無さんは’88年に乳がんが見つかり、当時標準治療だった全摘手術を受けた。手術後は、うつになり「死にたい」と苦しんだという。
音無「10時間に及ぶ手術、その後のリハビリと奮闘しましたが、抗がん剤の点滴治療のミスをきっかけに心を閉ざしてひきこもり状態に」
樋野「がん告知を受けた人の約3割に音無さんと同じようにうつ的な症状が現れます」
音無「眠れない、食べられない、何もできない。当時、そういうのは、心が弱い人がなる“ノイローゼ”だと思い込んで、恥ずかしくて病院にも行けなかった。告知されてからの闘病の苦しみ、『なぜ私が?』という恨みや未練も重なり、つらかった。いくら医療技術は進歩しても、人間の“心”は同じ気がしますね」
樋野「はい。医師には最先端の治療を確立することと、もう一つ『人間的な責任で手を差し伸べる』という使命がありますが、それが失われようとしています。そこで私は’08年に『がん哲学外来』を立ち上げました。患者さんとご家族に、『病気であっても病人ではない』『がんも単なる個性である』というような言葉の処方箋を出しています」
音無「言葉といえば、ある日、当時小学生だった娘の『ママなんで笑わないの?』の言葉にハッと気づかされたんです。左胸を全摘してから自分の体もそうですが、いっさい鏡を見られなくなったんです。鏡を見てみると口角も上がらないし、どう笑えばいいのかさえ忘れてしまっていて。娘に言われてから意識して鏡で笑顔をつくるようになりました。少しすると口紅もつけてみよう。美容室にも行こうと、徐々に元気になれました」
樋野「家族の『言葉の処方箋』に助けられましたね。私の哲学外来では一人1時間、カルテもなし。お茶を一緒に飲みながら話を聞いて対話するだけです。どんな病気なのか。なぜここに来たのかをじっくり聞くうちに本音を吐露していきます。自殺を考えていた人に『あなたには役割がある。存在には意味がある』と伝えると、自分ができることを探し始めます。その患者さんが自ら『メディカルカフェ』を開き、同じ苦悩する人の悩みに耳を傾ける人もいるんです」
音無「私自身、“心が重い日々”が続きましたが、一歩を踏み出すことで変わりました。うつで、夏休みに娘をどこにも連れていけないとき、『絵日記を書く材料がない』って言われたんです。娘は『ママと、目玉焼きをつくりたい』と言うから『それならできるかも』と、勇気を出してやってみたら『ママすごい』と娘が喜んでくれました。翌日、『じゃあ、おにぎりをつくろうか』と言って三角おにぎりをむすんだ私に『すごい』と娘が言ってくれて。本当に小さな一歩でしたが、これをきっかけに気持ちが回復していきました」
樋野「家族の接し方では、懸命に尽くすつもりが、気持ちの押し付けになる“よけいなおせっかい”が多い。ふだんは話もしないのに病気になると、途端に世話を焼く。それが患者の悩みや負担につながっています。そんな人に私は『偉大なるおせっかいであれ』と伝えます。同じ部屋にいて寄り添うだけでいいんです。夫婦でリビングに無言で1時間一緒にいる。“よけいなおせっかい”だと思われないように、お互いが一緒にいることで安心できる関係をふだんからつくっておきましょう。大事なのは相手に関心を持つこと。『後ろからじっと見守る』イメージです」
音無「私たちも仕事が忙しく、ふだんは対話の時間が多かったわけではないのですが、主人(俳優の村井國夫さん)は私が病気のことを人に言えずに苦しんでいることを見てくれていたようです。『もうさらけだせば』という思いが助けになりました。がんになって13年後、’01年に主人がテレビ番組でポロッと私のことを話したところ大反響で、それをきっかけに私も『徹子の部屋』に出演して闘病について告白でき、ようやくラクになりました」