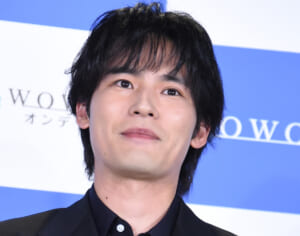主婦業の傍ら、ハリウッドで腕を磨き、大河ドラマ『麒麟がくる』の“坊主メーク”などで、邦画・ドラマ界でのパイオニア、第一人者として活躍し続ける特殊メークアップアーティスト・江川悦子さん。
短大卒業後はファッション雑誌「装苑」の編集部に入った彼女が、特殊メイクの職を志したのは、夫のアメリカ転勤がきっかけだったという。到着したアメリカで、夫婦で見たのが、81年公開のホラー映画『狼 男アメリカン』。映画館の暗闇の中、主人公の青年が狼男に変身するシーンが、江川さんをくぎ付けにした。
「主人公がアアーッとうなりながら、手や顎がズンズン伸びていき、毛むくじゃらに変身していく。CGのない時代ですから、どうなってるんだろう、どうやってこんなシーンを作るんだろう、って」
そのシンプルな驚きは、すぐに確固とした夢に変わっていた。
「私も、これ、やってみたい!」
江川さん、27歳の夏だった。
しかし、特殊メイクの学校に通い、いざ就職!となっても、アメリカ人の方が職が見つかりやすい。映画スタジオから何度も門前払いされる江川さんだが、決して諦めなかった。そうして掴んだ、最初の大きな仕事は84年公開の映画『デューン/砂の惑星』。同年には、あの『ゴーストバスターズ』でマシュマロマンの製作スタッフに抜擢された。
「とはいえ、最初はパーツ作りから。『なんでもやります』で、実績を積みました。よく『日本人は器用だ』とも言われました」
そんな、怒涛の7年間のアメリカ生活を終えて帰国した江川さんを待っていたのは、女性の特殊メークアップ・アーティストがゼロという日本の現状だった。作品作りをしながら営業しようと決めたが、そのためには、工房が必要になる。江川さんは、日活のスタジオへ談判へ向かい、東京・調布の日活撮影所の一角に、特殊メーク制作会社メイクアップディメンションズを設立したのが86年のこと。
日本映画初参加となったのは、『親鸞 白い道』(87)。「ハリウッド仕込みの技術を持つ女性がいる」との口コミから声がかかった。依頼されたのは、生首の造形。その後はバブル経済を追い風に、映画やCMなどの仕事が次々と舞い込んだ。
「子供を保育園に預けながらでしたから、いつも私がお迎えがいちばん遅くて、娘には『ごめんなさい』の気持ちでいっぱいでした。私が地方ロケのときには、義母が四国から出てきてくれたり。頼れるところは頼る、というのもアメリカで学んだことです」
メークを手がけたなかには、NHKドラマ『トットてれび』(16)で100歳メークを施した黒柳徹子さんのように、
「私が100歳になったら、こんな感じになるのね」
と、喜んでくれる人もいる。
「ありがたかったし、そんなやりがいを次につなげていきました」
00年代に入ると、『ハリー・ポッター』(01年)や『ロード・オブ・ザ・リング』(01年)などの世界的人気で、特殊メークはますます注目されるようになる。08年には、オフィスを現在の場所に移転。このころには、業界では「坊主メークは江川さんに」の評価が定まっていた。ドラマ『あの戦争は何だったのか』(08年)で、初めて坊主メークを施した北野武さんは言った。
「すごいね。痛くないし、軽いし、つけてるのを忘れるよ」
同じころ、前出の『おくりびと』にも参加。主人公の納棺師を演じる本木雅弘さんが遺体と向き合うシーンも多いが、実はこれも一部はダミーだ。
そして今、大河ドラマ『麒麟がくる』で、旧知の本木雅弘さんらの坊主頭などを担当。
「斎藤道三を演じた本木さんや、足利義昭役の滝藤賢一さんなど。かつらピースと俳優さんの地肌の境目をなくす手法が、私たちの腕の見せどころです」
こんな逸話がある。
本木さんの大河での坊主頭を見た『おくりびと』の滝田洋二郎監督が、
「あれ、メークなの!? 本木君のことだから、てっきり本当に頭を剃ったかと思ったよ」
と驚嘆したというのだ。
プロ中のプロの目をも完璧にあざむく高度なテクニック。それこそ「してやったり」の思いだろうか。江川さんに問えば、
「ビミョーですね。ありがたいんだけど、『もしかして、あれ特殊メーク?』くらいは気づいてほしかったり……フフフフ」
技巧を尽くすほど、周囲にはそれとわからない。まさに職人仕事ならではの醍醐味なのだろうーー。
(撮影:田山達之)
「女性自身」2020年11月17日号 掲載