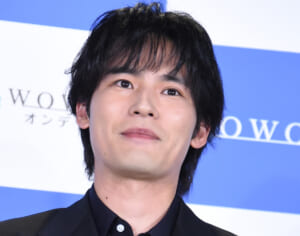■この歌詞を書くために今までの苦しみや悲しみがあった。もはや、表も裏もない!
「焦りまくってました。同世代のSPEEDがデビューと同時にブレークして、最年少メンバーは同い年。宇多田ヒカルさん、安室奈美恵さんたちもみな10代でヒット連発でしたから、私はすでに手遅れ、という思いでした。曲を作り、バンド活動を始めても先は見えず、私の人生はどうなるんだろうと不安で、ピアノに突っ伏して泣いていました」
18歳からは渋谷のCDショップでアルバイトを始め、気づけば20歳になっていた。
「いちばん葛藤していた時期です。私は相変わらずバイトしながら、中華屋のダクトからの煙の匂いをおかずに塩にぎりを食べる日々。一方、同級生は、そろそろ就職活動を始めていたり。もう私は、戻るに戻れない。この世界に骨を埋めるしかないんだとの覚悟、というより開き直りでしたね」
ただ、音楽で食べていきたいとの思いだけは消えなかった。
「好きなのはR&Bで、『日本のジェームス・ブラウンになるぞ』って。反骨精神にシンパシィを感じてたのかも」
このころ、一つの転機が音楽スクールの先輩を通じて訪れる。作曲家の作った歌をレコード会社などに提案するときにシンガーの役割をする“仮歌”の仕事だった。
「同時に、歌詞を考える“仮詞”もセットで依頼されるようになるんですが1曲2千円のギャラは往復の交通費などで消えました。その仮詞が少しずつ評価され、そのまま正式な詞として採用されたり、バックボーカルの仕事などが入るようになるんです」
どんな仕事も貪欲に引き受けていくなかで、作詞作曲やボーカルディレクション(レコーディング監督)は途切れずに依頼が舞い込むことに気づく。
「そこが、自分の得意分野なんだろうなと。やがて楽曲コンペの話も舞い込むようになり、多いときで年間500曲くらい、コンペの歌詞を書いていました」
その努力が報われ、ついに作詞家デビューを果たすのは21歳のとき。Soweluの『to YOU』。寒い冬の朝、思いがけないかたちで自分の作品と出合った。
「バイトに入ろうと、渋谷の、あのスクランブル交差点に立っていたら、職場の店舗フロントの大画面に自分の作品がドーンと流れ始めたんです。その場で体中が震え、音楽を生業にする醍醐味を“知っちゃった”という感覚でしたね。ただ、その後も3年くらい生活は大変で、バイトも続けました」
朝から夕方までCDショップで働き、それからレコーディングスタジオに向かい仮歌の仕事。明け方近くに帰宅してコンペの歌詞を書いて、またバイトへ。
「そこに、週末は路上ライブ。エナジードリンク飲みながら、乗り切りました(笑)」
やがて徐々に仕事も増え、’09年の安室奈美恵のアルバムに歌詞が採用されたのを機に、業界でも彼女の名前が少しずつ知れ渡っていく。
しかし、本人は「まだジレンマを抱えていた」というのだ。
「15歳からプライドを持ってバンド活動で表に出ようとしながらうまくいかず、でも一方で裏方の作詞作曲家として求められている自分がいて……」
そんな歯がゆい思いを抱えているさなか、ポップス大国・スウェーデンの音楽事務所から声がかかる。現地の作曲家たちと組んで曲作りをする“コライト”の誘いだった。
「初めての土地、初めてのチームで曲を作る。明け方までみんなで仕事をして、それからクラブで踊ったり、人生でこんなに楽しいことって本当にあるのか、って」
そんな刺激的な日々を8日間、過ごすなかで知る。
「歌うことがアーチストになるすべてと思っていましたが、私には作ることそれ自体が楽しいんだと。雷に打たれたような衝撃でした」
2年後、バンドを解散して、スウェーデンの音楽事務所と正式に契約を交わし、海外での活動もスタート。そして再びのスウェーデン滞在中、一本の電話が。
「安室奈美恵さんとクリスタル・ケイさんのコラボ曲のコンペに参加しませんか」
ちょうど一時帰国直前の超多忙なさなかだった。しかし、日本に着くまでの10時間、機内でPCを開き、「この歌詞が誰かの背中を押せばいい」との思いを込めて一心不乱に歌詞を書き続けた。その数日後、「岡嶋さんの歌詞に決まりました」
それが、’15年9月発売の『REVOLUTION』。
「ああ、報われた。今までの悲しみや苦しみは、この歌詞を書くためにあったんじゃないかと」
同年12月に行われた安室奈美恵の全国ツアーの東京公演では、クリスタル・ケイが共演し、その観客席に岡嶋さんもいた。
「涙が止まりませんでした。自分の抱えていた濁った塊のような思いが、プロフェッショナルなアーチストさんによって、こんな美しい形でみんなに届くんだと。コロナ前で、観客のみなさんの地鳴りのような歓声とも相まって、これを境に、もう表とか裏とかいう迷いは、私の中からすっかり消えていました」
そして、確信する。
「作詞作曲こそ、私の天命にして天職。これを全力でやらないで、私は何をやるんだ」
【後編】BTS、Snow Manなどを手掛ける作詞作曲家で二児の母「キャンピングカーで子育て」する岡嶋かな多さんへ続く
画像ページ >【写真あり】バンドを組み、歌い続けた過去(他2枚)