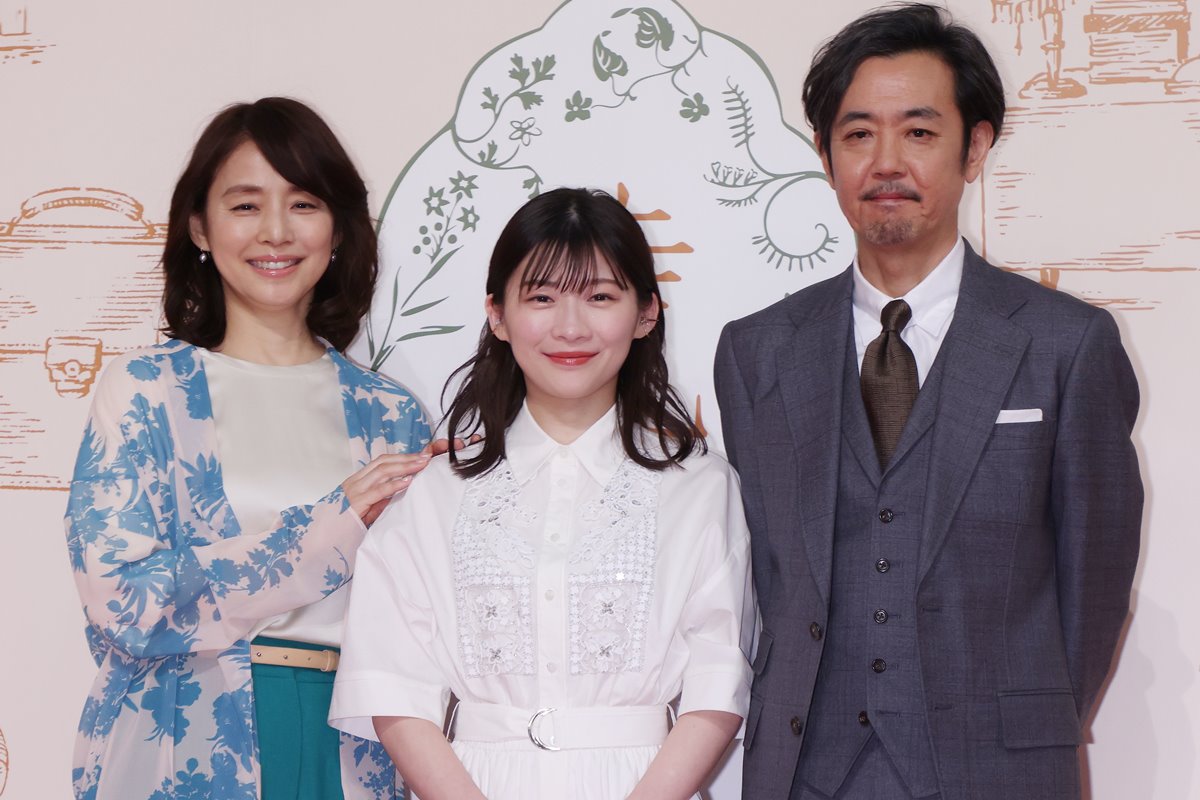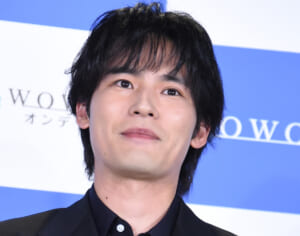■「自分で道を切り開くのではなく、結局は他人任せの他力本願の人生」
だが、当時の岡部はバイトが楽しくなりその仲間と遊んでばかり。
「ホンマに東京に何しに来たん?」
と、母親になった妻からそう言われても、
「当時は『やってるよ!』と答えてはいたけれど、でもそれは“やってなかった”と今は思いますね。“何か”が見つかってへん感覚はありました。標準語もでけへんし、芝居も下手くそでした」
厳しい母の庇護の下から外れた反動で、優しい妻に甘えすぎていたのかもしれないと振り返る。
「おかんも奥さんも、僕のためになんでもしてくれて。自分で道を切り開くのではなく、結局は他人任せの他力本願。僕の人生、出会った人らに助けられてるんです」
元ワハハ本舗の岩谷健司さんや、俳優・演出家の村松利史さん、またCMディレクター山内ケンジさん主宰の「城山羊の会」(’04年結成)と、現在にも続く芝居の仲間たちと出会ったのもこの時期だ。
「面白いとは何か?」に取りつかれるように、岡部は脚本作り・芝居に没頭していった。
「それまでの芝居は楽しい・軽い=面白いだけでしたが、このときは自分を突き詰めないといけなかった。それまで自分は、ずっと苦しみから逃げていただけやったと気づきました。芝居をやっていても誰にも褒められない。でもバイト先でなら『面白い!』と言ってもらえる。楽なほうへと逃げていたんです」
岡部が大切にしている、作家・町田康の言葉がある。
《面白いことはただ面白さだけでそこにあるのではなく、悲しみや苦しみとともにそこにある》
自らの家族との日常を脚本のネタにしたこともある。芝居へ精魂を注ぐ彼の舞台を観た妻は「むちゃくちゃ面白い!」と爆笑していたという。
「自分のこともネタにされても『こんなに面白いのは世に出るべきやで!』と言ってくれた。それ以降は、ずっと『面白い』と言ってくれています」
役者としての修業時代、着実に力をつけていくのと反比例するかのように、夫・父としての役割は遠く、薄くなっていった。
「正月に『サイゼリヤ』にこもってネタを作っていたこともあります。それまでは途中でいろいろとやめてきた僕が、それでも芝居をやめなかったのは、苦しいけれど“面白い”からでした」
幼子を抱え、美容師の仕事も休んでいた妻は和歌山の岡部の実家で暮らし、別居する時期もあった。妻は東京に戻っても、生活費を稼ぐためパートの日々。時給のよいラブホテルで勤務したことも。その間も夫は家に帰ってこない。
岡部はこのころ「子供と過ごす時間はほとんどなかった」と呟く。
やがて、息子が6歳になるとき、妻は一つの決断を下す。
《離婚してください。子供の養育費はちゃんと払ってください》
「33歳で息子を産み、当時は高齢出産といわれた時代でした。美容師の職もあるし、将来のことを考えて決めたんだと思います」
妻と息子は、地元・和歌山へと帰っていった。
30代半ばを迎えた岡部にも変化が訪れていた。
警備員、テレホンアポインター、デリバリー業とバイトは続いていたが、芝居での新たな出会いを求め、小劇場のオーディションを受け続けるようになった。
「落ちてもいいから以前と違うことをやりたい衝動にかられました」
離婚したことで他力から自力へと“自立”したのかもしれない。
芝居ではさらに“面白い”を追求するようになっていた。
「喋るのが下手なので、飲みに行って相手に向かい『お前、おもろない!』と言いすぎて、ケンカになることもありました。30代は尖ってたんです(苦笑)」
悩んでいた岡部は、城山羊の会で出会い名脇役として活躍していた女優の深浦加奈子さんの言葉に助けられることになる。
あるとき、岡部は深浦さんに「自分は普通で、おもろないんです」と嘆くと「そんなことで悩んでいるの?」と一笑され、こう答えてくれたという。
「『普通をちゃんとやりなさい。とがっているだけじゃ駄目だし、作ってやるもんでもない。あなたのままをちゃんとしたら面白い。普通をちゃんとできる人って、あまりいないんだから』と。作らんでいいということを言われましたね」
彼女の助言によって岡部の旧来の考え方に風穴が開き、ようやく壁を乗り越えられるように──。
深浦さんは’03年に結腸がんを患っており、’08年天国へと旅立った。