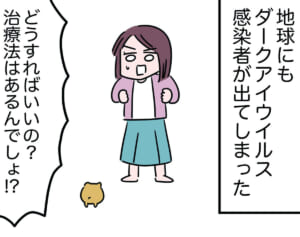<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>
「…ごめんなさいね。普通はこんな話をすると笑われてしまうんですけれど…。ご主人はなにか思い当たることがおありですか。もしかすると、なにか見ました?」
いきなり核心を衝いた。唐突なだけにはぐらかしようがないはずだ。目の前の夫は、座っていなければ倒れたのではないかと思うくらいのけぞり、その顔は明らかに恐怖に引き攣っている。期待した以上のリアクションだ。
「ご主人、お話ししていただけませんか?」
明美と亜里沙が子どもたちの霊を見たという辺りから、夫の態度は見ていて気の毒なほどに動揺し始めた。話せと言われ、動揺はさらに高まり…左右の手を握っては離し握っては離しを繰り返している。
「…妻が…。理沙が、娘が戻って来たって言うんです」
一週間ほど前の深夜。会社から帰って食事を済ませた夫が、いつものように理沙のDVDを繰り返し観る静江を半ばうんざりとした気分で眺めながらウィスキーを飲んでいるときに事件は起きた。

理沙を亡くして以来、静江は日を追って正気を失っていった。娘の告別式を終えて家に戻った静江は、その日から寝室から出ることが無くなり、一日中ベッドに横たわって過ごすようになっていた。
やがて起き上がれるようになると、今度は日がな一日理沙のDVDを観ては、夕方になると庭先に立って通りすがりの子どもたちに声を掛けるようになってしまった…。最初のうちこそ、近所の人も、不幸に見舞われた可哀そうな母親ということで済ませてくれていた。しかし、静江の行動は日を追ってエスカレートし、ある日理沙と同じ年頃の女の子を無理やり家に連れ込もうとして以来、静江の存在は事件化した。
今では子どもたちの登下校時には、どこからともなく父兄が現れ、静江の家の前に立つようになっている。その頃には、静江は理沙の位牌に手を合わせることも無くなり、愛娘の仏前に線香を焚くのは夫の仕事になっていた。それでも時が経てば、時がその最大の効力をもって妻の悲しみを和らげてくれさえすれば、また以前のような生活が戻ってくると信じて夫はひたすら耐えていた。
半年が過ぎようとする頃には、かつては職場の同僚も羨むほどチャーミングだった妻が、見る間に疲れ果てた老女と化し、夫が仕事に行っている間、ずっとDVDばかりを観て過ごす毎日になっていた。
そんな、日々の買い物にも出なくなった静江が、誰に聞いたか自ら訪ねて行ったのが、あの日のリーディングだ。明美に聞くまで、そんなことも知らずにいた夫は、毎日毎日、相も変わらず呆けて過ごす妻を暗澹とした気持ちで見守っていた。
そうして一年が過ぎ、様々なことを諦めかけた頃に事件は起きた。
闇夜に聞いた歌声
その夜も、いつものように理沙のDVDを飽きもせず眺める妻を、少し離れたダイニングテーブルでウィスキーの入ったグラスを片手に眺めていると…。突然、大型の液晶画面が真っ暗になった。映らなくなる直前の画面には、50メートルを一着で泳ぎきった理沙が、誇らしげに頬を膨らませてプールサイドに上がってきて見せた満面の笑顔が映っていた。数え切れないほどに繰り返し観たシーンだが、それでも見蕩れてしまう愛娘の笑顔が消え、静江はまるで理沙が死んでしまったときのようにうろたえ始めた。夫はそんな静江を見るに見かねて、リモコンを手にあれやこれやと操作してみるのだが一向に映らない。半ば諦めて振り返ると、ソファーから立ち上がった静江が、この一年見せたことの無い喜色を浮かべて真っ暗なガラス窓の向こうを見つめていた。
「そうしたら彼女が、妻が、子どもの声がするって外に出て行ったんです」
「かなり遅い時間ですよね」
「はい。彼女は四六時中観ているんだと思いますけど、私はもう飲んでいましたから…深夜の12時は回っていたと思います。で、危なっかしいんで追い駆けたんですが、外に出てもどこにも見当たらなくて…。なんだか心配で…。でもしばらくして、改めて辺りを見ると、なんと道路を挟んだ向かいの真っ暗な田んぼの中をこいつが走ってるんですよ。追い駆けてなんとかおとなしくはさせたんですけど…。そのとき、確かに私にも子どもの声が聞こえたんです。それも、なんだか歌っているような感じの…」
「歌って…。もしかして、こんな感じじゃありませんでしたか。“一で俵踏まえて 二でにっこり笑ろて…”」
「あっそれです。…今まで気がつかなかったけど、それって亥の子の数え歌ですよね。…どこかで聞いたことのある感じがしてたんだよな…」
都会から嫁いできた静江と違い、地元に生まれ育った夫には、子どもの頃に歌い歩いた記憶が鮮明に蘇っていた。
「ほら、…理沙ちゃんが歌ってる…。理沙ちゃん。…理沙ちゃん、ママよ。ママはここにいるわよ…」
今の今まで、夫の横で他人事のように微笑みながら話を聞いていた静江が、明美が数え歌を口ずさんだ途端に立ち上がり、あらぬ方を指差しながらふらふらと歩き出した。しかしその姿は、さきほどまでのしっかりとした足取りではなく、先日のリーディンのときよりも危なっかしい、今にも辺りに身体をぶつけそうな歩き方だ。さっきまでの、しっかりとした足取りが嘘のようにふらつき、言葉つきもだらしなく独り言のように力が無くなっている。ただ一つ、目だけが油断無くクルクルと瞬時に焦点を変えていくその様は、まるで人では無い、小動物か昆虫のような、何かに取り憑かれているとしか思えなかった。
「大丈夫、大丈夫だから…。ここに座っていなさい」
すぐに立ち上がった夫が、静江の肩を抱いてソファーに座らせようとしている。これでは、おちおち仕事にも出掛けられないはずだ。やっと座りなおした静江は、今度は明美と健作を舐めるような目で油断無く窺っている。その目つきは、まるで獣のようだった。
「あのぅ、お線香あげさせていただいていいですか?」
「…あぁ、ありがとうございます。…では、こちらにどうぞ」
案内されたのは、玄関から続く短い廊下の突き当たり。北向きの小さな和室の真新しい仏壇だった。毎日お奉りしているのだろう、線香の香りが漂う綺麗に整った仏壇には、こぼれるような笑顔の少女の写真が飾ってあった。改めて見ると、写真の少女はとても可愛く、その可憐な唇を半ば開いてみせる笑みが神々しくすらある。
邪気の巣食う仏壇
灯明の火を線香に移して香を焚き染める。チンの音に両の掌を合わせると、やがて五感が緩慢な緊張に埋もれていく。
始まった。閉ざした五感に代わって、脳裏に、まるで目を開いて見るような鮮明な映像が映し出される…。
最初に出てきたのは、真新しい仏壇に巣食う…薄気味の悪いドドメ色の塊。映し出された仏壇は、買ったばかりのあの真新しさが嘘のように古ぼけ、観音開きの扉は片方の蝶番が壊れて見苦しくぶら下がっている。薄茶色に苔むした位牌の周囲には、ぶつぶつと緑色の汁を吹く何体もの塊が、まるで老いた蛇のようにとぐろを巻いていた。
これほどの邪気がどこから現れたのか…。毎日ここに座るだけでも相当なダメージがあるはずだ。目も鼻も無い、赤黒い口だけの鎌首をもたげる塊に向かって、明美は素早く右手の人差し指と中指で剣を作ると真言を唱えながら一つずつ消していく。消される瞬間、腐りかけた蛇のような塊は、大きく赤黒い口を開き苦しそうに身悶え、嗅いだだけでも体調を壊しかねない強烈な臭気を吐き出しいる。
しかし、それにしてもこれほどの邪気がひとつところに寄せているなど、これひとつとっても只事ではない。消しはしたが、邪気を生む根本を絶ったわけではない。明美の唱えた真言の威力が消えれば、またぞろどこからともなく現れてとぐろを巻くに違いない。
明美は、そんなことを考えながら、なんとも遣る瀬無い気持ちで真言を唱え続けた。すると、やがて位牌の中ほどにボウと小さな光が明滅し、その淡い光の中に理沙の姿が現れた。

『…助けて。…ママを助けてあげて』
『理沙ちゃん? 理沙ちゃんなのね。…あなた、今どこにいるの?』
『怖いところ。…ママを助けてあげて…』
『怖いところって、どこなの? どこにいるの?』
『お願い。ママをた・す・け・・て・・・・』
消えた。後はもう、明美がいくら声をかけても返事は返ってこなかった。
「ありがとうございます」
長い瞑目の後、それでも立ち上がろうとしない明美に、静江の夫が声を掛けてきた。
「お恥ずかしい話ですが、去年の夏に理沙を亡くして以来、私たち夫婦はおかしくなってしまいました。色々とお聞きになっていると思いますが、…特に妻の落胆は酷かったです。それでも、時間が経てば持ち直してくれると信じていたんですが、持ち直すどころか、最近はこの仏壇の前にすら座ろうとしません。挙句の果てに『理沙は生きている。もうすぐ帰ってくるから、こんなもの片付けなきゃ』…とまで言い出す始末でして…朝目を覚ますと、仏壇が片付けられてたりするんです」
すげない診断
一人娘を亡くし、すっかり正気を無くした静江は仏壇の前にも座ろうとせず、毎日夫がお供え物を換えお線香を焚いていた。理沙が亡くなった当初は泣き暮らしていた静江が、しばらくして時折笑顔を見せるようになったかと思うと、小学生の下校時間になると理沙と同じ年頃の女の子を見付けては声を掛け、家に連れ込もうとするようになった。そうなるともう、一人娘を亡くして悲しみに浸る哀れな母親は目の離せない危険人物と化してしまい、おちおち外にも出せなくなったらしい。ついには静江の実家から義母に来てもらい、話し合った末に診察を受けることになったのだ。
そうして先日、すでに一人では足元も覚束ない静江の肩を抱えるようにして尋ねたのはオフィス街の外れにある心療内科だった。
その日、真新しいテナントビルのクリニックでは、いかにも手入れの行き届いた、金をかけていそうな女医が静江を待ち受けていた。夫は事前に、叶うならば女医がいいだろうと、このクリニックに予約を入れていた。およそ30分の簡単な診察では、静江自身による自己紹介と20問の問診とパズルのような何枚かの絵を見せられた。後は夫から、理沙に起きた不幸な事故から現在までの家庭での様子を聞いて終わり…。
診断結果は「統合失調症の疑い有り」。憐れむような口調で女医が口にしたのは、極端に言葉数が減り会話が成立し辛くなることと、妄想と幻覚が生活の中心に位置する鬱症状には、挙句に自殺衝動に駆られる場合が多く見られるという、先ほどの問診で夫が語った内容に留まるのみの結果だ。
最悪だった。恐れていた通り、静江は妄想と幻覚の中に生きていた。そして、しばしば自殺衝動に駆られてしまうのだ。
「…投薬による治療をいたしますが、治療以上に、お家の方には注意を払っていただく必要があります」
やたらと鼻につく高慢を振り撒きながら、女医は事も無げに言い放つ。言われるまでもなく、そんなことはわかっている。すでに目が離せなくなってきたから連れてきたのだ。
以来、朝・昼・晩と食後は薬を飲ませている。
静江がおかしくなったのは、…理沙を亡くした、その知らせを受けた瞬間だった。しかし、夫は随分と日が経つまで気付かずにいた。まさか妻がおかしくなっているとも知らず、ただ、娘を亡くして悲嘆にくれているものとばかり思っていたのだ。

最初の頃は、理沙のことを話そうとすると呂律が回らなかったり、話の筋立てがちぐはぐになったりする程度だった。しかし日に日に症状は深刻になり、いつしか理沙の話ではない夫婦の日常的な会話でも、気持ちが高ぶると呂律が回らなくなり始めた。やがて呼吸が困難になったり手足が痺れたりという過呼吸発作を起こすようになると、身体のどこかしこが常に痛んで眠れなくなったりと、まるで鬱のような症状を呈してきたのだ。
そうして夫は、上司の勧めもあって休職し、妻の介護ならぬ監視をする日々を送っている。
「そうですか。…でも、本当に残念。後は、一日も早く成仏させてあげなければならないですよね」
夫はひとしきり病院で告げられた診察結果を口にしたが、すでに明美の興味はそこにはなかった。なぜなら、静江の病は西洋医学で…ましてや心療内科の手に負えるものでは無いからだ。
「…成仏って…。理沙は成仏できてないんですか? どういうことなんです?」
さっきまで悄然としていた男の目に、頑なな灯りが点っていた。
魂
人体を構成する肉体とは異なり、精神活動を司り、五感による認識を超えた存在として、魂(心etc)が存在するとされる。古今東西、様々な宗教において、その存在は最重要視され、有史以来、宗教学・民俗学・文化人類学などが研究を続けてきた。現代においても、量子脳理論や素量域理論など科学的アプローチによる解明が試みられている。甦りや輪廻転生を考える時、実態としての魂の存在に思いを馳せるが、未だ解明には至っていない。
ただ、以前真印さんは魂の存在について、妊娠時のツワリを例に興味深い話をしていた。真印さんによれば「ひどいツワリに悩まされる方がいますが、それは仕方のないこと」という。「妊娠によって崩れたホルモンバランスの影響などもあるのしょう。でも、それにもまして、ツワリによって心身に不調を来たす最大の要因は、一つの肉体に異なる2つの魂が宿っているからなんです」(真印さん)。胎児の肉体を構成するDNAは、もちろん両親から受け継いだもの。しかし、真印さんは「そこに宿る魂は遺伝とは無関係のまったくの別物」という。「2つの魂を同時に体内に内包した女性が苦しいのはある意味、当たり前なのです」というのだ。未だ何も解明されていない魂。だが、彼女のこの一言にも、その存在を解き明かす糸口があるように思えるのは筆者だけだろうか。