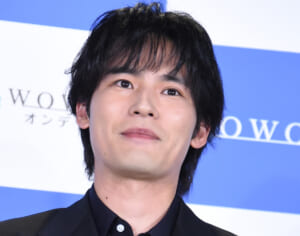世界の難題の最前線で飛び回っている、報道キャスター・長野智子さん(56)。現在、『サンデーステーション』(テレビ朝日系)の報道キャスターに加えネットニュースサイトの「ハフポスト日本版」編集主幹。並行して国連UNHCR協会(国連難民高等弁務官事務所の日本における公式支援窓口)の報道ディレクターとしての活動にも心血を注いでいる。
「’00年に鳥越俊太郎さんの『ザ・スクープ』(テレビ朝日系)に参加した私は、9.11後のパレスチナに飛びました。その後も各地の難民キャンプを取材して、痛感したんです。難民、特に子どもたちを支援することは、彼らのコミュニティの未来を救うことであり、いま世界が直面している問題を根本から解決することにもつながるのではないかと。そうした思いから、国連UNHCR協会の活動に関わるようになりました。出会った難民一人ひとりが、私たちと何もかわらない、生きることを選んだ強い意志を持つ人たちだということ、もっともっと多くの人に、難民支援の意義を伝えたい。来年の『TOKYO2020』にはリオに続き、難民選手団が来日することが決まっています。自分の国の国旗を掲げることのできない彼らを、日本の皆さんに応援していただけるよう国連UNHCR協会のサポーターを増やすことが、私の役割だと思っています」
長野さんは日本では数少ない、ニュースの現場を知り、現場を語ることができる硬派の報道キャスターだ。
長野さんがフジテレビに入社したのは’85年。もともとやりたかったのは報道の仕事だったが、翌年、配属されたのは報道とはかけ離れたバラエティ番組『オレたちひょうきん族』。山村美智子さん、寺田理恵子さんに続く3代目ひょうきんアナになった長野さんは、休むヒマもない忙しさに追われるようになった。
’89年、27歳で商社員と出会い、翌年にはスピード婚。結婚したらいまのままの仕事は続けられない。そんな思いの末に、長野さんは寿退社する。退職後は、フリーでアナウンサーを続けた。夫のNY転勤が決まったのは32歳の冬だった。
「夫は『日本に残って、仕事を続けていい』と言ってくれましたが、私は本気で報道に向き合うなら、これが最後のチャンスと思った。覚悟を決め、ゼロから挑戦する自分を選ぼうと思ったんです」
レギュラー番組をすべて降りて、NYへ渡った。ニューヨーク大学の大学院でメディア環境学を専攻。同時に子どものことを考え始めた。
「NYにいる間に子どもをつくりたいなと、漠然と考えていました。でも、できないなぁくらいで。気持ち的には、まだ、まったく切迫していませんでしたね」
『ザ・スクープ』のキャスターの声がかかったのは、37歳のときだ。子どもがほしい気持ちから、迷いがあった彼女の背中を押したのは、夫だった。
「何のためにNYに来たの? 報道をやりたいからじゃないの?」
’00年6月、夫をNYに残して帰国。『ザ・スクープ』に参加する。その1年半後に9.11が勃発。長野さんは、事件の背景にある中東問題を取材するべく、パレスチナへ飛んだ。その後も現場第一主義で取材を続け、経験を積んだ。
一方、結果が出なかったのが、妊娠だ。気がつけば40歳が目前に迫ってきていた。
「NYから帰ってきて、不妊治療に通い始めました。しかし、仕事も忙しかったので、ヘビーな治療は’04年からでした」
計画妊娠、人工授精、体外受精と、治療は徐々にキツくなる。精神的にも追い詰められた。子どもを産める限界が近づいているという焦り、妊娠しないまま生理がなくなる恐怖感。女に生まれたのに、動物としてどうなの? 生きている価値があるのかしら――。そんな思いまで湧いてくる。
「自分で追い込みすぎていたかもしれません。’05年あたりが、精神的にいちばんひどくて、夜中に過呼吸になっちゃって。神経内科に行って、薬を飲めば、治るんです。でも、その薬を飲んでいる間は、妊娠するわけにはいかない。矛盾のスパイラルでしたね」
報道キャスターとしてのデビューが遅かったこともあり、せっかくつかんだキャリアを失いたくない一心で、体のことより仕事を優先させがちになっていた。
「体外受精って、相当しんどい。卵子を採るのも、ものすごく痛いので。痛み止めを打って現場に行くのですが、途中で薬が切れて、取材中でも収録中でも、激しい痛みに座り込んでしまったり。夢にまで見た仕事なのに、なぜ、治療で痛い思いをしているのか。でも、治療をやめたら、子どもは持てないし……」
ジレンマに苦しみながら、長野さんは誰にも相談できなかった。つらい思いを8年間、1人で抱えてもがいた。
「さすがに47歳になって、『もう最後だよね』としないと、キリがなかった。その採卵で、なんと卵子が20個も採れて。それでも、受精しなかった……」
医師に「これで最後にします」と、告げた帰り道、涙があふれて止まらなかった。
「周囲の方からの慰めの言葉にも、救われない思いは、正直ありました。子どもがいる人がうらやましくて、親子連れがいる場所は避けちゃったり……」
そんなとき脳裏をよこぎったのは、グチャグチャに破壊されたパレスチナの町で出会い、親しくなったネタさんの言葉だ。
「彼女は、イスラエル人でありながら、『このまま闘い続けてはいけない』と、パレスチナ側に立って市民活動をする勇敢な女性でした」
体外受精にトライしてはうまくいかないというサイクルを繰り返していたころ、ネタさんに再会。そのとき彼女は4人の子どもを産み、育てていた。「子育てって、すごく楽しい」と、言うネタさんに、長野さんは打ち明けた。
「もしかしたら、私は(子どもが)できないかもしれない……」
ネタさんはこう言った。
「私は幸せだけど、市民活動はできないわ。いまの私が救えるのは、4人の子どもだけ。でも、智子。あなたはこうして取材をして、日本で伝えることで、たくさんの子を救うことになるの。子育てしている私と仕事をしているあなた。これってイーブンなんだよ」
長野さんは、その場で大号泣したという。治療を断念した直後、新番組『報道ステーションSUNDAY』のメインMCに抜擢された。’11年10月のことだ。
「グジグジ悩むヒマもないほど忙しくなりました。大きく失ったものがあったからこそ与えられたのかなとも思いました」
実際、紛争地に何度も足を運び、危険地域で取材をするのは、子どもがいたら難しかったかもしれない。
「いまでも子どもを持ちたかったと思うけれど、自分なりにイーブンの生き方もできるかもとようやく思えるようになってきた。ネタのあの言葉がより重く、価値あるものとして、私に響いてきています」