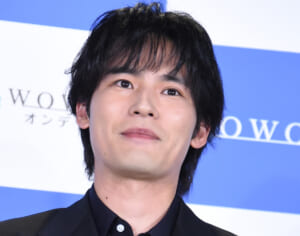若き乙女の心をつかんだ「おっちゃん」とは、笑福亭鶴瓶さん(70)。
「すぐ調べて、落語家してはるんやと知って。それまで落語の『ら』の字も知らんかったんですけど、落語会にも行き始めて」
追っかけファンになって、好きが高じて寄席でバイトもした。
「初めてお会いしたときは、相変わらず内気でしたから、小声で『好きです』言うんが精いっぱい。言われた師匠は、苦笑いしてはりました」
熱意は実り、やがて鶴瓶さんからごはんをご馳走になったり、落語会に無料で入れてもらえるようにも。こうして、通い詰めた寄席で、二葉さんはいつしか、落語そのものの魅力にハマっていった。
「見れば見るほど落語って面白いな、自分もやってみたいなと。それに漫才やコントと違って、古典なら、ネタを一から創作する頭脳がいらないのも魅力でした(苦笑)」
じつは二葉さん、幼いころからクラスの“いちびり(お調子者)”に憧れを抱いていた。
「いてるでしょ、先生に怒られてもアホなことして、いちびれる子。たいがい男子ですけど。『俺、砂場の砂、食えるしな〜』とか言うて。アホやなと思いつつ魅力的に見えた。私こそ“ほんまもん”やのに、内気が邪魔してアホをさらけ出されへんのが悔しかったのかも。憧れは大人になってもありました」
寄席に通ううち、ここなら思いっきりアホができる、そう思えた。
「堂々とアホをやって、皆が喜んで見てくれはる、『これや!』って」
もちろん、女性の自分にはハードルが高いこともわかっていた。
「長年、男の人が演るために研究されてきたものですから。女性が演じることでお客さんが違和感を覚えてしまったら、それは笑いにつながりにくいんやろなと。なんとなくわかってはいました」
でも、と二葉さんは続ける。
「この人、頭いいんやろな、と思う落語家さんが演じるアホにも、私は同じように違和感を覚えてた。なんか無理してはるな、と。でも、私はほんまもんやぞ、私なら純度の高いアホを、無理なく演れるはずや、そうも考えたんです(笑)」