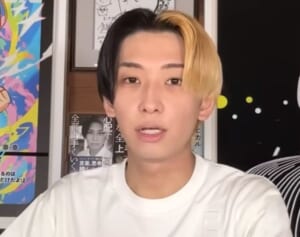■バリアフリー上映会のスタッフを経て映画祭の主催が人生の転機に――
「早稲田松竹のバイトを続けながら、自主映画監督が主宰していた異業種交流会に加わりました。そのなかで立ち上がった企画が、目の見えない人に向けてのバリアフリー上映会でした」
チャップリンのサイレント映画の名作『街の灯』の活弁付き映画会の実現に向け、平塚さんもスタッフのひとりとして参加。
「私はそれまで目の不自由な方とはお会いしたことがなく、正直、当初は、視覚障害者に映画の話なんてしたら怒られるんじゃないかという偏見もありました」
当事者の生の声を聞こうと、聞き取り調査を始めたところ、
「お会いするみなさんが、『ぜひ映画館で観たい』と強くおっしゃって。それまでの偏見や意識を180度転換させられるんです」
この上映会の企画は諸事情で流れたが、平塚さんは独自にさらなる調査を進める。
「すると、アメリカでは100館ほどのバリアフリーの映画館があって、公開初日から副音声と字幕付きで、『タイタニック』や『スター・ウォーズ』のような超大作を上映していました。レビュー投稿までするブラインド(視覚障害者)の人もいると知ることは、すごい追い風となりました」
’01年春、バリアフリー映画鑑賞推進団体「City Lights」を設立。シティ・ライツの名称は、もちろん敬愛するチャップリンの作品から。同時に、音声ガイド研究会をスタートさせた。
音声ガイドとは、目の見えない人が映画を楽しむときに、耳から情報を補足するもの。たとえば誰もが知る『ローマの休日』で、オードリー・ヘプバーン演じるアン王女が登場するシーン。スクリーンでは王女が移動するだけでセリフがないときも、音声ガイドでは〈側近を従えたアン王女が大使のエスコートで入場する〉といった解説が入る。
この研究会をスタートしてすぐに、あるリクエストが届いた。
「私たち視覚障害者も、1年とか2年遅れじゃなく、今公開されている映画が観たい。ぜひ『千と千尋の神隠し』を観てみたい」
話題作を早く観たいと願うのは誰もが同じと思った平塚さんは、まず映画館と交渉し、続いて6人の晴眼者を集めて視覚障害者とマンツーマンで、耳元で解説する“こそこそガイド”による同行鑑賞会を実現させた。
この方式ではまわりの客の迷惑になることや鑑賞人数が限られるという課題もあったが、
「歌舞伎のイヤホンガイドのような仕組みはどうだろう。FMラジオの電波を使い、イヤホンで解説を聴くようにすればいいんだ!」と思いついた。このラジオを使った同行鑑賞会の評判が口コミでも広がり、やがて200人規模の鑑賞会となる。
「多くの映画館にお世話になりましたし、映画を観たいけれど観られない人がこんなに大勢いることを社会に知ってもらう大切な時期だったと思います」
やがて、作品を送り出す側にも変化が生じる。’06年公開の山田洋次監督作品で、木村拓哉が盲目の武士を演じた『武士の一分』。
「製作委員会がバリアフリー版を作り、音声ガイド付きで上映されたんです。メジャーの松竹のお正月映画に音声ガイドが付いたのは、私たちにとって映画史に残るセンセーショナルな出来事でした」
さらに’08年からは、シティ・ライツ映画祭を主催していく。
これが人生の転機となったのが、当時は石川県で点字図書館に勤務していた全盲の田中正子さん(51)。
「’10年春に第3回シティ・ライツ映画祭のことを知りました。『雨に唄えば』と『虹をつかむ男』の2本立てで、どちらにも音声ガイドが付くと知り、どうしても体験してみたくて、小松空港から飛行機に飛び乗っていました」
映画を観終わったあと、田中さんは心地よい衝撃に浸っていた。
「こんな夢みたいな体験ができるんだ、って。それまでもテレビで『タイタニック』を観て感動したつもりでいましたが、実は何もわかっていなかったんですね」
こうした声に後押しされ、平塚さんは、いよいよ常設のバリアフリー映画館づくりに動き出す――。
【後編】目や耳が不自由な人でも誰でも一緒に楽しめる「日本で唯一のユニバーサルシアター」を誕生させた女性へ続く
(取材・構成:堀ノ内雅一)
画像ページ >【写真あり】盲導犬がいるのは普通の光景(他4枚)