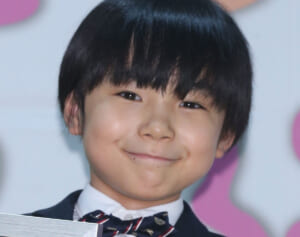『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『フェイクマミー』(ともにTBS系)、『終活シェアハウス』(NHK)、『新東京水上警察』『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』『小さい頃は、神様がいて』(すべてフジテレビ系)……。今期だけでも数え切れないほどのドラマを担当している、大人気フードコーディネーターのはらゆうこさん。彼女が“料理”に目覚めたのは、幼少期に遡る。
出身は埼玉県吉見町。両親と弟、祖父母、曽祖父、伯父までが一つ屋根の下に暮らす「まるで漫画のような大家族」。その中心には、料理のにおいがいつも漂っていた。母の本棚には料理本がずらりと並び、幼いはらさんはページをめくっては「おいしそう……」とうっとりする子どもだった。
母方の家系には料理上手が多く、山形の祖父はそば打ちの名人、祖母は魚料理を得意とした。
「家の食卓には赤飯や手打ちうどん、天ぷら、けんちん汁が当たり前に並んでいて、今思うとすごくぜいたく。夏に母の実家へ行けば、祖母が魚のさばき方や漬物の作り方を教えてくれました」
料理への興味は小学生のころにはすっかり芽生えていた。偏食の弟のために台所に立ち、友達と「お料理クラブ」を結成し、作る楽しさにのめり込んでいく。
「弟は野菜が全く食べられなくて、祖母の料理にも手をつけない。仕事から帰ってきた母が、弟のためにもう一品作る姿を見ると、何とかしてあげたくて。焼きそばや簡単な炒め物を作ったら弟が食べてくれて、母もすごく喜んでくれたんです」
高校を卒業するころには、心はすでに料理の道へ傾いていた。しかし、調理師学校への進学は親に反対され、短大へ。家庭科の教員免許を取ったものの採用試験に落ちてしまい、非常勤職員として教育事務所で働き始めた。
「父は高校の教員で、勤めるのは“教員か公務員”という考え方で、『絶対つぶれない』が口癖。母は母で『正社員になりなさい』という人でした(笑)」
結局、その言葉どおり公務員になった。安定した地元の役場に勤める日々。27歳で同級生と結婚し、人生は順調に見えた。
ただ、役場で住民と向き合う仕事は、時に心に重くのしかかる。
「30歳までには辞めよう」
そう、自分のなかで区切りをつけていた。転機となったのは、帯状疱疹で1カ月半の休職をしたことだった。
「そのとき気づいたんです。好きなことをやらないと、心も体ももたないって。夫も背中を押してくれましたし、両親も、私がずっと悩んでいたのを知っていたので受け止めてくれました」
さらに、親しい友人が若くして亡くなったことも大きかった。「やりたいことをやらないまま終わりたくない」
そんな思いが胸の奥で強く渦巻いた。やりたいこと。それはやはり料理だった。公務員を続けながらも、図書館に通って料理本を読みあさり、情熱を静かに燃やし続けていた。そしてついに、赤堀料理学園の門をたたく。長く胸にしまい込んでいた“好き”が、ようやく動き出した瞬間だった。料理人という選択もあったが、はらさんの目に留まったのは、料理本の著者紹介に記された「料理研究家」「フードコーディネーター」という肩書。その文字に、自分の未来を重ねた。
赤堀料理学園を選んだ理由は、「いちばん厳しそうだったから」。浮ついた夢を語る空気ではなく、地道に技術を積み重ねる雰囲気に引かれたという。こうして、公務員を続けながら週に1回料理を学ぶ生活が始まった。
1クラスは30人ほど。料理研究家を目指す仲間の存在に刺激を受け、半年のカリキュラムを進めるうちに、「好きなことで生きられるかもしれない」という希望が芽生えていった。ただ、食品メーカーの商品開発など進路は幅広いものの、短大卒の採用枠は狭く、書類審査で落とされることも多い。「就職活動に踏み出す勇気は持てなかった」はらさんを支えたのが、赤堀先生の言葉だった。
「この世界は、忍耐強く技術を積めば仕事はある」
役場を退職し、翌日から赤堀先生のアシスタントとして働き始めた。初日の朝、突然告げられたのは予想外のひと言だった。
「ドラマの撮影現場に行くよ」
連れていかれたのは、松本潤主演の『バンビ~ノ!』(日本テレビ系)の撮影現場。リストランテを舞台にした本格的な調理シーンが続く現場で、右も左もわからないまま、怒濤のスピードで作業が進んでいく。
「料理教室のお手伝いしか経験がなくて、現場はこれが初めて。『16時からこのシーンで使うから温めて』と言われても何を準備すればいいかわからない。『ドライ(カメラを使用しないリハーサル)を見て』と言われても、『ドライって何ですか?』という状態。先生には、『ボーッと突っ立ってないで動いて!』と叱られるし、とにかく、目で見て覚えるしかありませんでした」
現場に慣れてきたころ、忘れられない大失敗も経験する。ドラマ『おせん』(日本テレビ系)で、ふろふき大根の仕込みを任された際、物語の重要な設定があったにもかかわらず、その部分を再現せずに準備してしまったのだ。
「本番直前に気づいて血の気が引きました。大急ぎで作り直しましたが理想の仕上がりとはほど遠く、先生にも厳しく叱られました」
原因は資料の読み込み不足。成功よりも、こうした痛みが自分を育ててくれたと今では思う。アシスタント時代、褒められた記憶はほとんどなかった。
ずっと「勉強しなさい」と言われ続ける日々。変化の激しい世界で求められるのは、体力と根気、そして折れない心。「落ち込んでいる暇はない。前に進むしかない」という感覚が自然と身についた。
そんな折、支えてくれていたはずの夫が徐々に不満を抱え始めていた。
「僕との人生はどうしますか? 子どもは?」
多忙で充実した日々のなかで投げかけられた問い。さらに夫の海外赴任が決まり、両親は「女は家を守るべき」という価値観の持ち主。一度、フードコーディネーターの仕事から離れて、人生を見直す選択をするほかなかった。
しかし、主婦として過ごしていても、料理への思いが消えることはない。むしろ、「やっぱり現場が好きだ」という思いは膨らむばかり。そんなとき、知人からドラマの単発の仕事を打診され、再び心に火がついた。復帰を決めてからは「仕事をください」と積極的に頭を下げ、少しずつ撮影の仕事が戻ってきた。
ところが、フリーになって間もなく、初心に立ち返らされる出来事が起こる。ある現場でカレーを盛り付けたとき、その皿を見た女優から鋭い一言が飛んだ。
「台本を理解していますか?」
ハッとした瞬間だった。読み込みが浅く、役の背景まで理解できていなかったのだ。満足に食べられなかった子に「たくさん食べてほしい」と願う母の気持ち……、その心情をつかんでいれば、カレーを山盛りにしていたはず。「都会のお母さんじゃないのよ」その言葉は、はらさんの胸に今も残っている。
撮影で使う料理は、おいしそうに見えるだけでは足りない。その一皿が役の心情とどう結びつくのか。その意味を読み取ることが何より大切なのだ。
「そのとき初めて、料理で芝居を支えるということの重みを理解しました。あれ以来、台本の読み方がガラッと変わりました」
一つの皿が物語の一部になる。はらさんは、自分の仕事の本当の役割と責任に改めて気がついた。
『じゃあつく』『ふてほど』『VIVANT』料理を担当したドラマ500本以上のはらゆうこさんが明かすドラマ飯の舞台裏へ続く
画像ページ >【写真あり】カレーライスの盛り付け方で女優に叱責されたことも(他1枚)