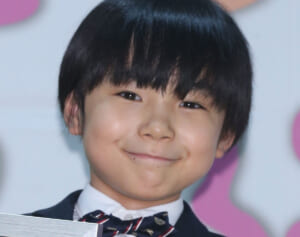「台本を理解していますか?」女優からの叱責…。はらゆうこさんが大人気フードコーディネーターになるまでの茨の道から続く
「いま、食べたね~?」
「今日は“消え物”があるから(朝ごはんを)食べないで来ました!」
スタジオに柔らかな笑い声が広がった。カットがかかった瞬間、つまみ食いをする永瀬矢紘(8)に草彅剛(51)がすかさずツッコむ。ほんの短いやり取りなのに、現場の空気がふっと和らぐ。
ここは、ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』(カンテレ・フジテレビ系)の撮影現場。草彅が演じているのは、幼い息子と静かに暮らすシングルファーザーだ。この日の撮影は、父子の朝食のシーン。草彅がフライパンで卵とウインナーを焼き、皿へと移す。そんな何げない所作にも、父子の生活感がにじむ。そのリアルさを支えているのが、スタジオの隅で手を休めることなく働く一人の女性だ。
フードコーディネーター・はらゆうこさん(48)。
トマトを切り、レタスをちぎり、盛り付けのバランスを丁寧に確認している。モニターに目を向けながら料理の出しどころを見計らっていると、美術スタッフが次回のピクニックシーンのお弁当の相談にやってきた。
「サンドイッチ用のパンじゃなくてもいいんじゃない?」
「いちごサンドは子どもが作った設定だから、ちょっとズレてるくらいが自然かも」
お弁当箱のサイズ、ウインナーの切り方、ブロッコリーの配置、フルーツの種類……。次々に飛んでくる質問に、はらさんは迷いなく応じる。会話をしながらも、視線は絶えずモニターとフライパンを行き来し、現場の空気を読む。
そしてリハーサルが始まると、草彅の横で皿の置き位置や調理の段取りを細かく確認する。
「草彅さんは、『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)で長年料理をされていたので、本当に手慣れているんです。盛り付けも上手で、私が手伝うことはほとんどないんですよ」
これまで手がけた作品は500本以上。ドラマ『VIVANT』『不適切にもほどがある!』(ともにTBS系)、映画『ゴールデンカムイ』など、多数の作品の食を担ってきた。
今作のアートコーディネーター・渡邊康典さんは、はらさんを指名する理由をこう語る。
「信頼感、安心感はもちろん、親しみやすい人柄も魅力です。ドラマによって料理のジャンルも時代設定もさまざまですが、台本から読み取り、こちらの要望に合わせて的確に提案してくれる。そこが本当にすごいんです」
時に、「溶けないケーキ」や「巨大プリン」、はては「お菓子の家」まで、むちゃなオーダーが出ることもめずらしくない。
「だいたい、大変なお願いが多いんです(笑)」と渡邊さんは笑う。
そんな難題を料理という形にするのがはらさんの仕事だ。
最近のドラマや映画は、食事シーンへのこだわりが年々強くなっていることを実感するという。かつては美術や小道具の一部にすぎなかった料理も、今では人物像や家族関係まで映し出す重要な要素。だからこそ、細部に宿る説得力が求められる。
印象的だったのは、『おいハンサム!!』シリーズの山口雅俊監督だ。料理の細部に徹底的にこだわる人で、目玉焼き一つにしても、「誰の分が半熟で誰が固めか」「黄身はどの程度とろっとさせるか」と細かい指示が飛ぶ。
サンドイッチのシーンでは、パンのサイズから切り方、さらに耳の部分で作るラスクの味にまで細かな指定が入り、オムライスでは納得のいく破れ方をめぐって全スタッフで議論したこともある。
「昼休憩に、撮影で使ったエクレアをみんなで食べていたら、監督が『やっぱり何か違う』と首をかしげ、結局午後にまた撮り直したんです(笑)」
こだわりの強さは役者にも見られる。堺雅人は最も印象深かった俳優の一人だ。段取りの段階から実際に食べながら動きを確認し、とにかく自然な食事シーンを追求する。
「『半沢直樹』(TBS系)では、テーブルに並んだ料理を本当に全部食べながら演じていました。セリフを言いながら自然に食べるのはかなり難しいため、食べやすいよう細かく切ることもあるのですが、堺さんは『そのままで』と、いっさい手を加えないことを望まれました」
また、作品に応じた料理表現を徹底する福澤克雄監督との仕事も忘れられない。『VIVANT』では、お赤飯の“色”に悩まされることに。
「『赤坂のとらやのお赤飯のように』という要望で実物を取り寄せたのですが、思っていた以上に深いピンク色で。そこから、もち米の蒸し時間、豆の煮方、煮汁の分量などを調整しながら何度も試作しました。でも毎回『もう少し研究して』と戻されて……。完成まで相当な時間を費やしました」
劇中に登場するモンゴル料理「ホーショール」も、監督のイメージを再現するところから始まった。餃子とピロシキの中間のような皮をのばし、具材を包んで揚げる。試作品にOKが出ず、作り直してようやく本番にこぎつけた。
『VIVANT』の現場は重要文化財など、料理の撮影には不向きな場所で行われることも多かったが、監督に、いつ「湯気を出して」と言われても対応できるよう、美術部とともに常に臨戦態勢を整えていた。
また北海道を舞台にした『ゴールデンカムイ』では、アイヌの伝統食を再現することが大きなテーマに。劇中たびたび登場する「チタタプ」(肉や魚を細かく刻んで作る料理)や「オハウ」(具だくさんの汁物)は、監修の先生が実際に作ったものを見せてもらいながら、現場で試作を重ねていった。
「オハウに使うリスやカワウソの肉は入手が難しいので別の肉で代用しています。チタタプも肉の種類で色が変わるため、鶏、豚、イノシシなど複数の肉を混ぜ合わせて、イメージからかけ離れないように調整しました」
求められるのは、細やかなコミュニケーションと瞬時の判断力だ。
「8年間の公務員生活やアシスタント時代の経験は大きかったと思います。相手が何を求めているのかを察知する力は、この仕事でとても大切なんです」
現場ではモニターを見ながら、俳優の動きや器の配置、食事の所作まで目を配り、監督の意図と照らし合わせながら瞬時に判断する。その“対応力”はフリーになってから最も鍛えられた力だ。
独立して約14年、その間に離婚と再婚、40歳での出産も経験した。
「娘をおんぶして撮影現場に行くこともありました。その経験があるので、私の事務所では子どもを連れて働ける環境づくりを意識しています。家族やスタッフの協力があってこそ、仕事と子育ての両立ができているんです」
現場は体力も神経も削られる。それでも続けてこられたのは、俳優やスタッフからの何げない一言があるからだ。
「『おいしかった』『またお願いします』って言っていただけると、どれだけ忙しくても全部報われる気がするんです」
そう語るはらさんに、仕事をするうえで大切にしていることを聞いた。
「フードコーディネーターはクリエイティブというより、要望を形にする仕事。だから私は、来た仕事はできる限り断らないと決めています。限られた条件でも、『できない』と言わずに方法を探す。それがこの仕事に求められていることだと思います」
取材のとき、「今後の目標は時代劇の料理や海外作品に挑戦すること」で、「そのためにもっともっと勉強したい」と語っていたはらさんだが、その言葉のとおり、11月からNetflixで配信されている岡田准一主演の新作ドラマ『イクサガミ』で念願の時代劇に挑戦している。
迷いながらも積み重ねてきた日々の“物語”があるから、はらさんの作る料理はどれも“演技上手”な名優たちなのだ。
画像ページ >【写真あり】はらさんがテキパキ料理する『終幕のロンド』のロケ現場(他1枚)