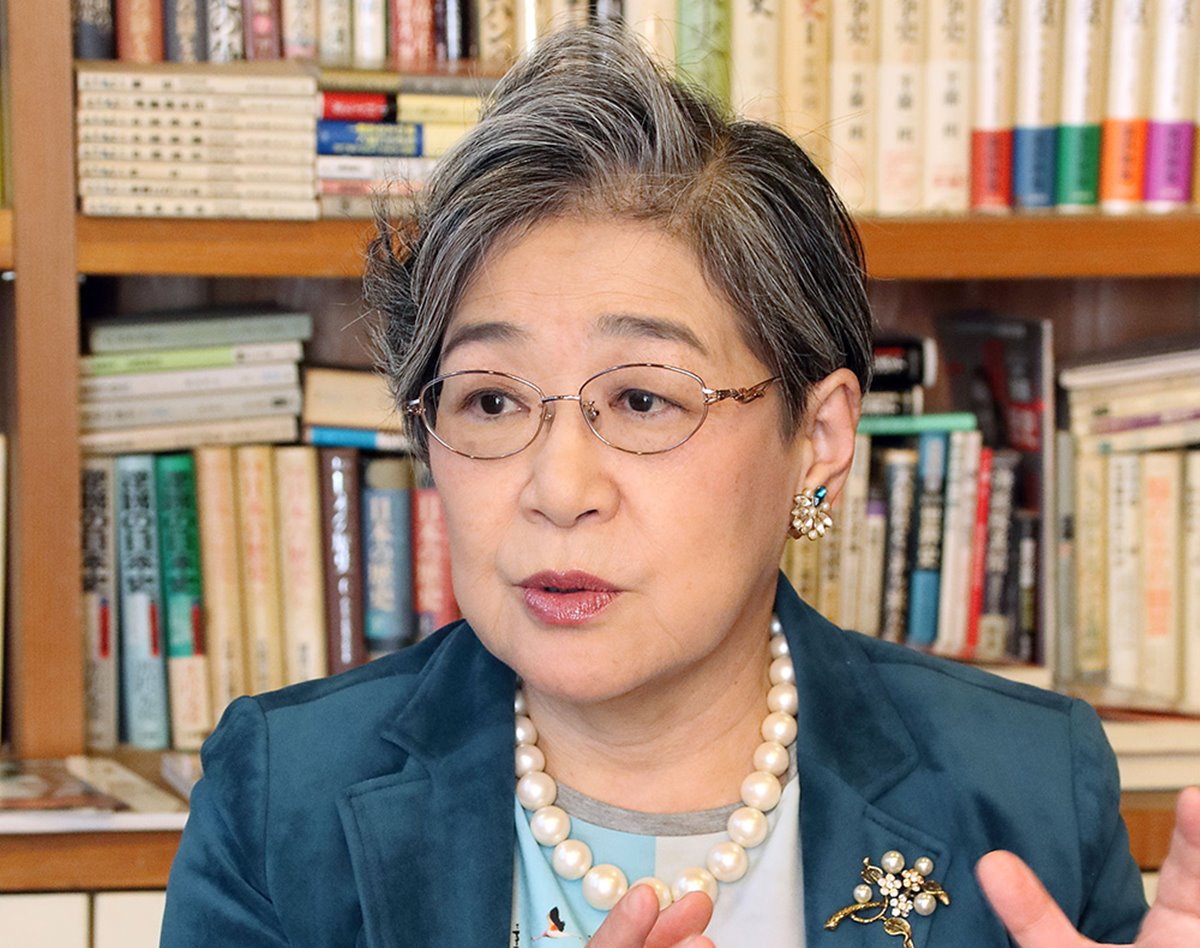春が近づくにつれ、果物売場はみかんに代わってオレンジ色の大きな果実が幅を利かせるように。でも最近のカンキツ系は「はるか」「アンコール」に「マーコット」など、知らない名前がいっぱい……。「もはや何が何だかわからない」という読者のために、200人の“みかん好き”を擁する「東大みかん愛好会」のみなさんに、教えを請うことにした。
そもそもカンキツとは、日本で誕生した温州みかんなどの「みかん」群、インド原産のバレンシアオレンジなどの「オレンジ」群、そしてみかんとオレンジの交雑種の「タンゴール」群などの総称。
一般的に「みかん」と呼ばれるのは、日本で誕生し、明治時代から盛んに栽培されている「温州みかん」のことだ。現在も日本のカンキツ出荷量の約7割が温州みかんだという。
「温州みかんとオレンジの交配はとても難しく、約30年もの研究の末にようやく成功したのが“奇跡の品種”と呼ばれる『清見』です。初のタンゴールである清見からはさまざまな品種が生まれ、カンキツ系の種類は爆発的に増えたんです」(平田徳明さん)
『清見』の誕生以降、どんどん複雑化していったカンキツ家系図には、「枝変わり」「交雑品種」などの聞きなれない言葉もある。
「カンキツは突然変異が多く、自然にできた品種を『自然交雑品種』と呼びます。また、1本の木の中で1枝にだけ変異種ができたものが『枝変わり』で、『甘夏』が代表的ですね。温州みかんの生産量日本一は和歌山県ですが、品種開発に積極的なのは愛媛県で、カンキツ系の生産量1位も同県です」(柘植一輝さん)
その愛媛県で続々と新種が生まれ、近年はスーパーなどで手に入る種類も飛躍的に増えた。なかでもおススメの品種は……。
「これからブームになるといわれているのは『はるみ』の子ども『あずみ』です。最高においしいんです!」(和久井綾香さん)
「注目の新品種は、昨年から栽培試験が始まった、『甘平』と『紅まどんな』の掛け合わせ『愛媛48号』。市場に出るのが今から楽しみです!」(東大みかん愛好会・冨田徳明さん)
すさまじい知識と愛ゆえに、おススメの仕方もマニアック。そもそも、なぜわざわざ東京大学で、みかんを研究しているのかを聞いた。
「みかん好きの東大生・清原優太が、日本のみかんの消費量が全盛期の3割以下に落ちていることに衝撃を受け、『みかんの消費量を増やす』という理念で立ち上げた団体です。現在では、産地とのコラボ企画やみかん尽くしの旅の提案など、幅広い活動をしています」(富田徳明さん)
彼らが声をそろえて主張するのは、一流農家が心を込めて作った果実のおいしさだ。
「スゴイ農家さんが作ったものは、食べると衝撃が走ります! ぜひ“農家狙い撃ち”で取り寄せをしてみてほしいです。そして、ぜひ、マイ・ベスト・カンキツを見つけてください!!」