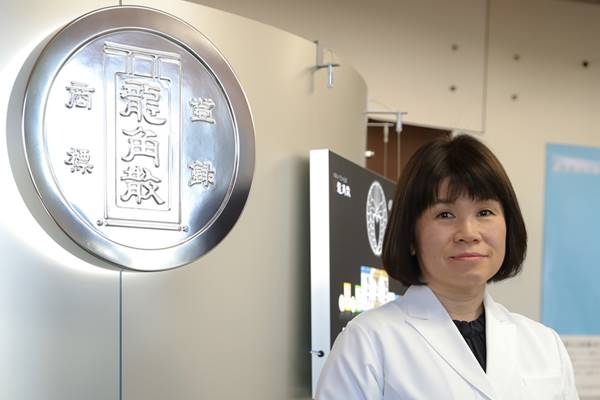製薬メーカー「龍角散」が販売する服薬補助ゼリーの1つ「おくすり飲めたね」。’08年、同社女性初の執行役員となった福居篤子さん(53)が、そのアイデアから開発、販売まで関わった大ヒット商品である。
「大きな錠剤やカプセル、苦い薬も、服薬ゼリーで包むと、子どもも、お年寄りでもすっと喉を通って、無理なく飲めるんです」(福居さん・以下同)
最近では老人ホームなどでも、服薬補助ゼリーはよく使われる。ゼリーのおかげで、粉薬が気管に入ってむせることも、薬を吐き出すこともなくなって、服薬の時間がスムーズになった。
「龍角散に勤める前、私は臨床薬剤師として、病院の薬局に勤務していました。そのとき多くの患者さんが薬を飲むのに苦労していること、病気を治すための薬というものが理解できない子どもにとってはただ嫌な行為であるということを痛感したんです。どうして飲みにくい薬を作るのか理解できず、全ての人にとって苦痛になっている課題を解決した新しい薬を作りたいと考えました。だから、臨床の世界から製剤の世界に移ったんです」
患者さんに寄り添いたい。守りたい。それが、福居さんの製薬の原点だ。
福居さんは’64年12月27日、広島で生まれた。親戚に尊敬する医師がいた影響で、いつしか医療の道を志すように。大学の薬学部薬剤学科に進学し、卒業後は患者さんと触れ合う仕事がしたいからと、臨床薬剤師として病院に就職した。その後、両親が住む近所の病院の薬局に転職すると、患者さんの薬の悩みを聞く機会が増えた。
患者さんの薬の悩みを聞いているうちに「どうしたら、楽に薬を飲めるのだろう」という疑問が、福居さんのなかで膨らんでいったという。
「それなら一度、薬を作る側に回ってみてもいのかな」
そんな思いで、新聞の求人欄で見つけた龍角散の採用試験を受け、合格。’91年、福居さんは26歳になっていた。
社長面接で、先代の社長に「うちは専門性を重視した縦割りの業務体系だが、横断的にいろんな部署をまたいで活躍してくれる人材が欲しい」と言われた福居さんは、「いろんなことにチャレンジできる」と、意欲満々だった。
しかし、入社してみると、200年を超える歴史ある企業には、旧態依然とした空気が蔓延していた。今と違って、男尊女卑の風潮も根強かった。職場のなかでも心臓部である製剤室は、まるで女人禁制の“聖域”だ。
「錠剤を作る機械にも簡単に触らせてもらえません。怒られるんじゃないんです。『作業中、指を落とした人もいるから、女性には危なすぎるわ~』と、優しく諭されるんです」
入社当初は、千葉工場勤務で、開発と兼任で、自社製品を営業するMR(医薬情報担当者)も任された。自作の資料を手に、熱心に説明して回り、瞬く間に営業成績トップクラスに。同期入社のなかで、誰よりも早く主任に出世し、30歳で本社勤務となった。
当時の龍角散は、40億円の年商に対して、40億円の負債を抱え、倒産の危機に瀕していた。しかし、社員の危機感は希薄で、保守的な古参役員には、会社を立て直そうという気概もない。
福居さんは、千葉工場時代から、新製品の開発を始めているが、そこには常に古参の役員との対立がついて回った。最初に取り組んだのは、鼻炎薬の開発だ。当時はまだ1日3回飲む薬が主流だったが、1日2回の服用で効く薬の開発に取り組んだ。
だが、苦闘の末に新製品が完成しても、古参の役員たちは、反対しかしない。開発した製品が、ことごとく否定され、嫌気がさして、転職を決意。別会社の内定をもらって、役員室に行ったこともあった。
「辞めさせてもらいます!」
福居さんの大きな声に、隣室から出てきて「私は1カ月後に社長になる。一緒に改革をしよう。一度、思う存分やってみてから辞めても、遅くはないよ」と、慰留したのが現社長の藤井隆太さんだ。
’95年10月、社長に就任した藤井さんを中心に、上司と福居さんの3人で改革チームが結成された。「もう龍角散だけでは生き残っていけない」と危機感を募らせる改革チームは、保守的な古参役員の反発を尻目に、新製品の開発を推し進めていった。
服薬補助ゼリーの開発を始めたのは、’97年ごろからだ。
「薬局で買って、その場で服用できるように、薬と一緒にパックされた水を開発してほしい」という営業からの要望がきっかけだった。そのとき思い浮かんだのは臨床薬剤師時代の経験だ。水では薬が飲めない患者さんを大勢、見てきた福居さんは、「ゼリーで包む」という画期的なアイデアを思いつく。
服薬補助ゼリーの試作品を作って、経営会議に提出した。だが、古参の役員からは「水を作れと言ったのに、なぜ、ゼリーなんだ」という声が上がる。当時は、嚥下機能が低下した高齢者が服薬で、誤嚥を引き起こし、肺炎につながるという事実や、嚥下機能が未熟な子どもの存在は、ほとんど知られていなかった。何度も現状を訴えたが、古参の役員たちは理解せず、製品化を認めようとしない。
「そんなに言うなら、介護現場を見てみよう」と言ってくれた藤井社長と一緒に訪ねた高齢者施設には、福居さんがかつて、臨床の現場で見ていたのと全く同じ光景が広がっていた。薬を食事に混ぜるため、食が進まず、苦悶の表情で食事をとる高齢者を目のあたりにして、社長は帰りの電車のなかで、「明日はわが身だな」と呟いた。
藤井社長は、古参役員の反対を押し切り、「服薬補助ゼリーは社会的意義のある製品だ。販売するのは、龍角散の使命だ!」と英断を下す。福居さんも、長年の夢だった「薬を飲みやすくする」製品の開発に夢中になった。
糖衣チョコを錠剤に見立て、ゼリーに包んで何十個も飲み込むなど、無謀ともいえる体を張った実験までした。’98年、ついにレモン味をつけた服薬補助ゼリーが完成する。
福居さんは、地域の医師会や医師の勉強会などにもサンプルと実験データを持って押しかけ、営業にも奮闘。介護施設でもそのニーズが高まっていった。ほどなく、子ども向けの服薬補助ゼリーを販売し、ヒット商品となった。