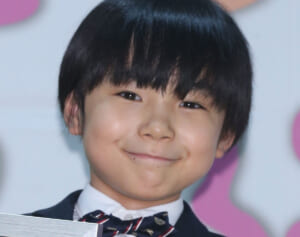■妻に依存し、甘えてしまっていたと振り返った
失った機能は戻らないが、工夫で補う。そんな津久井さんに「一緒に頑張ろう」と、寄り添ってくれたのが、妻・雅子さんだ。
「行き場のない苛立ちをぶつけたこともあったし、一緒に泣いたりもしました。でも“一緒に頑張ろうの勘違い”という“患者あるある”なんですが、助けてくれる家族に依存しちゃって、甘えてしまったりするんですね」
最近まで一緒の部屋で寝ていたが、津久井さんが寝返りをうてないために、雅子さんは一定時間ごとに体を動かしてあげた。仕事があれば現場に同行。「トイレ」と聞こえればかけつけ、時間がかかれば「早く~」と津久井さんに文句を言われる。心身共に雅子さんの負担は大きくて、体調を崩してしまったという。
「頑張っているのは妻だけ。でも、そんな姿を見て、ボクまで頑張っている気になっていたんです。ほんと、ボクのせいです」
津久井さんは、可能な限りヘルパーさんに頼るようにした。最初は他人が差し出すしびんでは、出るものも出ないし、お尻を拭かれることに抵抗があった。
「でもね、慣れればなんとかなる。5回分のおしっこにたえられる高性能のおむつだってあるので、つい先日から妻とは別室で寝ています。ゆっくり休んでもらいたい」
これからもさまざまな機能を失い、いずれは呼吸すら危ぶまれ、気管切開して人工呼吸器をつけるかどうかの選択を、迫られることになるだろう。人工呼吸器を選択すれば、ほとんどが声を失うことになるが、一定期間、長く生きられることが期待できる。若い人、子供が小さい患者は選択するケースが多い。一方、気管切開、人工呼吸器を選択しない場合、近い将来の死を意味することになる。
「どちらを選択するか、まだ決めていません。でも、ボクとしては、生死を選択するつもりはないんです。“どう生きるか”の選択です」
声の仕事をしてきて、多くの人とつながり、社会とつながってこられた。信頼できる友人は『口から生まれた口太郎なんだから(人工呼吸器は)つけなくてもいいんじゃないか』とアドバイスしてくれた。
だが一方で、あらかじめ録音した声を機械がつなぎ合わせ、意思を伝える技術が発達している。
「テクノロジーがより進化して“しゃべれる”のであれば、まだ生きたいって思い、人工呼吸器をつけるかもしれません」
津久井さんの中で、日々、考えは揺れているが─。
「じつはALSを発症する3年前に弟をスキルス性胃がんで、2年前、ALSの検査入院中に母親を亡くしているんです。胃ろうで命をながらえることを拒否すると言っていた弟は、その選択を迫られる間もなく、診断からわずか7カ月半で亡くなりました。母は心臓病を患い、入退院を繰り返しながら、最後は人工呼吸器につながりました。危篤から持ち直したときの『あれ(人工呼吸器)がなければ逝けたのか。もう何もしなくていいからね……』という言葉が、心に残っています」
こうした経験が、津久井さんの死生観に影響を与えている。
「気管切開、人工呼吸器の選択をどうするのか、100対0のようなはっきりした答えは出ません。でも、今のところ僅差の闘いで、51対49で、“しない”という答えです」
それが現時点での、津久井さんにとっての“生きる”という選択肢なのだ。