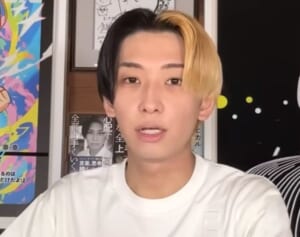■高校時代は美術クラブの人気者。’80年代サブカルチャーを席巻した鬼才の原点
’47年10月21日に熊本県天草市で生まれ、すぐに長崎市に移り住んだ蛭子さん。父親は遠洋漁業船の乗組員で、年の離れた姉と兄はすでに家を出ていたため、末っ子の蛭子さんは、ふだんは母親のマツ子さんと2人暮らしだった。
長崎市立商業高校を卒業後、地元の看板店に就職。その4年後の’70年、22歳のときに上京。広告代理店の看板部門で働きながら2歳年下の先妻と結婚。’73年、25歳のときに、白土三平や水木しげる、つげ義春が連載した漫画誌『ガロ』でデビュー。漫画家を目指したが、2人の子供を抱えていたため生活費を稼ぐためにチリ紙交換、ダスキンのサラリーマンを経験した。
蛭子さんが芸能活動を始めたのは’86年。蛭子さんは「素人の時代の波に乗って」とかつて語っていたが、タレントや俳優として八面六臂の活躍。怪しくて情けない笑顔、空気を読まない行動、不謹慎な発言が人気を集めた。あとは説明するまでもないだろう。
テレビを通して蛭子さんを知る人こそ多いが、ここでは絵の才能について振り返ってみよう。
長崎市立商業高校の美術クラブで蛭子さんとともに絵を描いていた土平啞倭子さん(75)が語る。
「グラフィックデザイナーの横尾忠則に憧れていた蛭子君は、グループ展ではギラギラ光るような絵をよく描いていました。でもそんなサイケデリックな絵は、県や市が主催するコンテストでは落選してしまうんですよ。そこで蛭子君は『市長賞を絶対とる』と審査員のことを調べ上げて『精密に描けば賞はとれる』と審査員の好みに合わせて木々を細かく描いていました。賞をとるためといえばしたたかだけど、憎めないんです」
そんな蛭子さんは美術クラブの人気者だったという。
「みんなは蛭子君のことが好きでした。しかめっ面を見たことがありません。毒気のあるひと言を言って笑わすんですが、わたしもよく“おまえは(肌が)黒かね”と言われました。あのヘラヘラした顔で言うから、みんな笑ってしまうんですよね」(土平さん)
看板店に勤めながら、友達が作った漫画クラブに参加していた蛭子さん。NHK長崎放送局に
「働きながら漫画を描いている青年」として取り上げられたこともある。
長崎市出身の漫画家でツージーQこと、辻村信也さん(68)が振り返る。
「中学1年生のときにテレビで紹介されたのが蛭子さんの漫画。長崎のシンボルの稲佐山の地下に宇宙船の基地があるというストーリーでしたが、きれいに色が塗られ、コマ割りも斬新。当時の主流だった手塚治虫さんの娯楽という範囲にとどまらない蛭子さんの漫画に驚きました。長崎にこんなすごい人がいるんだ、と衝撃を受けて、蛭子さんの漫画クラブに顔を出して教えてもらったことがあります」
漫画誌『ガロ』の編集者で、現在は、雑誌『アックス』を出版する青林工藝舎の手塚能理子さん(67)はこう話す。
「蛭子さんが『ガロ』に入選した’73年、私は一読者でしたが、不条理な展開、いらだちと妄想が入り交じる笑いで、それまでの漫画にはないパワーに圧倒されました。ヘタウマ漫画の祖といわれる湯村輝彦さんも、蛭子さんの入選作に影響を受けたと話していたくらい。
とくにコマのどこを切り取ってもポスター作品になるほどのデザイン力は天性のものでしょうね」
“いつもやる気がない”がトレードマークの蛭子さんには別の顔があったと手塚さんが続ける。
「’80年のあるとき、漫画だけでは食べられないから長崎に帰ると、蛭子さんが編集部を訪ねてきたことがありました。当時の社長が蛭子さんの才能を惜しんで『単行本を出してあげるから売れなかったら長崎に帰ればいい』と引き留めたんです。初の単行本『地獄に堕ちた教師ども』が発売されたら話題になって売れに売れました。蛭子さんも中央線沿線の書店を巡って『オレが描いたんです』と一生懸命に営業していました」
そう、蛭子さんは、’80年代のマイナー系の漫画の世界において旗手と目されていた。しかし、蛭子さんはその後、喜び勇んでテレビの世界に飛び込んでいった。